「老齢の親の介護費用が不足する」「自分の老後資金が心もとないし、健康状態にも不安がある」といった不安を抱える方は少なくないでしょう。
生活が苦しいときには生活保護を受ける選択肢があります。
では、生活保護を受けたときに介護サービスは利用できるのでしょうか。本記事では、生活保護と介護サービスの疑問にお答えします。
介護コンシェルジュに相談する受付時間 月~金:9:00~19:00 / 土:9:00~18:00
記事をシェアする
「老齢の親の介護費用が不足する」「自分の老後資金が心もとないし、健康状態にも不安がある」といった不安を抱える方は少なくないでしょう。
生活が苦しいときには生活保護を受ける選択肢があります。
では、生活保護を受けたときに介護サービスは利用できるのでしょうか。本記事では、生活保護と介護サービスの疑問にお答えします。
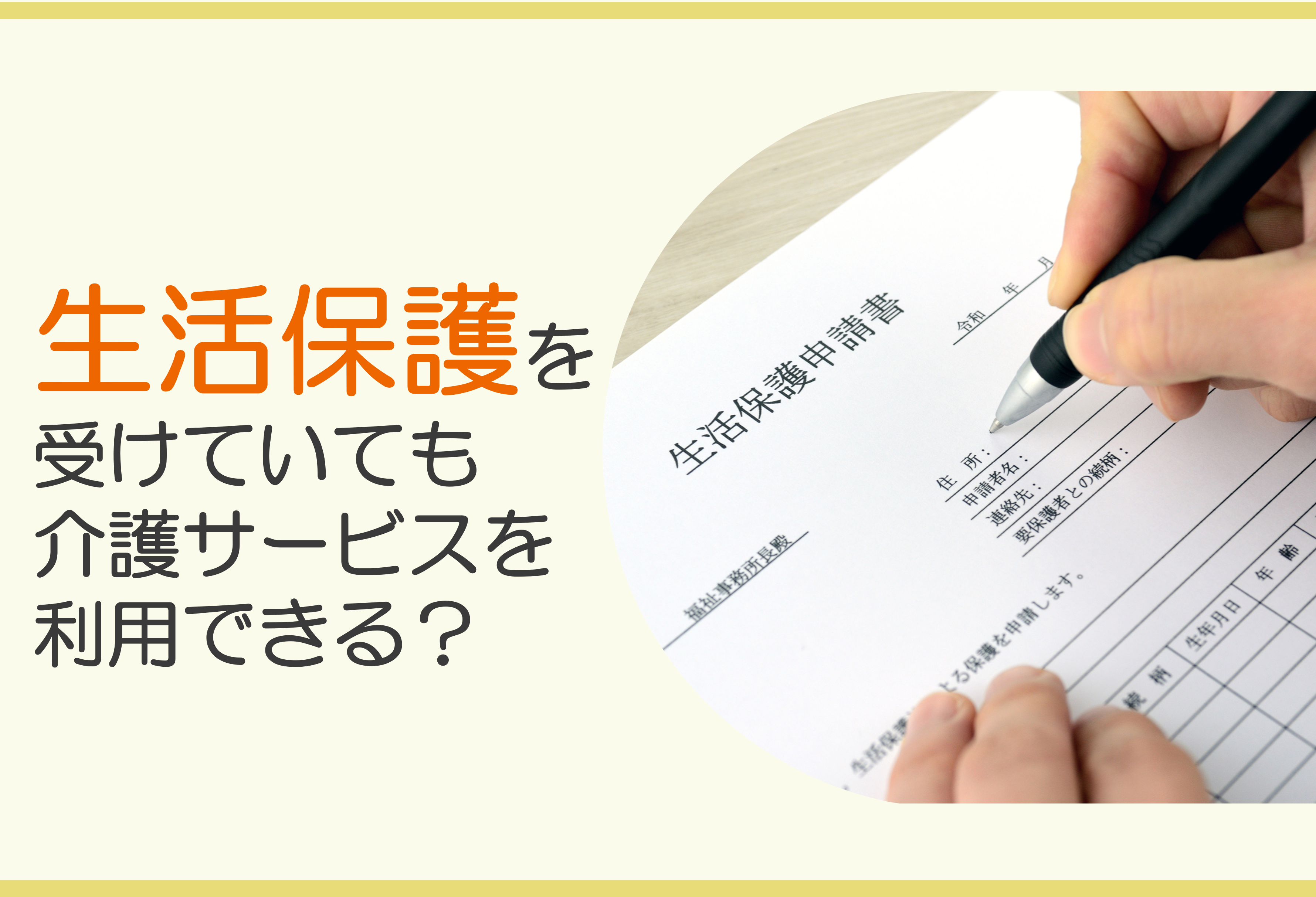



生活保護を受けている方が、介護サービスを利用するうえでは、まず「生活保護とはどのような制度なのか」を理解することが大切です。
生活保護は、生活に困窮する人が最低限度の生活を維持できるように、足りない生活費を支給する制度です。まずは、生活保護を受けるための基本的な条件と、生活保護によって受けられる「8つの扶助」について詳しく見ていきましょう。
生活保護は、原則として世帯全体の収入や資産をもとに判断されます。たとえば親と子が一緒に暮らしていれば、その収入を合算して、世帯全体で保護が必要かどうかが判断されます。世帯の収入が、国が定めている最低生活費を下回っている場合には、不足分が「生活保護費」として支給されますが、超える場合は生活保護は受けられません。
その他、「働くことができない」「使える貯金や財産がない」といった利用要件も加わります。生活保護は、ただ世帯収入が低いだけではなく、資産や能力などを活用してもなお生活に困窮する方に対して支給されるものです。
生活保護では、必要に応じて、以下の扶助(ふじょ)が支給されます。
| 扶助の種類 | 支給方法 |
|---|---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用 (例)衣食、水道光熱費など | 定められた基準額を支給 |
住宅扶助 | 住居に関する費用 (例)家賃、地代など | 定められた範囲内で実費を支給 |
教育扶助 | 子どもが義務教育を受けるための費用 (例)学用品、給食費など | 定められた基準額を支給 |
医療扶助 | 医療に関する費用 (例)診察・治療費、薬剤費、入院費など | 現物給付 |
介護扶助 | 介護に関する費用 (例)介護保険サービスの利用 | 現物給付 |
生業扶助 | 高等学校の費用 就職するために必要な技能・資格の取得のための費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
出産扶助 | 出産に関する費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭扶助 | 葬儀の費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
医療扶助および介護扶助については「現物支給」となり、費用が直接医療機関へ支払われる仕組みです。そのため、本人の費用負担はありません。
ここからは、介護サービスを受ける場合に関連の深い「介護扶助」「医療扶助」「住宅扶助」「生活扶助」の4つについて詳しく解説します。
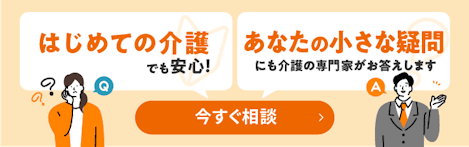

公的な介護サービスは介護保険制度を通じて提供され利用する場合、 通常は介護サービス利用料の1割(所得に応じてまたは2〜3割)を自己負担する必要があります。
しかし、生活保護を受けている方は、この自己負担分が「介護扶助」でカバーされるため、実質的な負担なしで介護サービスを受けることが可能です。
|
※ケアプランの作成料も全額が介護扶助の対象となります。
※介護度に応じて定められている支給限度額を超えるケアプランは認められません。
生活保護を受けている方は、介護扶助によって介護サービスを原則自己負担なしで利用できます。しかし、その仕組みは、介護保険制度に加入する年齢によって異なることを知っておきましょう。
通常、65歳以上は原則として「第1号被保険者」として介護保険に加入し、介護保険料を支払います。そして、公的な介護サービスを利用する際は、所得に応じて1〜3割の自己負担が生じます。
しかし、生活保護を受けている方は、介護保険料は「生活扶助」、介護サービスにかかる費用は「介護扶助」でカバーされるため、実際の費用負担はありません。
40~64歳の場合、通常は医療保険とセットで介護保険に加入します(第2号被保険者)。ただし、生活保護を受けている方の多くは国民健康保険の適用から除外され、医療保険の未加入者となるため、介護保険の被保険者とはなりません。
例外として、16種類の病気(=特定疾病)のいずれかによって要介護または要支援の認定を受けた場合は「みなし2号」として扱われます。
この場合、保険料は免除されつつ、介護サービスの対象となり、介護扶助によって費用全額が補助されるため、実質的な自己負担はなく介護サービスを受けることができます。
特定疾病に該当する病気は、以下からご確認ください。
厚生労働省|特定疾病の選定基準の考え方
なお、特定疾病に該当しない40〜64歳の生活保護受給者でも、障害者総合支援法に基づいて必要性が認められれば、ホームヘルパーなどの支援を受けられる可能性があります。
介護扶助を受けるには、以下の流れで手続きが進みます。
|
具体的な手続きや必要書類は、自治体によって異なる場合があります。介護扶助の手続きする際は、事前にお住まいの自治体の福祉事務所にて流れを確認しておくと安心です。

生活保護を受けている方でも介護施設に入居することは可能です。
介護施設内で提供される介護サービスは「介護扶助」によって現物給付されますが、その他に、「住宅扶助」と「生活扶助」「医療扶助」が活用されます。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
施設の家賃にあたる費用は、「住宅扶助」で支援されます。
市区町村によって支給上限は異なりますが、単身者の場合、月額5万円程度が目安といわれています。この範囲内で収まる施設を選べば、自己負担は基本的にありません。
ただし、施設によっては生活保護を受けている方を受け入れていない場合や、定員数が決まっている場合もあるため、注意が必要です。
介護施設での日々の食事や施設内の管理費、水道光熱費、日用品などの生活費は、「生活扶助」として支援されます。
こちらも地域によって金額が異なりますが、単身者の場合で月6〜7万円程度が一般的な支給額の目安といわれています。
ただし、生活扶助は実費の支給ではなく、定められた基準額が支給される仕組みのため、実際にかかった金額がすべて支払われるわけではありません。
そのため、生活扶助の範囲内で生活できる施設を探すとともに、毎月の支給額のなかでやりくりする必要があるでしょう。
介護施設に入居した後に、ケガや病気をしたときは医療扶助の適用を受けます。この場合の医療費は、「医療扶助」によりカバーされますが、以下のような制限もある点に注意が必要です。
|

生活保護を受けながら介護施設に入る場合は「受け入れ可能な施設かどうか」を事前に確認することに加え、費用が住宅扶助・生活扶助の範囲内に収まるかをチェックすることが重要です。施設によって入居のしやすさも異なるため、比較しながら検討しましょう。
以下、生活保護を受けている方にとって、入居の選択肢となりやすい介護施設をまとめました。
施設 | 条件・注意点 | 備考 |
|---|---|---|
特別養護老人ホーム |
| 公的施設のため利用費用が安いが、地域によっては入居待ちが多い。 |
ケアハウス(C型) |
| 公的または社会福祉法人などが運営しており、費用が比較的安価。 |
グループホーム |
| 地域密着型で家庭的なケアが可能だが、費用が扶助範囲に収まるかがポイント。 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
| 比較的自由な住環境だが、費用が扶助範囲に収まるかがポイント。 |
費用の観点から、もっとも現実的なのは「特別養護老人ホーム」でしょう。しかし、入居希望者が多いため、事前に申し込みを行い、空きが出るのを待つ必要があるかもしれません。
一方、民間施設は選択肢が限られますが、中には生活保護を受けている方を積極的に受け入れている施設もあります。
制度や地域条件によって事情は変わるため、入居希望の際は自治体の福祉窓口やケアマネージャー、「マイナビあなたの介護」に相談するのがおすすめです。

生活保護を受給していても、「介護扶助」によって自己負担なく介護サービスが受けられ、「住宅扶助」や「生活扶助」により介護施設への入居も可能です。また、「医療扶助」で、診察や治療も安心して受けられます。
ただし、利用には制度の理解と事前準備が重要です。ケアマネージャーにも相談しながら、生活保護と介護制度の両方を正しく使いましょう。
介護にまつわる質問は、「マイナビあなたの介護」でも気軽に相談することができます。
施設探し、介護準備のサポート、資料請求・見学申込の代行など、幅広く支援を行っていますので、ぜひお試しください。LINEや電話などから、いつでもアドバイスを受けることができます。

FPサテライト所属 ファイナンシャルプランナー
堀田 絵里奈(ほりた えりな)
FPサテライト所属 ファイナンシャルプランナー
堀田 絵里奈(ほりた えりな)
現在は独立系FPとして執筆業務をはじめ幅広く活動中。
現在は独立系FPとして執筆業務をはじめ幅広く活動中。