高齢になると、自宅での転倒や入浴中の事故などにとりわけ注意が必要となります。
介護保険の住宅改修費支給を利用すれば、介護のプロに相談しながら自宅を安全にリフォームでき、金銭面の負担も軽減されます。
申請方法や注意点などについて、詳しく確認していきましょう。
介護コンシェルジュに相談する受付時間 月~金:9:00~19:00 / 土:9:00~18:00
記事をシェアする
高齢になると、自宅での転倒や入浴中の事故などにとりわけ注意が必要となります。
介護保険の住宅改修費支給を利用すれば、介護のプロに相談しながら自宅を安全にリフォームでき、金銭面の負担も軽減されます。
申請方法や注意点などについて、詳しく確認していきましょう。




年齢を重ねると、ちょっとした段差などが移動の妨げになり、活動量の低下につながってしまうことがあります。また、高齢期では家庭内で不慮の事故に遭うことが増え、特に「つまずきなどによる転倒」や「浴室内での溺死・溺水」などが多く発生している点は見逃せません。
こうした事故を防ぎ、安全に過ごすために効果的なのが、自宅のリフォーム(住宅改修)です。住み慣れたわが家であっても、加齢による心身の変化に応じて「求められる住環境」が変わっていくことを知っておきましょう。
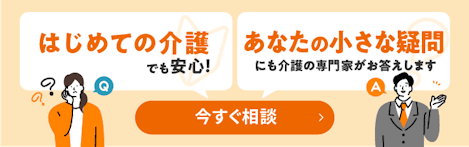

高齢期に必要な自宅のリフォームとは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか。住環境と合わせて、本人の運動機能や生活習慣などからも、必要な介護リフォームの内容が見えてきます。
身体機能の低下によって歩行時にふらつくようになると、動くこと自体が億劫になったり、転倒の不安を抱いたりする場合があります。そうした人にとって、距離の長い廊下や急な階段はリスクが高い場所と言えるでしょう。
そこで、手すりを設置して安全に家の中を行き来できるようになれば、転倒を予防するだけでなく自然に活動量が増え、心身の健康維持につなげることができます。
家の中で車いすを使うようになった時、畳の上では車輪が沈み込みやすいため、スムーズに動かしづらく感じるもの。床材をフローリングに張り替えれば自走が円滑になる上、介助する家族の負担も減らすことができます。
その他にも、扉を引き戸に取り替えて少ない力で開閉できるようにしたり、玄関の段差をスロープにしたりと、自宅のさまざまな部分に少し手を加えるだけで、車いすを利用することになっても快適に生活しやすくなります。

リフォームが必要であると認められた人に対しては、かかった費用の一部を介護保険で負担してもらえる制度があります。
対象となる改修の種類や支給額の限度など、さまざまな条件があるので、事前に当てはまるかどうかをチェックしておきましょう。
要支援1~2、あるいは要介護1〜5の認定を受けていて、介護保険被保険者証に記載されている住所に住んでいる場合に支給対象となります。
入院していたり介護施設などに入所していたりする場合には対象外となるので注意しましょう(ただし、病院や施設から自宅に戻ることが決まっており、その先の日常生活において必要なリフォームであると認められれば支給対象となるケースがあります)。
あくまでも、申請時に居住している家屋のリフォームに対して支給される制度なので、新築の建設や増改築などにかかる費用については対象となりません。
リフォームにかかった費用の全額を介護保険で負担してもらえるわけではありません。
要支援と要介護のいずれであっても、支給限度基準額は20万円です。
保険給付は原則9割(上限18万円)で、所得などに応じて8割(上限16万円)や7割(上限14万円)になることがあります。
本制度の利用回数は、原則1人1回まで。ただし、20万円の限度額の範囲内であれば、複数回申請することができます。
また、要介護認定の区分が3段階以上(※)上昇したり、別の家屋に転居したりした場合には、もう一度支給を受けることができます。
(※)要支援2と要介護1はまとめて一段階とみなす
介護保険のサービスでは、以下の介護リフォームにかかる費用が支給対象となります。自宅の場所や形状などによって金額はさまざまです。
|

住宅改修費の支給を受けるまでには、主に7つのプロセスがあります。
少し複雑に感じられるかもしれませんが、申請のタイミングや必要な書類など大事なポイントを押さえておけば、ミスを防ぐことができます。しっかりと確認していきましょう。
お住まいの市区町村の介護保険認定担当係に要介護認定の申請を行います。提出する申請書や身分証明書など、自治体によって決まりがあるためウェブサイトなどで確認しておきましょう。
その後、認定調査などにより介護が必要な度合いが調査され、認定を受けると介護保険サービスを受けられるようになります。
介護保険の住宅改修費支給を受ける際には、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談しましょう。家の中で不便を感じることや予算の上限などを伝えると、専門的な見地から必要な改修についてアドバイスを受けることができます。
改修内容が決まったら、リフォーム業者の選定に入ります。
受領委任払制度(※)を利用したい場合など、自治体への登録事業者に依頼することが条件になるケースもあるため、地域の窓口に確認してみましょう。
(※)被保険者が自己負担分を業者に支払い、残りを自治体から業者に支払う制度
見積り依頼などを経て業者を決めたら、着手に向けて打ち合わせを進めていきます。ケアマネジャーなどが同席し、自宅の現地調査を行うこともあります。
そして、「住宅改修が必要な理由書」を作成します。これはリフォームのプランなどを記したもので、ケアマネージャー、地域包括支援センターの担当職員、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者などが作成を担当します。
理由書が完成したところで、市区町村の窓口へ事前申請を行います。
「支給申請書」「住宅改修が必要な理由書」「工事費用の見積り書」「完成予定の状態を示す図面や写真など」を提出することが基本ですが、地域によって詳細が異なる場合もあるため、準備段階で確認しておきましょう。
審査結果は後日通知されます。通知を受け取る前に施工を開始すると支給対象外になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
審査を通過したという通知を受け取ったら、いよいよ工事に入ります。作成したプランに沿って業者が工事を進めていくので、随時確認しましょう。
次のプロセス(事後申請)で改修箇所の写真や詳しい費用の内訳を提出する必要があるため、工事中から業者に相談しておくとスムーズでしょう。完了したら、支払いを行います。
再び市区町村に申請を行います。この事後申請では「リフォームに要した費用に係る領収書」「工事費内訳書」「リフォームの完成後の状態を確認できる書類(写真)」「住宅の所有者の承諾書」などが必要になります。
事後申請の内容が認められると、支給金を受けることができます。
費用を全額負担した場合には、介護保険の適用分から利用者負担分を差し引いた金額が振り込まれます。
自己負担分のみを支払った場合には、自治体から業者へ残りの代金が直接支払われます(受領委任払制度)。

介護リフォーム費用の支給を受ける場合、工事の「着手前」に自治体への申請が必要なことを忘れないようにしましょう。着工前の申請が、保険給付の前提となります(ただし、やむを得ない事情がある場合には工事完成後の申請も可とされています)。
新築や増改築、住宅の老朽化を原因とする修繕工事など、施工の内容によっては支給の条件から外れる場合があるため気をつけましょう。
なお、住宅が賃貸物件の場合でも、家主の承諾が得られれば改修できますが、退去の際に修繕費を負担することになる可能性があります。無断で改修を進めることはNG。しっかりと家主に許可を取り、退去時のことについても話し合っておきましょう。
また、業者を選ぶ際には焦り過ぎず、ケアマネージャーなどの意見を聞きながら慎重に検討したいところ。できれば、複数の業者から見積りを取ることがおすすめです。
「住み慣れた自宅でこれからも暮らし続けたい」と願う人は多いもの。しかし、それを実現するためには、現在の住環境から課題を見つけ、リスクや不便さを減らすことがとても重要です。介護リフォームだけでなく、福祉用具のレンタルサービスなども取り入れると、より細かい部分にも手が行き届くようになります。
また、介護保険サービス以外にも、自治体が独自に介護リフォームの補助事業を行っている場合があります。介護保険と併用できるものや要介護認定を受けなくても使えるものなど、その内容はさまざま。興味がある人は、お住まいの地域の窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。

住環境を改善すると、介護をする側とされる側、双方の負担を減らすことができます。介護保険サービスにより出費を抑えられる点も心強いですね。介護リフォームにはたくさんの選択肢があるので、ケアマネージャーなどとよく相談し、いろいろな角度から検討を重ねていきましょう。
もし、リフォームや福祉用具の導入で不安が解消されない場合には、介護施設への入所を考え始めてもよいかもしれません。
介護施設選びに迷った時は、「マイナビあなたの介護」で相談できます。LINEや電話からのお問い合わせも受け付けているので、介護にまつわるお悩み事があれば、どうぞお気軽にご利用ください。

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。