福祉用具を適切に利用することで、可能な範囲で自立した生活を在宅で送れるようになります。本記事では、「福祉用具を借りたい」「どれくらい費用がかかるのか知りたい」と考えている方に向けて、福祉用具貸与でレンタルできる13品目を介護度別に紹介します。
また、福祉用具貸与をレンタルするメリット・デメリット、利用料金、利用の流れについても紹介しているため、ぜひ福祉用具貸与のサービス検討の参考にしてください。
介護コンシェルジュに相談する受付時間 月~金:9:00~19:00 / 土:9:00~18:00
介護の費用と経済的支援を知る
記事をシェアする
福祉用具を適切に利用することで、可能な範囲で自立した生活を在宅で送れるようになります。本記事では、「福祉用具を借りたい」「どれくらい費用がかかるのか知りたい」と考えている方に向けて、福祉用具貸与でレンタルできる13品目を介護度別に紹介します。
また、福祉用具貸与をレンタルするメリット・デメリット、利用料金、利用の流れについても紹介しているため、ぜひ福祉用具貸与のサービス検討の参考にしてください。


福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)とは、介護保険制度の居宅サービスの一つです。利用者が可能な範囲で自立した生活を在宅で送れるように、さまざまな福祉用具をレンタルできるサービスです。
福祉用具は原則レンタル支給ですが、腰掛便座や簡易浴槽など他の利用者が使用したものを再度利用することに心理的な抵抗感があるものや、スロープや歩行補助つえなど使用を重ねることで品質や形が変わるものは特定福祉用具として販売の対象となります。
指定を受けた事業者が利用者の心身の状況や生活環境、そしてニーズをふまえたうえで、適切な福祉用具を選ぶ手助けや取り付け、調整などを行います。
サービスの利用は介護保険の対象となり、自己負担は1~3割で済むため、レンタルにかかる費用的な負担が軽減されるでしょう。
要介護者や要支援者が在宅で自立した暮らしを手助けするために、利用する用具が「福祉用具」です。介護保険制度では、治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用し、起居や移動などの基本動作の支援を目的とするものと定義されています。
貸与された福祉用具は基本的に在宅で使用し、取り付けに住宅改修工事を伴わないものが対象です。
使用例として、車いすを使用すれば脚に麻痺などの障害があっても、移動できるようになることが挙げられます。また、介護ベッドを使用すれば、ベッド柵を活用して利用者が自力で起き上がれるようになるでしょう。
福祉用具を使用することで、介護者の心配や負担も軽減も見込めます。
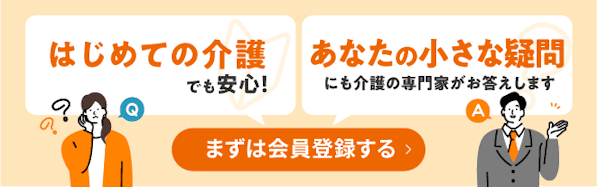

福祉用具をレンタルするメリットやデメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|---|
福祉用具貸与(レンタル) | ・費用負担が少ない ・状況に応じて交換が可能 | ・使用期間が限られる |
特定福祉用具販売(購入) | ・高額になりやすい | ・長期間使用できる |
福祉用具貸与の利用後は、福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンスも行ってもらえるため、安心して福祉用具を利用できます。
福祉用具を効率よく使用するためには、購入とレンタルを使い分けることがポイントです。長く使い続けられるものは購入し、交換する頻度が高くなる可能性があるものはレンタルしましょう。

介護保険制度を使用してレンタル可能な福祉用具は、13品目あります。利用者がレンタルできる福祉用具の対象は、介護度によって異なります。ここからは、介護度別に利用できる福祉用具を見ていきましょう。
要支援1・2、要介護1~5のすべての方が利用できる福祉用具は以下の通りです。
| 備考 |
|---|---|
手すり | 取付工事が必要ないものが対象。 |
スロープ | 取付工事が要らず、段差の解消を目的とするものが対象。 |
歩行器 | 歩行が難しい利用者が歩いて移動する際に、体重を支えられるもので、以下のどちらかに当てはまるものが対象。 ①身体の左右前方を囲んだつかむところがあり、車輪があるタイプ ②4本足があり上肢で掴まって移動できるタイプ |
歩行補助つえ | 松葉づえやカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、あるいは複数の脚がある多点杖が対象。 |
自動排泄処理装置 | 利用者本人・介護者が簡単に使用でき、尿や便が自動的に吸引されるもの。尿や便の経路部分が分割できる構造のものが対象。 |
要介護2以上の方が利用できる福祉用具は、次の通りです。
| 備考 |
|---|---|
車いす | 自走用標準型・普通型電動・介助用標準型の車いすが対象。 |
車いす付属品 | クッション・電動補助装置など、車いすと一体で使用するものが対象。 |
特殊寝台 | サイドレール取付け済み、もしくは取付け可能な以下どちらかが対象。 |
特殊寝台付属品 | 特殊寝台と一緒に使用され、マットレスやサイドレールなどが対象。 |
床ずれ防止用具 | 以下の①②どちらかにあてはまるものが対象。 ①送風装置や空気圧調整装置がある空気マット ②減圧可能で、体圧分散効果のある全身用のマット |
体位変換器 | 体位保持のみを目的するものではなく、空気パッドなどを利用者の体の下に入れ込み、体位変換を簡単に行える機能があるものが対象。 |
認知症老人徘徊感知器 | 認知症の方が家から出ようとした際に、センサーが感知して家族や隣人などに知らせるもの。 |
移動用リフト | 身体をつり上げ、体重を支える構造で自力での移動が難しい方の移動をサポートするもの。取付け工事が要らないものが対象。 |
要支援1・2、要介護1と認定された方は、上記の福祉用具は原則として利用が認められていません。しかし、医師の医学的な所見に基づき、ケアマネージャー等が必要性を判断し、「例外給付」の条件を満たすことが認められた場合、例外的にレンタル可能な場合があります。
上記は医師による医学的な所見に基づいて判断され、その後、サービス担当者会議を経て福祉用具貸与が必要である旨を市町村が確認し、認められた場合に「例外給付」が認められます。
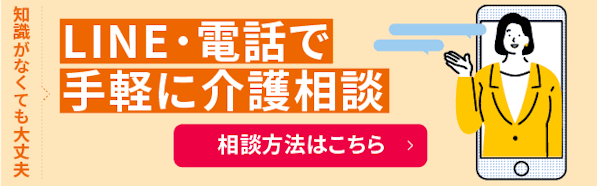

福祉用具をレンタルする際は、介護保険制度を活用することで自己負担額の軽減が可能です。また、福祉用具貸与のサービス利用開始日や解約日によって利用料金が半額になる場合もあります。以下で詳しく説明します。
福祉用具貸与は、ほかの介護サービス同様に介護保険制度が適用されるため、購入するより料金を抑えて福祉用具を利用できます。
利用料金は利用する対象品目によって変動しますが、利用料金の自己負担額は原則1割程度です。ただし、所得に応じて2~3割負担になることもあるため注意が必要です。
例として、1割負担が適用される場合、1ヶ月のレンタル料金が10,000円だと、負担料金は1,000円となります。
レンタルの料金は原則、月額で設定されています。しかし、福祉用具貸与を契約した日によっては、半月も利用していないケースもあり、そのような場合では支払う料金は1ヶ月分の料金の半額となります。
ただし、レンタルの開始と解約が同じ月である場合は1ヶ月分の料金を払う場合もあるため注意しましょう。
介護保険は要介護度別に1ヶ月の支給限度額が決まっています。限度額を超えて利用すると超過分については全額負担となるため、他の介護サービスを利用する中で、限度額に応じた福祉用具をレンタルしましょう。

介護保険制度を使用し、福祉用具貸与サービスを利用するまでの流れは、以下のとおりです。
|
福祉用具の利用を希望する場合、まず担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しましょう。
また、福祉用具に関する疑問や不安は、福祉用具専門相談員に相談しましょう。「福祉用具専門相談員」とは福祉用具の貸与や販売を行っている事業所に所属し、利用者さんやご家族に福祉用具の適切な選び方や使用方法をアドバイスする専門職です。福祉用具の使用を希望する際は福祉用具専門員の提案やアドバイスを参考にして、自分に合う最適な福祉用具を提案してもらいましょう。

福祉用具貸与は、介護保険が適用されるため、購入するよりも手頃な金額で福祉用具が利用できます。福祉用具を上手く活用することで、利用者の起居動作や移動などの日常生活動作をサポートでき、自立した生活の支援ができます。また、介護者の負担軽減にもつながるため、双方にメリットがあります。
制度の利用を検討する場合、まずはケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しましょう。少しでも長く、安心して在宅での生活が送れるように環境を整えることが大切です。
マイナビあなたの介護でも介護に関するお悩みをLINEや電話で相談することができます。最適な施設探しから介護準備のお手続きのサポートなど幅広く対応します。
どんな些細なお悩みでも、まずはご相談してみるのはいかがでしょうか。
参考URL
厚生労働省|福祉用具貸与(参考資料)
厚生労働省|どんなサービスがあるの? - 福祉用具貸与
厚生労働省|福祉用具・住宅改修に関する法令上の規程について
一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会|介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。