ご家族の介護をしているなかで、「今の状態と介護度が合っていない気がする」「介護サービスが足りない」と感じたことはありませんか?
そのようなときは、介護認定を見直すことで、介護をするご家族の負担が軽減する可能性があります。
この記事では、介護認定を見直すメリットやタイミング、手続きの流れ、注意点について解説します。無理のない介護を続けるために、ぜひ参考にしてください。
介護コンシェルジュに相談する受付時間 月~金:9:00~19:00 / 土:9:00~18:00
記事をシェアする
ご家族の介護をしているなかで、「今の状態と介護度が合っていない気がする」「介護サービスが足りない」と感じたことはありませんか?
そのようなときは、介護認定を見直すことで、介護をするご家族の負担が軽減する可能性があります。
この記事では、介護認定を見直すメリットやタイミング、手続きの流れ、注意点について解説します。無理のない介護を続けるために、ぜひ参考にしてください。
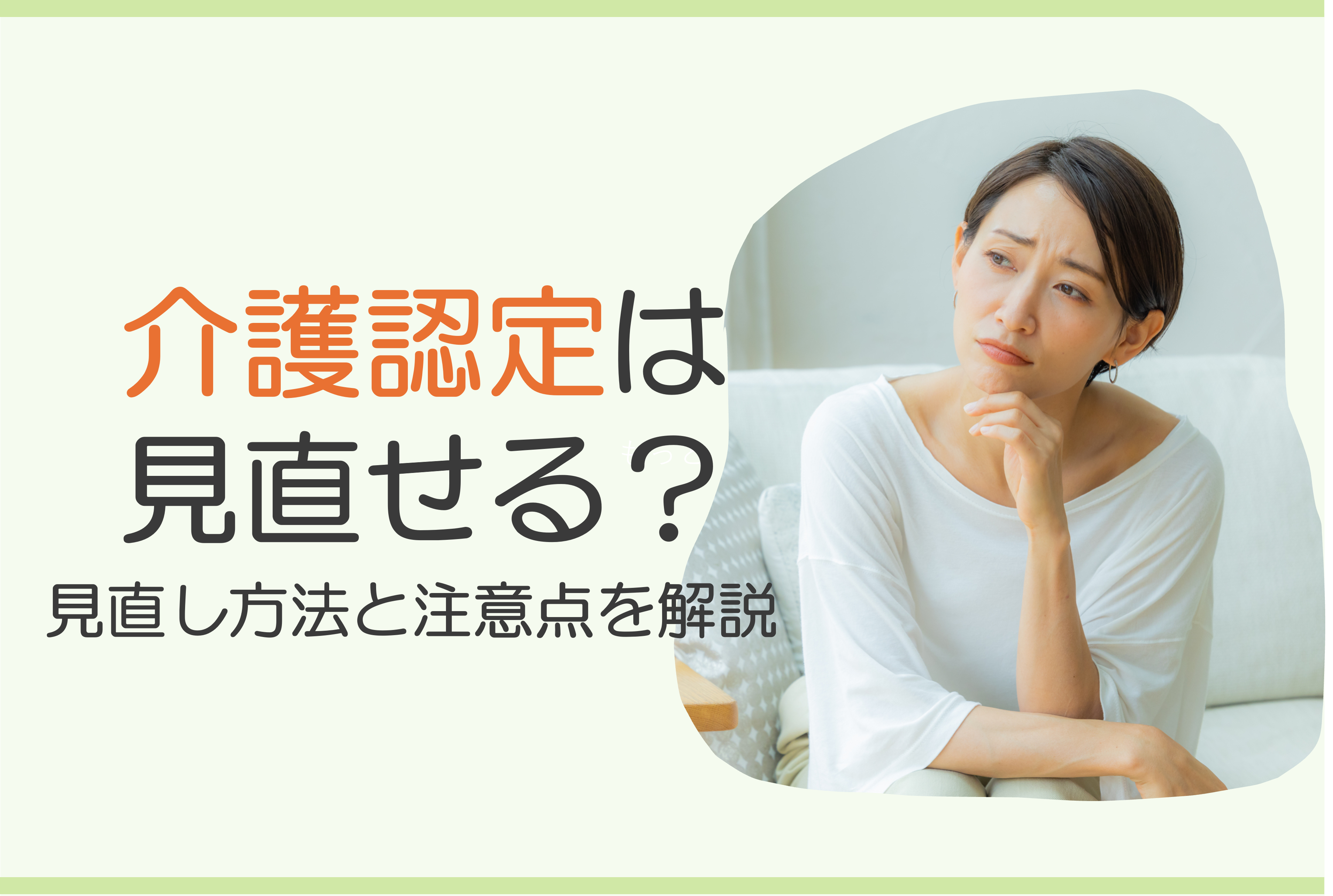



要介護認定の見直しは、介護を受けるご本人と介護をする方にとって次の3つのメリットがあります。
要介護度が上がると、利用できるサービスの種類が増えます。
たとえば、要介護2から要介護3になると、特別養護老人ホームの入所対象となり、自宅以外の選択肢が広がります。状況に合った支援が受けやすくなり、生活の安定にもつながります。
要介護度が上がると、介護保険で利用できるサービスの上限(支給限度額)も増えます。
たとえば、要介護2の支給限度額は19,705単位ですが、要介護3になると27,048単位に増加します。
限度額が増えることで、訪問介護やデイサービスなど、必要な介護サービスをより多く、無理なく利用できるようになります。これも、介護認定を見直す大きなメリットのひとつです。
適切な要介護度に見直されることで、必要な支援が受けやすくなり、家族や介護者の負担が軽減されます。訪問介護やデイサービスの利用が増えれば、介護者にも休息や自分の時間が生まれ、無理なく介護を続けやすくなります。
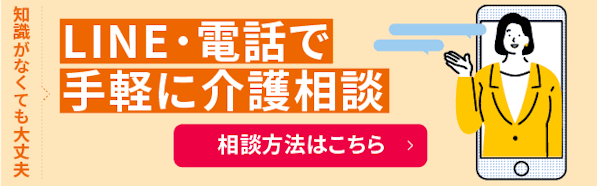

では、どのようなときに介護認定を見直すべきなのでしょうか。ここでは、見直しを検討する主なタイミングをご紹介します。
もっとも分かりやすい見直しのタイミングは、ご本人の心身の状態に大きな変化があったときです。
たとえば、脳梗塞や心疾患などの病気を発症した場合や、持病が悪化した場合。また、転倒による骨折や事故によるけが、入院や手術によって体力や生活動作に大きな影響が出たときも該当します。
さらに、認知症の進行によって物忘れがひどくなったり、一人歩きが始まったりと、行動や意思疎通に変化が見られるようになった場合も早めに介護認定の見直しを検討しましょう。
状態の変化は、必ずしも急激に起こるとは限りません。要介護認定を受けた当初は安定していたものの、少しずつ介助が必要な場面が増えてきたと感じることもあります。
たとえば、自立して行えていた食事や排せつに、サポートが必要になってきたといった場合です。「今の要介護度と、実際の状態が合っていない」と感じたときも、見直しを検討すべきタイミングです。
実際に筆者が担当していたケースでは、認知症が進行し、以前より介護の手間が大幅に増えた利用者様がいらっしゃいました。ご家族と相談のうえ、介護認定の見直しを行い、要介護度が上がった結果、利用できるサービスが増え、ご家族の負担が減ったというケースがあります。
現在の要介護度では利用できるサービスが足りず、介護者の負担が明らかに大きくなっていると感じる場合も、介護認定の見直すタイミングです。
たとえば、デイサービスの利用回数を増やしたくても支給限度額に達してしまう、訪問介護の時間内では必要な介護をこなしきれないといった場合です。こうした状況が続けば、家族だけでの介護では対応しきれなくなります。
サービスが足りないと感じる背景には、ご本人の心身状態の変化が原因であることも多く、そのままにしておくと、状態の悪化や介護者の疲弊につながりかねません。介護サービスが足りていないと感じたら、早めに介護認定の見直しを検討しましょう。


介護認定を見直すために行う手続きが「区分変更申請」です。これは、認定の有効期間内であっても、本人の状態が大きく変化した場合に、要介護度や要支援度を変更するための正式な申請です。
介護認定には有効期間があり、新規認定では原則6ヶ月、更新では12〜48ヶ月の範囲で設定されます。ただし、有効期間中であっても状態の変化があれば、更新を待たずに区分変更申請を行うことができます。
区分変更申請は、以下の6ステップで進みます。
申請は、市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで行います。(※)
本人や家族のほか、ケアマネージャーや介護施設職員などによる代理申請も可能です。担当のケアマネージャーがいる方は、まず相談して、状況整理や書類作成のサポートを受けると手続きがスムーズに進みます。
※オンライン申請(マイナポータルを活用したワンストップサービス)が可能な市区町村もあります。
申請が受理されると、認定調査員が本人の生活環境(自宅、病院、施設など)を訪問し、心身状態や生活状況を確認します。
調査内容は、身体・認知・行動・生活機能など多岐にわたります。所要時間は1時間程度です。日頃の様子を家族やケアマネが伝えることで、より正確な評価につながります。
調査と並行して、市区町村から主治医に対し、本人の病状や治療内容、生活への影響について記載した意見書の作成が依頼されます。
事前に「区分変更申請を行う」ことを主治医に伝えておくと、状態変化を反映した内容にしてもらいやすくなります。
調査結果と主治医意見書の一部を基に、全国共通の基準に基づいたコンピュータ判定が実施され、必要とされる介護時間が算出されます。
一次判定の結果に加え、調査員の所見(特記事項)や主治医意見書をもとに、複数の専門家が審査会で最終的な介護度を決定します。
市区町村が審査会の結果をもとに要介護度を決定し、結果通知書と新しい介護保険被保険者証が郵送されます。通常は申請から30日程度で届きます(状況により前後あり)。
区分変更申請時には、以下の書類が必要です(市区町村により異なる場合があります)。
|
「退院してからでないと申請できない」と思われがちですが、区分変更申請は入院中でも可能です。申請から認定結果が出るまでには通常1ヶ月近くかかるため、退院後すぐに介護サービスを利用したい場合は、入院中に申請を済ませておくとスムーズです。この場合、認定調査は病院で行われます。
筆者が担当したケースでも、ひとり暮らしのご利用者様の退院後の生活を見据えて、入院中に病院と連携しながら申請を進めたことがあります。その結果、退院直後から必要なサービスを利用できました。
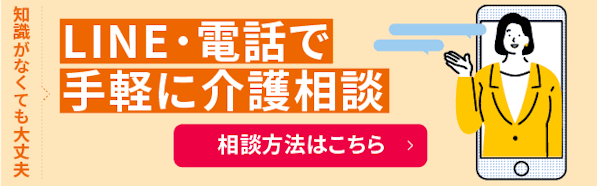

区分変更申請にあたってはいくつか注意しておくべきポイントがあります。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、次の注意点を理解しておきましょう。
区分変更申請をすれば、必ずしも要介護度が上がるわけではありません。場合によっては、現状維持や、むしろ要介護度が下がる可能性もあります。
介護認定は、認定調査員の調査結果と、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が総合的に判断します。あくまで客観的な評価に基づいて決定されるため、希望と結果が異なるケースもあることを理解しておきましょう。
要介護度が上がると、利用できるサービスが増える一方で、自己負担額も増える可能性があります。
たとえば、デイサービスや訪問介護の利用頻度が増えれば、その分の自己負担も比例して増えます。家計への影響を考慮するためにも、申請前にケアマネジャーとよく相談し、利用するサービスの内容や費用を事前にシミュレーションしておくことが大切です。

要介護認定の見直しは、ご本人に合った支援を受けるための大切な手段です。
介護度が適切に見直されることで、利用できるサービスが増え、支給限度額も引き上げられる可能性があります。その結果、ご本人の生活の安定やご家族、介護者の負担軽減にもつながります。
ただし、申請しても必ず希望どおりの認定結果が得られるとは限らず、場合によっては現状維持や自己負担額の増加も考えられます。そのため、申請前にケアマネジャーとよく相談し、状況や費用をしっかり確認することが大切です。
マイナビあなたの介護では、LINEや電話で介護に関する無料相談を受け付けています。制度や申請の進め方に不安がある方も、お気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフが丁寧にサポートしますので、一緒に最適な介護のかたちを考えましょう。
参考
介護サービス情報公表システム|厚生労働省
要介護・要支援認定の申請について(区分変更申請)|江東区
要介護認定に係る法令|厚生労働省

介護福祉系ライター/監修者
中谷 ミホ
介護福祉系ライター/監修者
中谷 ミホ
介護福祉士・社会福祉士等の資格と現場経験を活かし、介護福祉系記事の執筆・監修を手掛ける。
介護福祉士・社会福祉士等の資格と現場経験を活かし、介護福祉系記事の執筆・監修を手掛ける。

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。