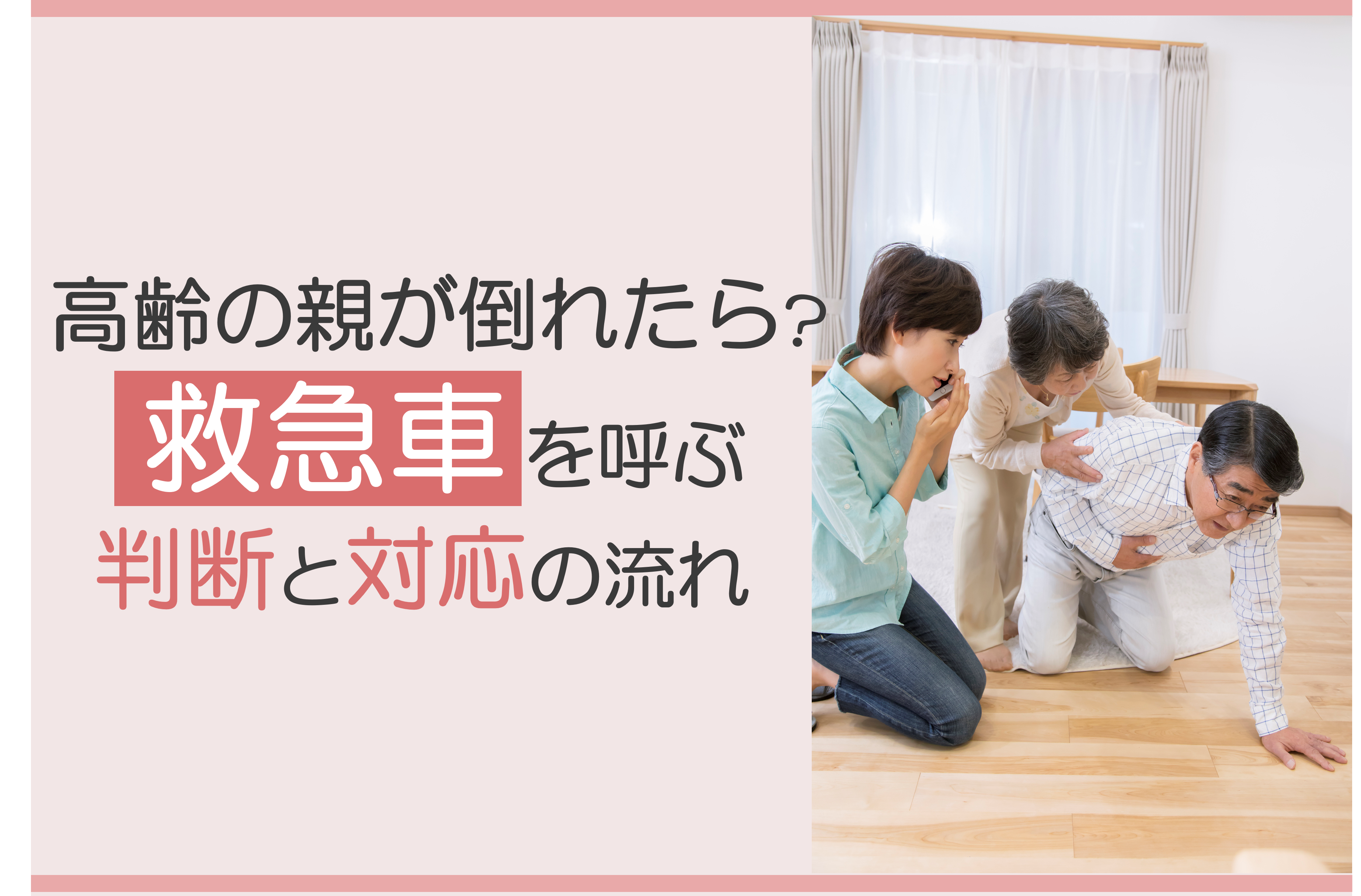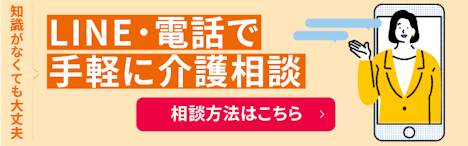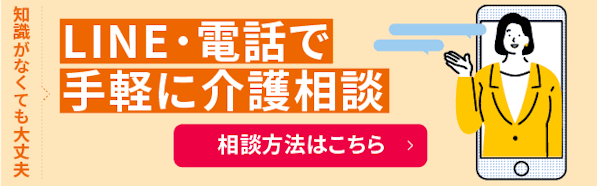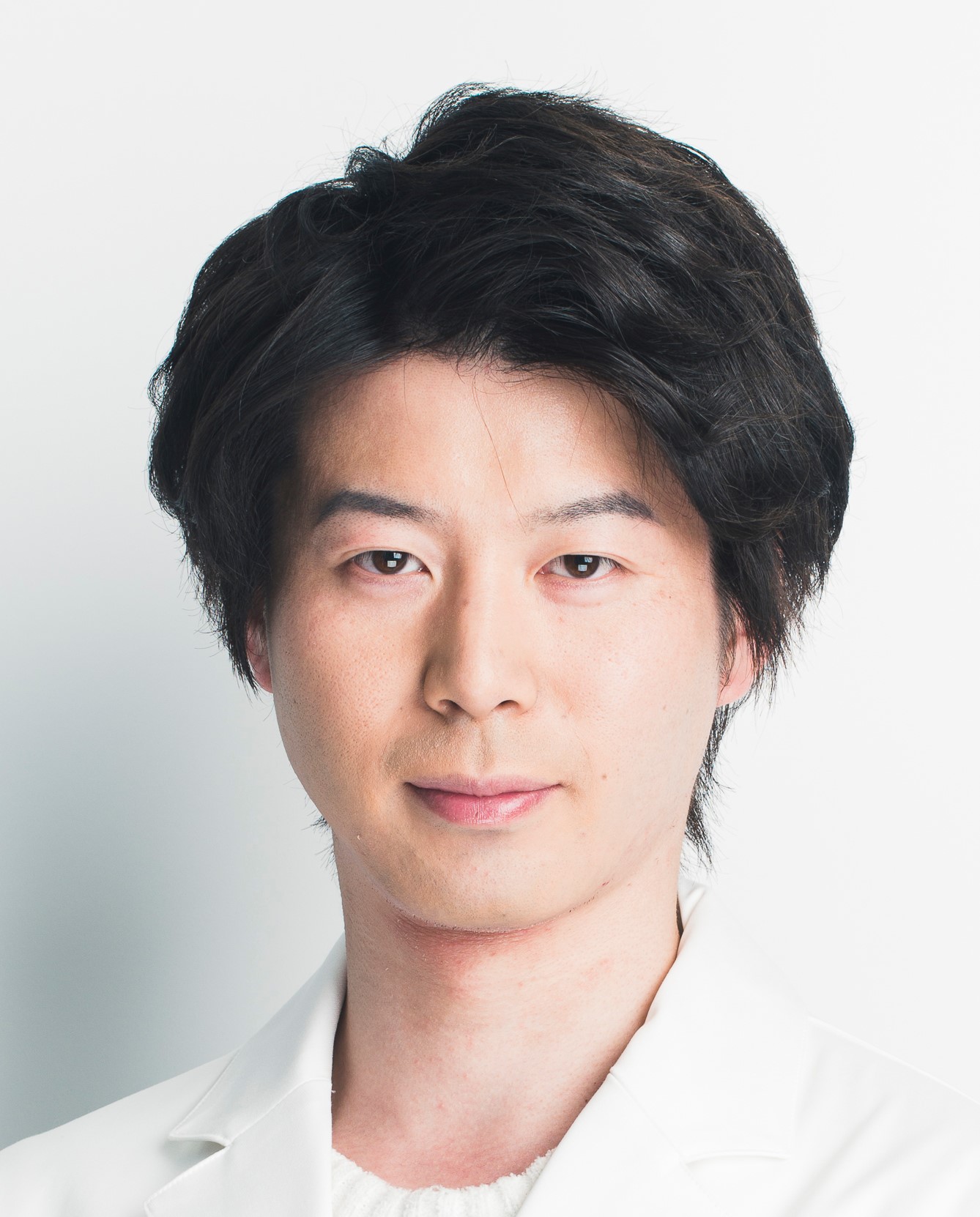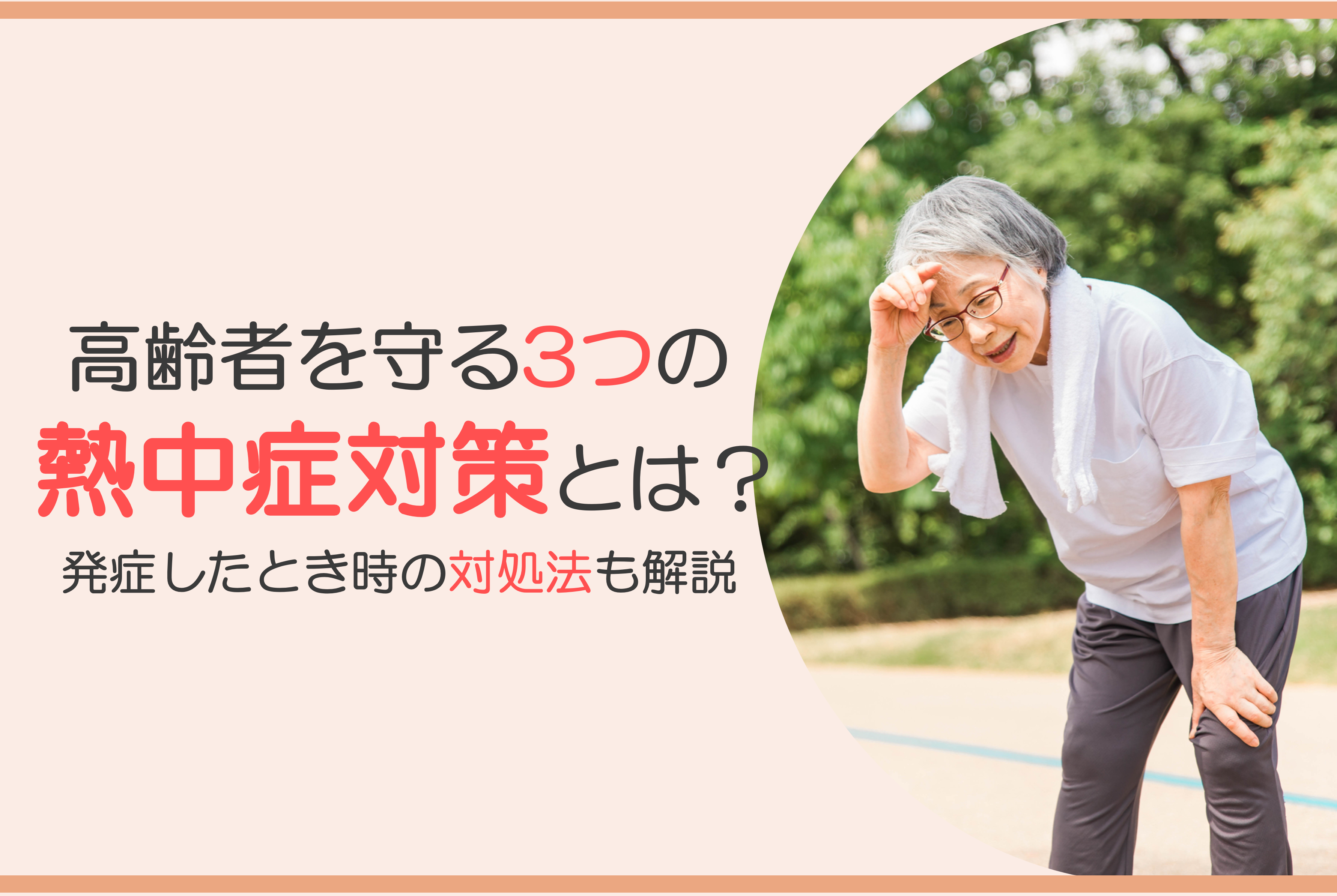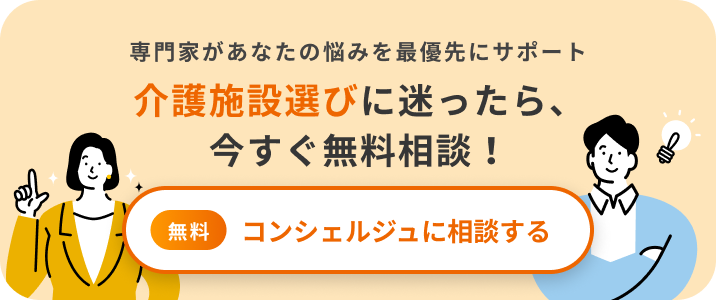Q&A
質問
最近、親の体調があまり良くなくて少し心配しています。もし急に倒れてしまったとき、どんな対応をすればいいのか、救急車を呼ぶタイミングなども含めて、事前に知っておきたいと思っています。万が一に備えて、教えてください。
回答
まずは落ち着いて状況を確認し、「反応がない・苦しそうな呼吸」などが見られたら119番へ連絡しましょう。。迷ったときはかかりつけ医や緊急安心センター事業(#7119)へ連絡し、アドバイスを受けてください。救急車以外にも、介護タクシーや民間救急サービスなどの選択肢も検討しましょう。
介護の専門家への相談はこちら ▶
ご家族様が動けなくなったときにまず確認・対応すべきこと

高齢のご家族様が倒れるなど、突然の事態に慌ててしまうのは当然です。まずは落ち着いて状況を確認しましょう。
ご家族様が動けなくなったときに確認・対応すべきこと |
|---|
- 意識や呼吸などご家族様の状態を確認しましょう
- けがの有無を確認し、身の回りの安全を確保しつつ安静にする
|
意識や呼吸などご家族様の状態を確認しましょう
まずは、ご家族様の意識や呼吸の状態を確認しましょう。
呼びかけに反応があるか、顔色や呼吸の状態をチェックする
ご家族様のそばに行き、優しく肩を叩きながら、はっきりとした声で呼びかけてください。「私の声が聞こえますか?」など、簡単な質問で意識の状態を確認しましょう。呼びかけに反応がない、または反応が鈍い場合は、危険な状態の可能性があります。
同時に、以下の点も注意深く観察してください。
- 顔色はどうか
- 唇の色が紫色になっていないか
- 呼吸の状態はどうか(速さや苦しそうかなど)
これらの情報は、救急隊や医療機関に状況を伝える際に重要です。
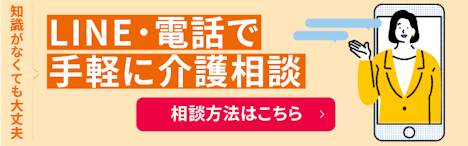
けがの有無を確認し、身の周りの安全を確保しつつ安静にする
まずは痛みの有無や転倒の可能性を確認しましょう。次に、患者さんのケガをした際の状況を把握しながら、身の回りの安全を確保しましょう(物がさらに倒れないようにするなど)。そして安静を保てる場所に移動できるようなら移動することが大切です(例えば、広く横になれる平らな場所など)。
転倒や痛みがないか確認し、安全な姿勢を保つ
転倒した様子がある場合や、ご家族様が痛みを訴えている場合は、骨折などのけがをしている可能性があります。どの部位に痛みがあるか、腫れや変形がないかなどを、身体を大きく動かさない範囲で確認しましょう。
特に高齢者は転倒でも骨折しやすいため、注意が必要です。意識があり、呼吸も安定しているようでも、強い痛みがある場合は無理に体位を変えたり、立たせようとしたりしないでください。
楽な姿勢で安静にできるよう、クッションなどで支え、必要であれば毛布などをかけて保温しましょう。安全な場所で安静を保つことが原則です。また、頭部を打っている場合は、気分が悪くなり吐いてしまう可能性があります。首を動かさないようにして、気道を確保しましょう。
救急車を呼ぶべきケースと緊急度の判断基準

ご家族様の状況を確認したら、次に救急車(119番)を呼ぶべきかどうかを判断しましょう。
以下の症状が見られる場合は、ためらわずに119番へ通報してください。命に関わる可能性が高い、あるいは緊急の処置が必要なサインです。
すぐに119番通報すべき緊急の症状・状況 |
|---|
- 意識がない、または呼吸・脈が停止している
- 呼吸が苦しい、胸に激しい痛みが見られる
- 手足のまひや言葉の不明瞭さが見られる
- 突然の激しい頭痛や高熱が見られる
- 骨折の疑いがあり、激しい痛みで動かせない
|
①意識がない、または呼吸や脈が停止している場合
まず、肩を軽く叩きながら「大丈夫ですか?」などと大きな声で呼びかけてください。呼びかけに全く反応がない場合は、直ちに周囲のひとの助けを呼び119番やAEDのお願いをしましょう。その後呼吸と脈の有無を確認し、その結果に応じて行動しましょう。
呼吸と脈の確認は、10秒ほどかけて胸やお腹の動きを観察し、普段通りの呼吸をしているかどうかを見ます。脈の確認は喉ぼとけの横のくぼみに人差し指と中指の2本を当てて軽く押し脈拍を探します。もし、呼吸をしていない、またはしゃくりあげるような異常な呼吸の場合、脈が確認できないは、心臓マッサージ(胸骨圧迫)を開始してください。脈が触れているかわからない・自信がない場合もすぐに心臓マッサージを開始してください。
心臓マッサージは「強く、速く、絶え間なく」(目安:1分間に100〜120回、胸が約5cm沈む強さ)を意識し、救急隊が到着するまで続けましょう。
近くにAED(自動体外式除細動器)があれば、迷わず電源を入れ、音声ガイドに従って使用します。
このように「意識がない」「普段通りの呼吸・脈がない」状態は、命に関わる緊急性の高い状態です。ためらわず、迅速な対応を心がけましょう。
【参考】政府広報オンライン「応急手当の知識と技術 いざというときに備えて身につけておきましょう」、東京消防庁「命を救う~心肺蘇生法~」
②呼吸が苦しい、胸に激しい痛みが見られる場合
以下のような症状がある場合は、心臓や肺に重大なトラブルが起きている可能性があります。
- 息がうまく吸えない、息苦しい
- ゼーゼー・ヒューヒューという異常な呼吸音がする
- 胸を締めつけられるような激しい痛みがある
- 顔や唇の色が紫や暗い色になってしまっている
|
これらは、心筋梗塞などの心疾患のサインかもしれません。特に「胸が締めつけられる」「冷や汗をかく」「顔が青白くなる」といった様子が見られた場合は、すぐに救急車を呼んでください。
また、同じような症状が「肺塞栓症(はいそくせんしょう:血の塊が肺につまる病気)」や気道に異物が詰まるなど呼吸系の障害で起きることもあります。
いずれの場合も、命に関わる緊急性の高い状態です。ためらわずに119番通報し、速やかに医療機関で適切な処置を受けましょう。
③手足のまひや言葉の不明瞭さが見られる場合
以下のような症状が突然現れた場合は、脳卒中(脳梗塞や脳出血など)の可能性があります。発症からの時間が治療効果に影響するため、一刻も早い対応が必要です。
このような症状がひとつでも見られたら、ためらわずに119番通報してください。
- 片方の手や足に力が入らない、動かせない
- 手足がしびれる、感覚が鈍い
- ろれつが回らない、言葉が出にくい
- 相手の言っていることが理解できない
- 顔の片側がゆがんでいる(表情が左右非対称)
|
④突然の激しい頭痛や高熱が見られる場合
これまでに経験したことのないような激しい頭痛や、急な高熱に加えてぐったりしている、意識がもうろうとしているといった状態は、くも膜下出血などの可能性があります。
速やかに119番通報し、医療機関での緊急対応が必要です。
⑤骨折の疑いがあり、激しい痛みで動かせない場合
転倒などの後、強い痛みで全く動けない、または手足に明らかな変形が見られる場合は、骨折が疑われます。
特に大腿骨(太ももの骨)の骨折は、高齢者の寝たきりの原因にもなりやすいため、できるだけ早い医療処置が必要です。
無理に動かすと悪化してしまう可能性がありますが、けがや事故の状況をしっかり把握して身の安全は確保するようにしてください。119番に通報して救急搬送を依頼しましょう。
【参考】消防庁「救急車を上手に使いましょう」

緊急でない場合の相談先と対処法

上記のような明らかな緊急性の高い症状はないものの、「動けない」「いつもと違う」状態で判断に迷う場合や、緊急性は低いが移動手段がない場合は、以下の対処法があります。
【緊急でない場合の相談先と対処法】 |
|---|
- 救急安心センター事業(♯7119)に相談して指示を仰ぐ
- 日中であれば、かかりつけ医に連絡し指示を受ける
- 介護タクシー・民間救急サービスを利用して病院へ行く
|
①救急安心センター事業(♯7119)に相談して指示を仰ぐ
「救急車を呼ぶべきか迷う」「受診できる病院を知りたい」といった場合に、医師や看護師などの専門家が電話でアドバイスしてくれるのが、救急安心センター事業(#7119)です。
判断に迷ったら、まず#7119に電話してみましょう。なお、このサービスは、一部の地域でのみ実施されているため、お住まいの自治体で利用できるか事前に確認しておくことをおすすめします。
【参考】総務省 消防庁「救急車の適時・適切な利用」
②日中であれば、かかりつけ医に連絡し指示を受ける
日中であれば、かかりつけ医に電話で相談し、受診や療養の指示を受けましょう。
主治医は、ご家族様の病状を把握しているため、的確なアドバイスをもらえる可能性が高いです。
③介護タクシー・民間救急サービスを利用して病院へ行く
緊急性は低いものの、自力での移動が困難で病院を受診したい場合、これらのサービスが利用できます。いずれも、費用は原則自己負担です。
サービス名 | 詳細 |
|---|
介護タクシー | 車椅子やストレッチャーのまま乗車でき、乗降の介助も依頼できます。通院や入退院時によく利用されている人がいます。 |
民間救急サービス | 寝たきりの方や医療機器(酸素など)が必要な方の搬送、長距離搬送にも対応しています。 |
※サービスの提供体制や事業者の数は地域によって差があるため、事前に対応エリアや予約状況を確認されることをおすすめします。
【参考】東京防災救急協会「東京民間救急コールセンターに関するお知らせ」、西日本PAM株式会社「日本民間救急総合受付センター」
要介護者が動けなくなってしまったときのよくある状況

実際にどのような状況で救急車やその他のサービスが利用されているのか、4つの事例を見てみましょう。
事例1:自宅で転倒し痛みで動けず、救急搬送した
80代の女性で、パーキンソン病を患っている方の事例です。
ある日、ご自宅の部屋の中を歩いていた際にバランスを崩し、尻もちをついてしまいます。当初はそれほど強い痛みはなかったものの、数時間後から徐々に痛みが強くなり、自力で歩けない状態になりました。
とても自家用車で移動できる状況ではなかったため、同居のご家族が119番通報し、救急車で病院へ搬送されることになりました。診察の結果、腰椎および胸椎の圧迫骨折と診断され、そのまま緊急入院となったのです。
転倒直後に強い痛みがなかったとしても、高齢者の場合、圧迫骨折などは時間が経ってから症状が悪化することがあります。
特にパーキンソン病などの持病がある方は、転倒リスクが高まっているため、転倒しやすい場所に注意をしましょう。
事例2:朝起きたら半身がまひして動けない(脳卒中の疑いで119番)
70代の女性で、ご家族と暮らしている方の事例です。
ある朝、普段どおり起床する時間になっても部屋から出てこなかったため、ご家族が様子を見に行きました。すると、ご本人様はベッドに横になったまま、「身体が動かない」と訴えられ、ろれつも回っていない状態でした。
明らかに普段と様子が異なるため、ご家族はすぐに119番通報をされます。救急搬送された病院で脳梗塞と診断され、そのまま緊急入院となりました。発見から通報・搬送されたことにより、症状の進行を最小限に抑えられました。
ろれつが回らない、半身がまひしているといった症状は、脳卒中の代表的な初期サインであり、場合によっては時間との勝負となります。
このようなときに「もう少し様子を見よう」とせず、すぐに救急車を呼んだ方がよいです。
事例3:徐々に足腰が弱り自力で動けず、介護タクシーで通院した
90代の女性で、徐々に足腰が弱くなっていた方の事例です。
これまでは、月に一度ほど、ご家族が運転する車で近隣のかかりつけ医に通院していました。しかしある日、体調は普段と変わりなく元気でしたが、ご家族が介助しても車に乗り込めなくなってしまいます。ご本人様の足が上がりにくくなっていたのです。
ご家族は「このままでは通院できない」「でも救急車を呼ぶほどではない」と判断に迷い、ケアマネージャーへ電話で相談しました。そして、介護タクシーという選択肢があることを教えてもらいました。早速、手配を行い介護タクシーのスタッフによる介助を受けながら、無事に通院できたのです。
事例4:夜間に動けなくなったが意識はあり、訪問看護の緊急対応サービスに相談した
80代の男性で、高齢の奥様と二人暮らしをされている方の事例です。
普段から車椅子を使用しており、この日は夜中にトイレへ行こうとした際、車椅子からうまく乗り移れず、床にずり落ちてしまいました。一度、床に座り込んでしまうと、高齢の妻も持ち上げられず、身動きが取れない状態になってしまうのです。
そんな時、妻は、普段から利用している訪問看護ステーションへ緊急訪問を要請します。夜間でしたが、看護師が駆けつけ、ご本人様を無事にベッドへ誘導してくれました。その際には、バイタルサインの確認や転倒によるけが・打撲のチェックも行い、大きな異常は認められませんでした。
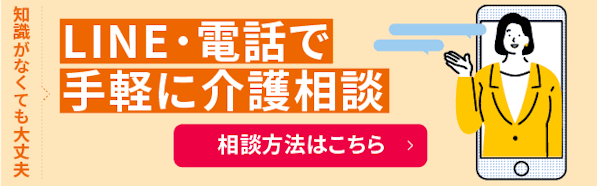
まとめ:高齢のご家族様が突然動けなくなったとき、慌てず対応するためにできること

この記事では、高齢のご家族様が突然動けなくなった際の対応について、判断のポイントや相談先、そして事例を交えて解説しました。
万が一のときに慌てず対応するために、あらかじめ以下のポイントを確認しておきましょう。
この記事のポイントは、以下のとおりです。
- 意識・呼吸・けがの有無を確認:まずは落ち着いて状態を観察し「反応がない・苦しそうな呼吸」などが見られたら119番へ連絡しましょう
- 救急車を呼ぶべき症状を知る:意識障害・胸の痛み・まひ・激しい頭痛などは緊急対応が必要になります
- 迷ったときは相談機関へ:かかりつけ医や救急安心センター事業(♯7119)に連絡し、アドバイスを受けましょう
- 移動手段を知る:介護タクシーや民間救急サービスなど、救急車以外の選択肢も検討しましょう
|
突然の出来事に直面すると、誰でも不安になるものです。だからこそ、いざというときに何をすればいいかを事前に知っておくことが、ご家族様や同居されているご家族の安心につながります。
「マイナビあなたの介護」では、介護や医療の現場をよく知る専門家が、介護全般のお悩みに無料でアドバイスや情報提供を行っています。
電話やLINEでのご相談も可能で「こんなとき、どうすればいい?」「今後、在宅でやっていけるのかな…」など、どんなお悩みも大歓迎です。
ひとりで抱え込まず、まずは気軽に相談してみませんか?経験豊かな専門家と一緒に、解決できる方法を見つけましょう。
監修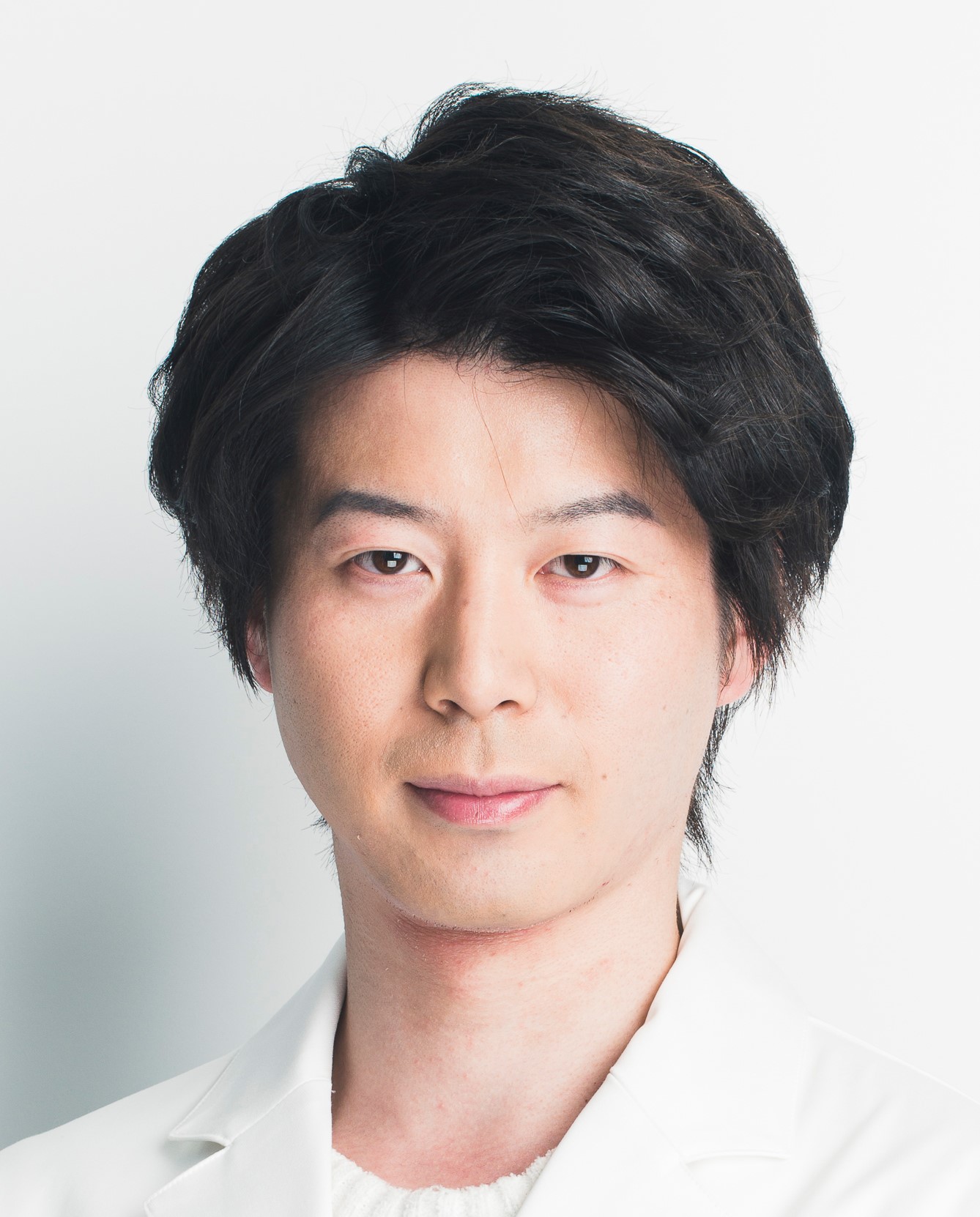
UT Austin, Faculty of Education and Kinesiology, Cardiovascular aging research lab, Visiting Scholar
眞鍋 憲正(まなべ かずまさ)
UT Austin, Faculty of Education and Kinesiology, Cardiovascular aging research lab, Visiting Scholar
眞鍋 憲正(まなべ かずまさ)
医師、医学博士。スポーツ医学を専門とし研究・臨床を行う。2021年よりアメリカの大学にて研究に従事。
医師、医学博士。スポーツ医学を専門とし研究・臨床を行う。2021年よりアメリカの大学にて研究に従事。