親を介護しているなかで、親の状態、あるいは介護者の状況によって、親を施設に入れる必要性が生じることがあります。しかし、親を施設に入れることに抵抗を感じる人も多くいるのも事実です。
そこでこの記事では、施設入所のメリット、親を施設に入れることの罪悪感と向き合うための方法、筆者が経験した実際の事例などを紹介していきます。
介護コンシェルジュに相談する受付時間 月~金:9:00~19:00 / 土:9:00~18:00
記事をシェアする
親を介護しているなかで、親の状態、あるいは介護者の状況によって、親を施設に入れる必要性が生じることがあります。しかし、親を施設に入れることに抵抗を感じる人も多くいるのも事実です。
そこでこの記事では、施設入所のメリット、親を施設に入れることの罪悪感と向き合うための方法、筆者が経験した実際の事例などを紹介していきます。
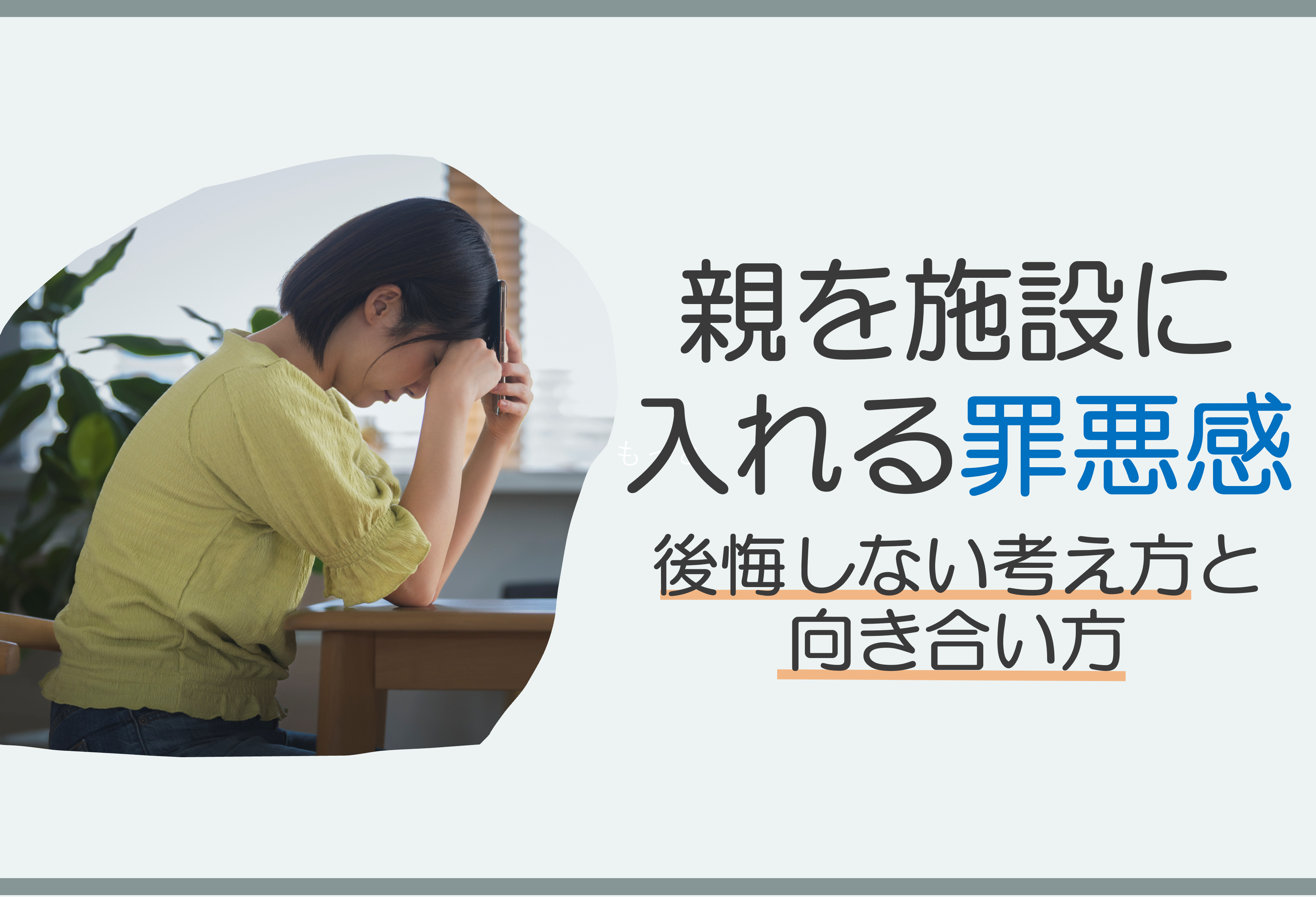



親を施設に預けることに罪悪感を持つ方の多くが、「自分が世話をしないのは親不孝ではないか」「見捨てたと思われないか」と考えてしまいます。
しかし実際には、施設は家では難しい医療的ケアや専門的なケアを提供できる場所であり、在宅介護では対応が困難になったときこそ、施設の力を借りるべきタイミングです。
認知症の進行や身体機能の低下、日常的な医療的ケア対応が必要になった場合、在宅介護を続けるのは現実的に困難といえます。そうした中で、介護者が無理を重ねて体調を崩してしまっては、かえって親にも良い影響は与えられません。
介護のプロを頼ることは、親を見捨てるのではなく、「より良い支援体制にバトンタッチする」という前向きな選択なのです。
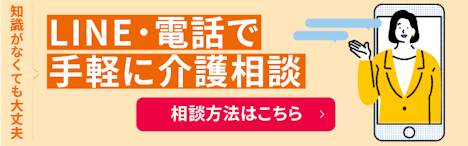

施設には、看護師や介護職員が常駐しているため、万が一の体調変化にもすぐに対応できる体制が整っています。
また、リハビリやレクリエーション、季節の行事などが用意されているため、生活にリズムが生まれ、楽しみも増すでしょう。認知機能が低下したり、体が思うように動かせなくなったりすると、引きこもりがちになる高齢者も少なくありません。
しかし、施設に入所すると人と接する機会が増えるため、適度な刺激につながる効果が期待できます。同年代との交流ができることも、精神的な安定につながります。
家族にとっても、食事の準備や入浴、夜間の見守りといった日常的な介護の負担から解放されることで、心身にゆとりが生まれます。その結果、仕事や育児との両立がしやすくなり、経済面や生活全体の安定にもつながっていくでしょう。
また、介護によるストレスが軽減されることで、親との関係がより穏やかに変化するケースも少なくありません。お互いに無理のない距離感を保ちながら関わることができるようになると、家族全員が気持ちの面でも落ち着いた時間を過ごせるようになります。
施設入所が決まった後も、家族としてできることはたくさんあります。定期的な面会はもちろん、親の好きな食べ物を差し入れるなど、家族が顔を見せることが親にとって大きな支えになるでしょう。
また、施設のスタッフとの良好な関係を築くことも重要です。親の性格や好み、生活習慣などを積極的に伝え、より良いケアにつなげてもらいましょう。家族が施設と連携することで、親はより安心して生活を送ることができます。

介護を頑張りすぎていると、自分では気づかないうちに疲労が蓄積していることがあります。不眠やイライラ、食欲の低下などが見られる場合、それは明らかな疲労のサインです。
「まだ大丈夫」と無理するのではなく、「今が限界なのかもしれない」と冷静に自分自身の状態を見つめることも大切です。
介護に関する悩みや不安は、ひとりで抱え込まないことが何より大切です。地域包括支援センターやケアマネジャーは、中立的な立場から状況を整理し、的確なアドバイスをしてくれる心強い存在です。
また、かかりつけの医師やソーシャルワーカーなど、医療・福祉の専門職からの客観的な意見を聞くことで、感情に偏らない冷静な判断がしやすくなります。
親の施設入所は、ご本人だけでなく家族全体に関わる大きな節目となる出来事です。ひとりで抱えず、きょうだいや配偶者などと率直に気持ちを共有することで、「自分だけが責任を背負っている」と感じるプレッシャーから解放されることも多いです。
いきなりの施設入所に抵抗を感じる方は、まずは「ショートステイ(短期入所生活介護 等)」を利用してみるのも一つの方法です。
数日〜数週間の短期間だけ施設に滞在し、雰囲気やサービス内容を体験してみましょう。段階的に環境に慣れていくことで、不安も和らぎ、本格的な入所入居に対する心理的なハードルも下がっていきます。
施設を選ぶときは、インターネットやパンフレットの情報だけに頼るのではなく、必ず実際に見学して、雰囲気を確認することをおすすめします。
職員の対応の丁寧さや入居者の様子、施設内の清潔感、居室やトイレの使いやすさなど、細かい点を自分の目で見ることで「ここなら安心できそう」と感じられる施設に出会える可能性が高まります。

ここでは、筆者が実際に経験した「親の施設入所に対して罪悪感を抱きながらも、最終的に前向きな決断に至ったご家族の事例」をご紹介します。
50代の長女が、パーキンソン病と診断されたお父さま(85歳・要介護4)を自宅で介護されていました。
訪問介護やデイサービス、ショートステイなどを組み合わせながら、長年にわたり懸命に支えてこられましたが、次第に誤嚥性肺炎を繰り返すようになり、1日に何度もたんの吸引が必要な状況になりました。
それでも「まだ頑張れる」と自分を奮い立たせながら介護を続けていましたが、やがて十分な睡眠や休息が取れなくなり、体調を崩してしまいました。
そこで、これまでショートステイで利用していた介護施設への入所を決断することになりました。
入居後、お父さまは必要な医療的サポートを安定して受けられるようになり、娘さんも「ようやく安心できた」とおっしゃっていました。
以前よりも表情が和らぎ、「できるだけのことはやったと思えるから、今は後悔していません」という言葉がとても印象に残っています。
このケースは、施設入所という選択が親を見捨てることではなく、家族が無理なく、そして健やかに関わり続けるための前向きな手段であることを、あらためて実感させられるものでした。

親を施設に入れるときに罪悪感を抱くのは、誰にでもある自然な感情です。しかし、その感情だけに左右されてしまっては、親にも自分にも無理をさせ続けることになりかねません。
大切なのは、「親を見捨てる」のではなく「支え方を変える」という発想に切り替えることです。
介護は、親の心身の状態や家族の状況、そしてそのときどきの環境によって変わります。だからこそ、感情に流されるのではなく、冷静な判断を心がけることが重要です。
親と家族の双方が安心して穏やかに暮らすためにも、柔軟で前向きな選択をしていきましょう。
介護にまつわる悩み事は、「マイナビあなたの介護」でも気軽に相談することができます。
施設探し、介護準備のサポート、資料請求・見学申込の代行など、幅広く支援を行っていますので、ぜひお試しください。LINEや電話などから、いつでもアドバイスを受けることができます。

介護福祉系ライター/監修者
中谷 ミホ
介護福祉系ライター/監修者
中谷 ミホ
介護福祉士・社会福祉士等の資格と現場経験を活かし、介護福祉系記事の執筆・監修を手掛ける。
介護福祉士・社会福祉士等の資格と現場経験を活かし、介護福祉系記事の執筆・監修を手掛ける。

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。