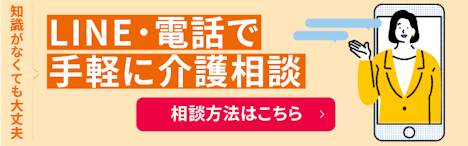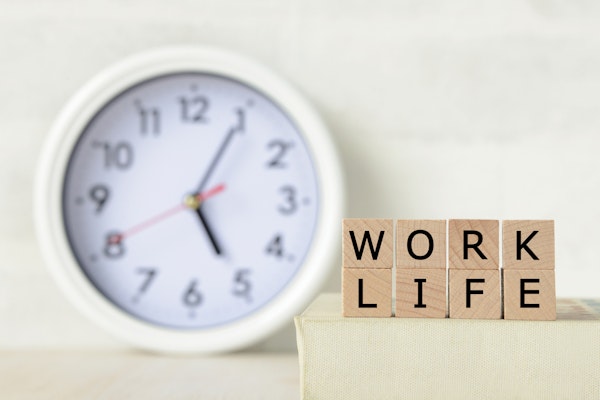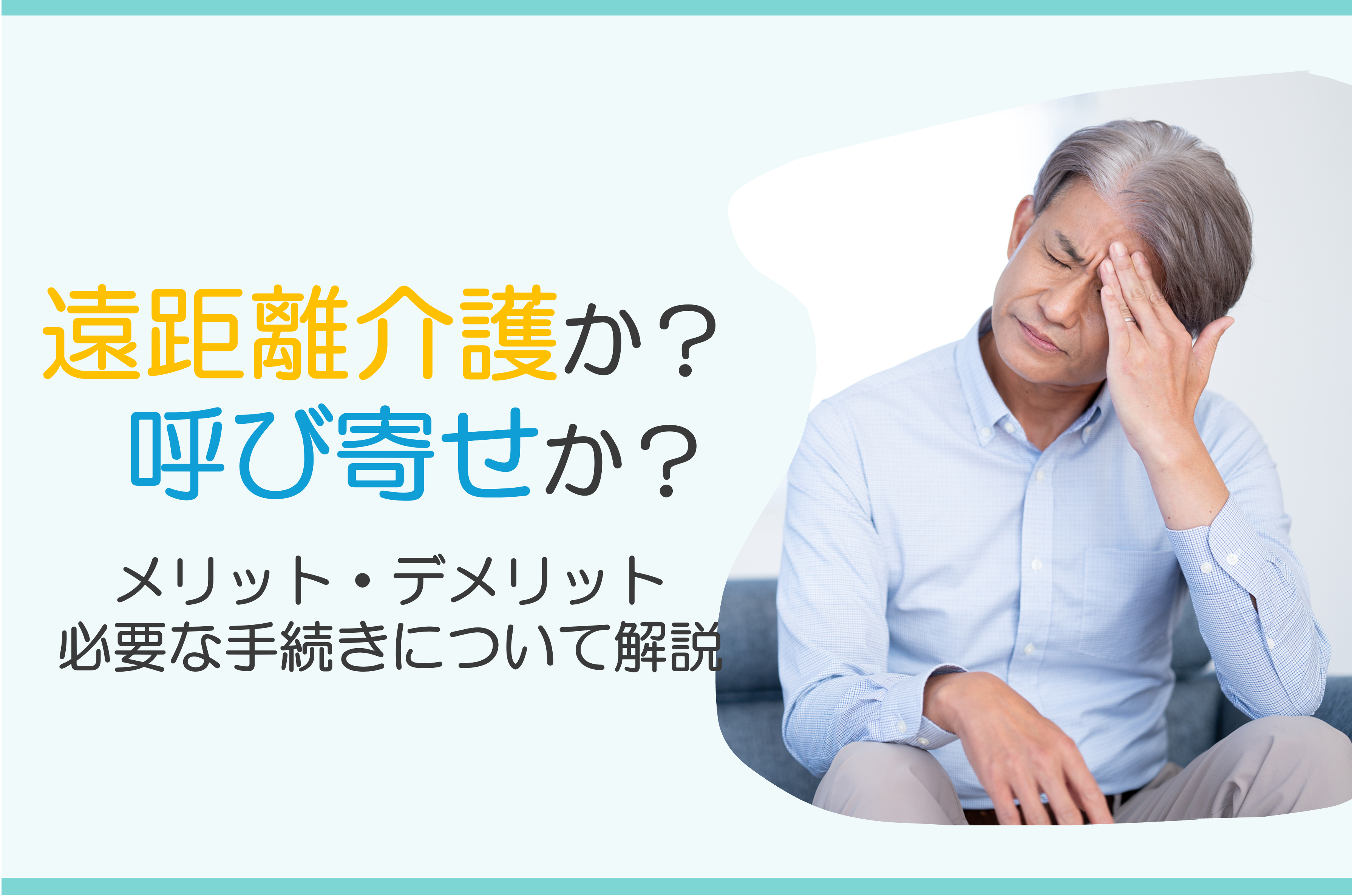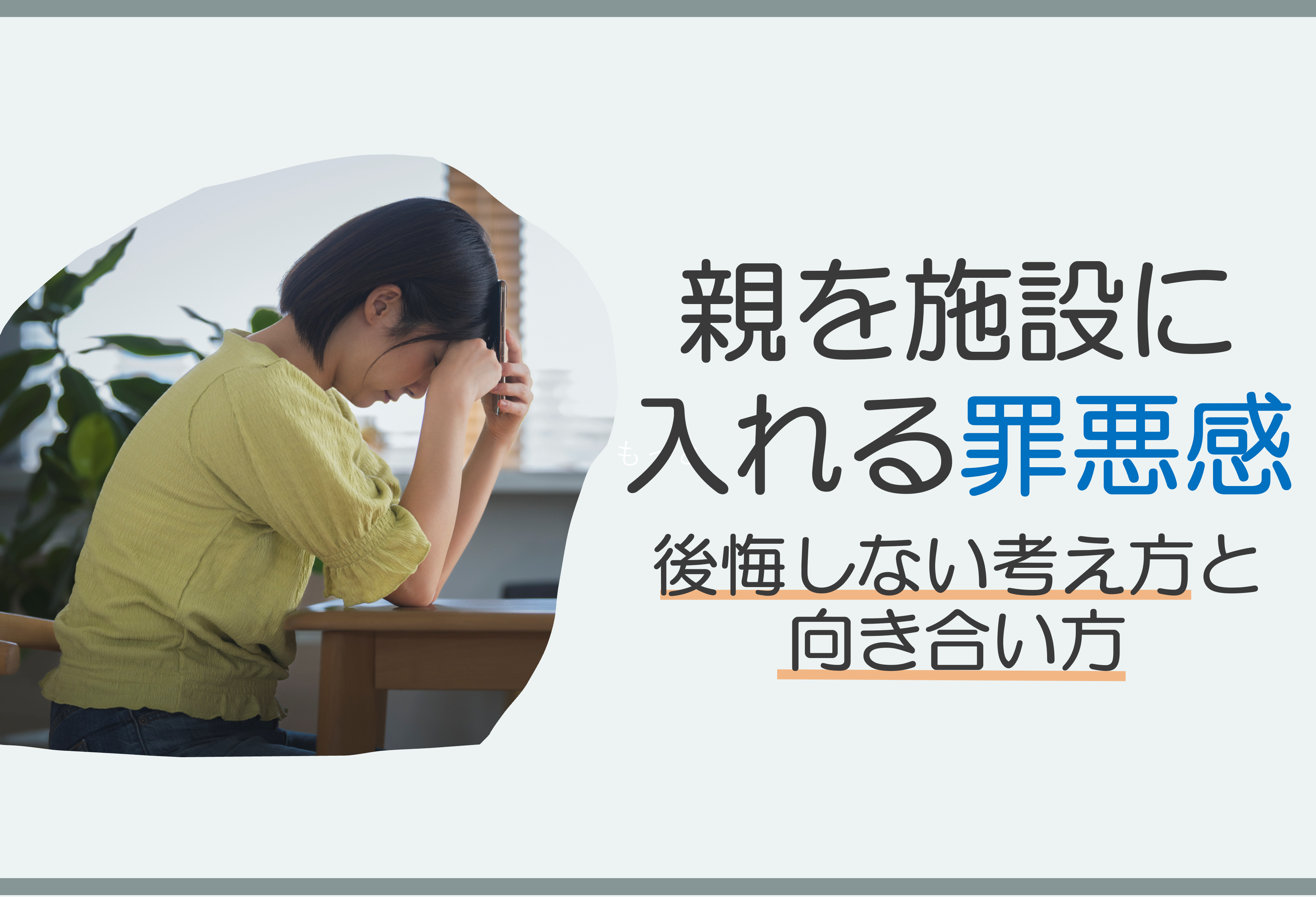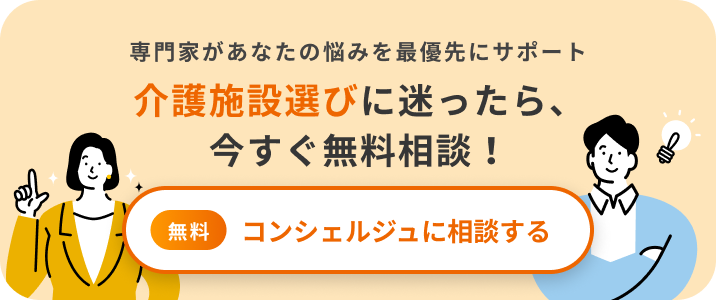Q&A
質問
親の介護が必要になりそうで不安です。一人っ子の私は何から始めればいいでしょうか?
回答
ご家族様の介護が必要になってくる段階では「何から手をつけていいのか」「誰に相談すればいいのか」と不安になるお気持ち、よく分かります。まず大切なのは「ひとりで抱え込まないこと」です。情報を集め、相談できる相手を見つけることから始めましょう。
具体的には、近くの地域包括支援センターに相談し、介護保険やサービス利用の情報を得ること、そして必要に応じて、介護認定の申請を検討することです。ご親族様と今後について話し合い、協力をお願いすることも重要です。
介護の専門家への相談はこちら ▶
一人っ子がご家族様の介護に直面するときの不安と大変さ

ご家族様の介護に対して「全部、自分でやらなければならない」という不安や責任感を抱く方は少なくありません。ここでは、介護の悩みや、介護が始まる前に感じやすい心配事について解説いたします。
一人っ子ならではの介護の課題は?
一人っ子の方が介護をする際の課題は「全ての責任が自分に集中してしまう」ことです。精神的・肉体的・経済的な負担がひとりに集中し、プレッシャーも大きくなります。
身近に相談できる人がいないため孤独感が深まり「自分だけが頑張っている」と感じてしまい、心身のバランスを崩すことも少なくありません。だからこそ「ひとりで抱え込まない意識」が重要なのです。
介護開始前に感じやすい具体的な不安例
介護が必要になる前には、多くの不安を抱えてしまうものです。一人っ子の方が抱えやすい不安は、大きく3つに分けられます。
① 経済的な不安
- どれくらいお金がかかるのか
- 施設に入るとしたら、どのくらい必要なのか
介護には予想以上に費用がかかることもあります。制度の活用や費用については、後の章で解説いたします。
② 介護力の不安
- 認知症になったら、自分に対応できるのだろうか
- 離れて暮らしており、身近でお願いできる人がいない
身近な相談先や支援の受け方を理解しておきましょう。いざというときに相談先があると、安心です。
③ プライベートや仕事との両立への不安
- 仕事を辞めないといけないのでは…
- 介護と仕事を両立する自信がない
仕事と介護の両立を目指すには、職場制度の活用や周囲との連携が重要です。
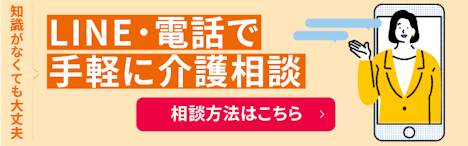
まず最初に取るべきアクションとは?

介護が始まる前に、どのような準備をしておくかが大切です。ここでは、一人っ子の方が、ご家族様の介護に備えるために「最初に取るべき4つのアクション」について解説いたします。
まず最初に取るべき4つのアクション |
|---|
- 地域包括支援センター等への相談
- 介護保険の確認・要介護認定の申請
- 家族・親族との話し合い
- 「ひとりで抱え込まない」マインドを持つ
|
地域包括支援センター等への相談
介護にどう向き合えば良いか迷ったとき、最初の相談先は「地域包括支援センター」です。お住まいの地域に設置されている無料の相談窓口で、介護・福祉・医療の幅広い相談に対応しています。
「まだ介護は始まっていないけど不安」という段階でも問題ありません。現状を話すことで、情報提供や専門機関への紹介など、適切なサポートにつなげてくれます。
介護保険の確認・要介護認定の申請
まずは、ご家族様が介護保険の被保険者(65歳以上、または40歳〜64歳で特定疾病をお持ちの方)であるか確認してください。介護が必要と感じたら、市区町村窓口や地域包括支援センターを通じて要介護認定の申請を行いましょう。
認定結果に応じて、利用できるサービスや限度額が決まります。申請手続きも、地域包括支援センターがサポートしてくれます。
家族・親戚との話し合い
叔父や叔母、いとこなどの親戚がいれば、現在の状況を共有し今後について話し合っておきましょう。
直接協力を得られなくても、精神的に支えてくれたり、悩みを聞いてくれたりするかもしれません。また、ご家族様本人の意向(どんな介護を受けたいか、どこで過ごしたいかなど)を、元気なうちに少しずつ聞いておくことも重要です。
◆関連記事:親の介護を「私ばかり」と悩む方へ…家族と上手に分担するコツ
「ひとりで介護を抱え込まない」マインドを持つ
一人っ子の方は責任感が強く「自分が頑張らないと」と思い詰めてしまいがちです。しかし、介護は、ひとりで背負うものではありません。
制度や介護サービスを活用し、頼れる人には頼る意識を持つことが大切です。最初から完璧を目指さず、必要なときに助けを求めることを大切にしましょう。
一人っ子が親の介護を両立させる方法~生活・仕事・プライベートの時間
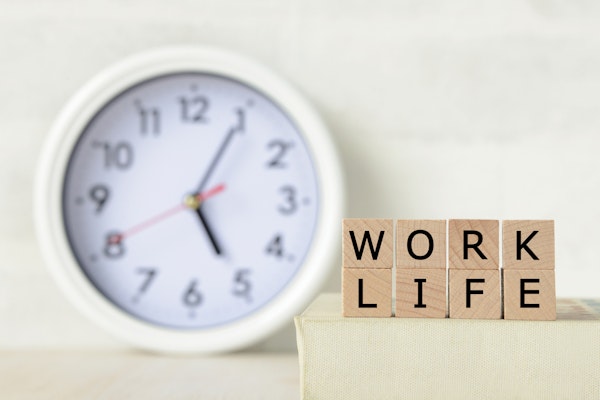
介護が始まると「自分の時間がなくなるのでは」「仕事に支障が出るのでは」と不安になる方も少なくありません。しかし、必要な支援を取り入れたり、元気を保つ工夫をしながら介護と向き合うことも可能です。ここでは、介護と日常生活を両立させるための視点や工夫をご紹介いたします。
自分の生活・仕事と介護の両立ポイント
介護と生活・仕事を両立させるためには、「制度を利用する」「介護サービスを取り入れる」「周囲の理解を得る」という3つの視点をバランスよく取り入れることが大切です。
まず、勤務先の介護休業や時間短縮勤務制度を確認し、上司や人事担当に相談してみましょう。また、デイサービスやショートステイを組み合わせることで、日中の時間を確保しやすくなります。
職場や親しい人に現状を伝えることで、理解や協力が得られ、落ち着いて仕事ができます。「全てを完璧にこなす」ことを目指すのではなく、優先順位をつけて「できることを無理なく続ける」ことを心がけましょう。
心が疲れ切ってしまう前にできること、元気を保つ工夫
介護が続くと、心も体も気づかないうちに疲れてしまいがちです。「自分のための時間を持つ」ことを意識しましょう。短時間でも、リラックスできる時間をつくることが大切です。
十分な休息も必要です。ショートステイを活用して、まとまった休みを取ることも検討しましょう。「つらい」「しんどい」と感じたら、その気持ちを隠さず、信頼できる人に話したり、日記に書き出して気持ちを整理したりすると楽になります。
また、同じような立場の介護者とつながる場を持つと、気持ちを軽くできるかもしれません。家族会やSNSなども活用してみましょう。
介護の負担を軽減するために活用できる介護サービスと制度

介護をひとりで抱え込むと、心身共に疲弊してしまいます。負担を軽減するために、介護サービスを上手に活用しましょう。ここでは、主なサービスや制度の特徴と選び方を紹介いたします。
介護の負担を軽減するために活用できる介護サービスと制度 |
|---|
- 活用できる介護サービスと選ぶときのポイント
- 地域包括支援センターや市区町村窓口、相談窓口の使い方
- 介護保険・医療制度・医療費・医療費控除の具体的な活用法
|
活用できる介護サービスと選ぶときのポイント
介護保険で利用できるサービスには、訪問介護やデイサービス、ショートステイなど、さまざまなサポート体制があります。大切なのは、ご家族様の状態やご家庭の事情に応じて「必要な支援を受けること」です。
まずはケアマネージャーと「どんな支援が必要か」「どの時間帯が手薄になりそうか」などを話し合いながら、必要なサービスを組み合わせていきましょう。ひとりで頑張りすぎず、サービスの力を借りることが大切です。
地域包括支援センターや市区町村窓口、相談窓口の使い方
「誰に相談すればいいのか分からない」という場合は、まず地域包括支援センターや市区町村の高齢福祉課などを訪ねましょう。
介護保険制度やサービスについての説明など、幅広く相談できます。介護認定の申請代行や、ケアマネージャーの紹介も行ってくれるため、困ったときの相談先として活用しましょう。
介護保険・医療制度・医療費・医療費控除の具体的な活用法
介護保険を使えば、訪問介護やデイサービスなどを自己負担1〜3割で利用できます。ケアマネージャーと相談しながら、限度額の範囲内で複数のサービスを組み合わせていくのが基本です。
また、高額療養費制度や高額介護合算療養費制度を利用すれば、医療費や介護費の自己負担を軽減できます。医療費控除の対象になる場合もあるため、確定申告用に領収書を保管しておきましょう。
介護にかかる費用・経済的負担~介護費用が高額で経済的に厳しいときの対策

介護は長期間にわたることが多く、経済的な負担は決して少なくありません。一人っ子の場合、負担が自分に集中しやすいため、早めに費用の目安や支援制度を把握しておくことが大切です。ここでは、主な費用と公的支援制度を紹介します。
介護にかかる費用・経済的負担に関する主なポイント |
|---|
- 老人ホーム・介護施設の費用相場・施設選びの注意点
- 施設入居(介護施設・ショートステイ)の流れと必要な手続き
- 経済的に厳しい場合の公的支援・無料相談・高額介護費用控除について
|
老人ホーム・介護施設の費用相場・施設選びの注意点
施設ごとに特徴と費用感は異なります。ここでは代表的な5つの施設を簡単にご紹介いたします。
サービス種別 | 月額費用 | 概要 |
|---|
介護付き有料老人ホーム | 15〜30万円前後
※入居一時金が必要な場合もある | 介護スタッフが24時間常駐し、日常生活のサポートを受けられます。 |
住宅型有料老人ホーム | 10〜20万円前後 | 比較的、要介護度が低い高齢者向けの居住施設です。介護サービスが必要な場合は、外部の事業所によるサポートを利用します。 |
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 12〜20万円前後
(家賃込み) | バリアフリー構造の賃貸住宅で、見守りや生活相談などのサービスを受けられます。介護サービスは外部提供が基本です。 |
グループホーム | 15〜20万円前後 | 認知症の方を対象とした少人数の共同生活型施設です。家庭的な雰囲気の中で生活できます。 |
ケアハウス | 10万円前後 | 自立した高齢者向けの軽費老人ホームで、食事や生活支援が受けられます。要介護状態になると、外部サービスの導入が必要です。 |
選ぶ際は、介護度や生活スタイル、費用、立地条件を総合的に検討しましょう。複数の施設を見学して、雰囲気や対応を確認するのがおすすめです。
◆関連記事:介護サービスの種類
施設入居(介護施設・ショートステイ)の流れと必要な手続き
施設入居の流れは、おおまかに以下のとおりです。
- 情報収集・相談:ケアマネージャーや地域包括支援センター、インターネットから情報を集めます。
- 資料請求・見学:候補の施設に資料を請求し、見学して雰囲気や対応を確認しましょう。
- 入居申込・面談:申込書や診療情報提供書などの必要書類を提出し、施設スタッフが本人様・ご家族様・身内の方と面談します。
- 審査・契約・入居:施設に空きがあり、受け入れ可能の審査結果が出れば、契約を結び入居します。
※ショートステイを利用する場合は、ケアマネージャーに相談してケアプランに組み込んでもらう必要があります。
経済的に厳しい場合の公的支援・無料相談・高額介護費用控除について
介護費用が経済的に大きな負担となる場合には、以下のような支援制度や相談先があります。
高額介護サービス費制度 | 介護保険サービスの自己負担額が、世帯や個人ごとに設定された月額上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。食費や居住費などは含まれません。 |
介護保険負担限度額認定 | 所得に応じて、施設利用時の食費・居住費が軽減されます。市区町村への申請および認定が必要です。 |
自治体独自の助成 | 住宅改修費や福祉用具購入費など、自治体独自の支援を受けられる場合があります。詳細は地域包括支援センターや市区町村の福祉窓口で確認しましょう。 |
生活保護制度 | 生活が困窮した場合は、最後のセーフティーネットとしての役割があります。 |
無料相談窓口 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会、市区町村の介護保険課などで、介護費用や制度の相談が無料でできます。 |
経済的な不安を感じたら、まずは地域包括支援センターや市区町村窓口に相談して、利用できる制度や手続きについて情報収集しましょう。
親が認知症、要介護になったら?それぞれの段階で取るべき対応やポイント

親が認知症や要介護状態になった場合の対応は、悩みが深くなりやすいものです。いざというときに焦らないよう、それぞれの段階で必要な準備を事前に理解しておきましょう。
親が認知症・要介護になったときに確認しておきたいこと |
|---|
- 認知症・病気の診断・介護認定の申請から判定・要介護度の把握
- 在宅介護か施設介護か選ぶときのポイント
- ご家族様の気持ちも大切にした話し合いの進め方
|
認知症・病気の診断・介護認定の申請から判定・要介護度の把握
ご家族様が「最近、物忘れが増えた」「様子が違う」と感じたら、まず主治医に相談しましょう。必要に応じて、物忘れ外来など、専門医を紹介してもらうのが一般的な流れです。
認知症などの診断を受けた場合は、適切なサポートにつなげます。介護サービスが必要な場合は、地域包括支援センターや市区町村の窓口で要介護認定の申請を行いましょう。認定結果に基づき、支給限度額が決まります。
ケアマネージャーと相談し、ケアプランを作成してサービス利用を開始します。
在宅介護か施設介護か選ぶ時の3つのポイント
ご家族様が認知症や要介護状態になったとき「在宅で介護を続けるか」「施設への入居を検討するか」は、とても重要な判断です。
①経済的に可能かどうか
- 施設の入居金や月額費用を無理なく支払えるか
- 在宅介護の場合、必要な介護用品・サービス費用はどれくらいか
②介護者の負担はどのくらいか
- 介護者の体力・時間・精神面において、在宅生活を続けられるか
- 施設介護に切り替えた場合、訪問や連絡は可能か
③ご家族様のお気持ちはどうか
- 在宅もしくは施設、どちらを望んでいるか
- 施設の雰囲気に馴染めそうか、抵抗感はないか
ご家族様のお気持ち、介護者の状況、経済面を考慮し、納得できる選択をしていきましょう。
ご家族様の気持ちも大切にした話し合いの進め方
介護方針を決めるときは「ご家族様の気持ちを置き去りにしないこと」が大切です。どんな暮らしを望んでいるかを丁寧に聴きましょう。
介護する側の事情も冷静に伝え、互いに理解し合う姿勢を心がけましょう。話し合いは一度で決めず、何度か機会を持つことも大切です。
必要に応じて、親族やケアマネージャーなど第三者の意見を取り入れると、広い視点で話を進められます。
施設入居は「在宅で介護しなければ」と感じる方にとっては罪悪感を抱きやすいものです。しかし、施設ではスタッフによる24時間体制のサポートがあり、安心して過ごせる環境が整っています。施設入居は、「ご家族様を大切にするための選択肢」ともいえるのです。
遠方に親が住んでいる場合の介護
ご家族様が遠方に住んでいる場合、介護はより難しくなりがちです。しかし、工夫や周囲との連携で、無理なく介護を進められます。ここでは、遠距離介護に役立つポイントを紹介いたします。
ひとりで背負わないためのネットワーク・介護体制を作る
離れていてもサポートできる体制づくりが重要です。現地のご親族様や友人、民生委員、地域包括支援センターの職員など、いざというときに頼れる人を探しておきましょう。
ケアマネージャーとは電話やメールで定期的に連絡を取り、情報を共有しましょう。帰省時には必要な手続きや関係者との面談をまとめて予定しておくと効率的です。
緊急時やショートステイなどの使い方
遠距離介護では、緊急時の対応策を事前に準備しておくことが大切です。定期的にショートステイやデイサービスを利用することで、ご家族様の生活リズムや体調を把握しやすくなり、「万一のとき」の備えになります。
遠距離介護に役立つ緊急時対策 |
|---|
- 訪問看護の活用:緊急時には、夜間でも訪問してくれます。
- 民間の駆け付けサービス:警備会社などが提供しています。ご家族様がボタンを押せば緊急対応してくれる仕組みです。
- 見守りサービスの導入:ポットや冷蔵庫など家電の使用履歴がスマートフォンに転送され、遠隔からご家族様の生活状況を把握できます。
|
これらを組み合わせることで、遠方からでも安心して見守れる体制を整えましょう。
介護の悩みを相談できる窓口の紹介

介護の悩みや困りごとを「誰に相談すればいいのか分からない」と感じることがあるかもしれません。ここでは、気軽に相談できる窓口をご紹介いたします。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の介護や福祉に関する総合相談窓口です。「介護が必要になるかもしれない」などの初期段階でも相談できます。
介護への不安やサービス開始までの流れなど、幅広くアドバイスや情報提供を受けられます。また、介護認定の申請やケアマネージャーの紹介、必要に応じた専門機関へつないでくれるので、気軽に相談してみましょう。
公共サービスの相談窓口
市区町村の介護保険担当課や社会福祉協議会など、地域の公共サービス窓口でも相談を受付ています。介護保険制度の仕組みや申請の手順、利用できる介護サービスの種類や条件、経済的支援などの情報を提供してくれます。
不安を感じたら、早めに相談し、サポートにつなげましょう。
マイナビあなたの介護
「マイナビあなたの介護」では、介護や医療の現場をよく知るコンシェルジュが、介護全般のお悩みに無料でアドバイスや情報提供を行っています。
「親が認知症かもしれない…」「在宅介護でやっていけるのかな」「施設を探したいけど何から始めればいい?」といったお悩みも、電話やLINEで相談できます。
「電話は少し緊張する」という方には、LINE相談がおすすめです。じっくり考えながら質問できるので、安心して本音を伝えられます。
ひとりで抱え込まず、まずは「マイナビあなたの介護」に相談しましょう。
今すぐ相談してみる ▶
まとめ:一人っ子が介護問題で後悔しないために

一人っ子の方にとって、ご家族様の介護は負担が大きく、悩みや戸惑いを感じるのは当然のことです。しかし、事前に備えや心構えをしておくことで、スムーズな支援につなげられます。
この記事のポイントは、以下のとおりです。
- 介護は突然始まることが多く、ひとりで抱えてしまいがちです。
- ひとりで抱え込まず、周囲のサポートを活用しましょう。
- ご本人様のお気持ちと介護者の生活バランスが大切です。
- 元気なうちに少しずつ話し合い、気持ちや希望を共有しておきましょう。
次章に、将来を見据えた準備・安心につながる行動リストを紹介します。ぜひお役立てください。
将来を見据えた準備・安心につながる行動リスト
介護が必要になったときの混乱を減らすためにも、今からできる準備を少しずつ始めていきましょう。
- 親とコミュニケーションを取る:元気なうちに、介護や終末期医療、財産管理などについて話し合い、エンディングノートを活用するのもおすすめです。
- 地域包括支援センターに相談する:専門家のアドバイスを受けることで、不安が軽減されます。
- 介護保険制度について学ぶ:どんなサービスがあり、どう活用できるのか事前に理解しておきましょう。
- ご家族様の健康状態・経済状況を把握する:医療・介護・資産情報を整理しておきます。
- 自分のライフプランを考える:介護と仕事をどう両立するか、プライベートも含めて計画しておきましょう。
- 相談先を見つけておく:ご親族様、友人、地域の支援、介護者の会など、支えとなる存在を見つけておきましょう。
- 心と体のケアを忘れない:休息やストレス解消を心がけましょう。
上記のチェックリストを参考に、できることから一歩ずつ、無理なく進めていきましょう。
しかし、ご自分の生活と介護を両立しようとしている方の中には、「自分の状況に合った対応方法を知りたい」「窓口に行く時間がない」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
「マイナビあなたの介護」では、介護や医療の現場をよく知る専門家が、在宅介護や施設探し、認知症ケアなど幅広い相談に無料で対応しています。
電話やLINEで気軽に相談でき、専門家が親身にサポートしてくれます。「誰にも話せず悩んでいる」という方も、まずは気軽に「マイナビあなたの介護」に相談してみませんか?
著者・監修現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。