高齢期の安心・安全な暮らしを求めて老人ホームへの入居を検討する方が増えています。しかし、実際に入居してみると「思っていたサービスと違う」「スタッフとの関係がうまくいかない」など、予期せぬトラブルに直面するケースも少なくありません。
この記事では、現場で実際にあったトラブル事例を参考に「どんな理由でトラブルが起きやすいのか」「ご本人様やご家族様がどんな行動を取れば良いのか」そして「事前に確認・準備できること」について解説いたします。
記事をシェアする
高齢期の安心・安全な暮らしを求めて老人ホームへの入居を検討する方が増えています。しかし、実際に入居してみると「思っていたサービスと違う」「スタッフとの関係がうまくいかない」など、予期せぬトラブルに直面するケースも少なくありません。
この記事では、現場で実際にあったトラブル事例を参考に「どんな理由でトラブルが起きやすいのか」「ご本人様やご家族様がどんな行動を取れば良いのか」そして「事前に確認・準備できること」について解説いたします。
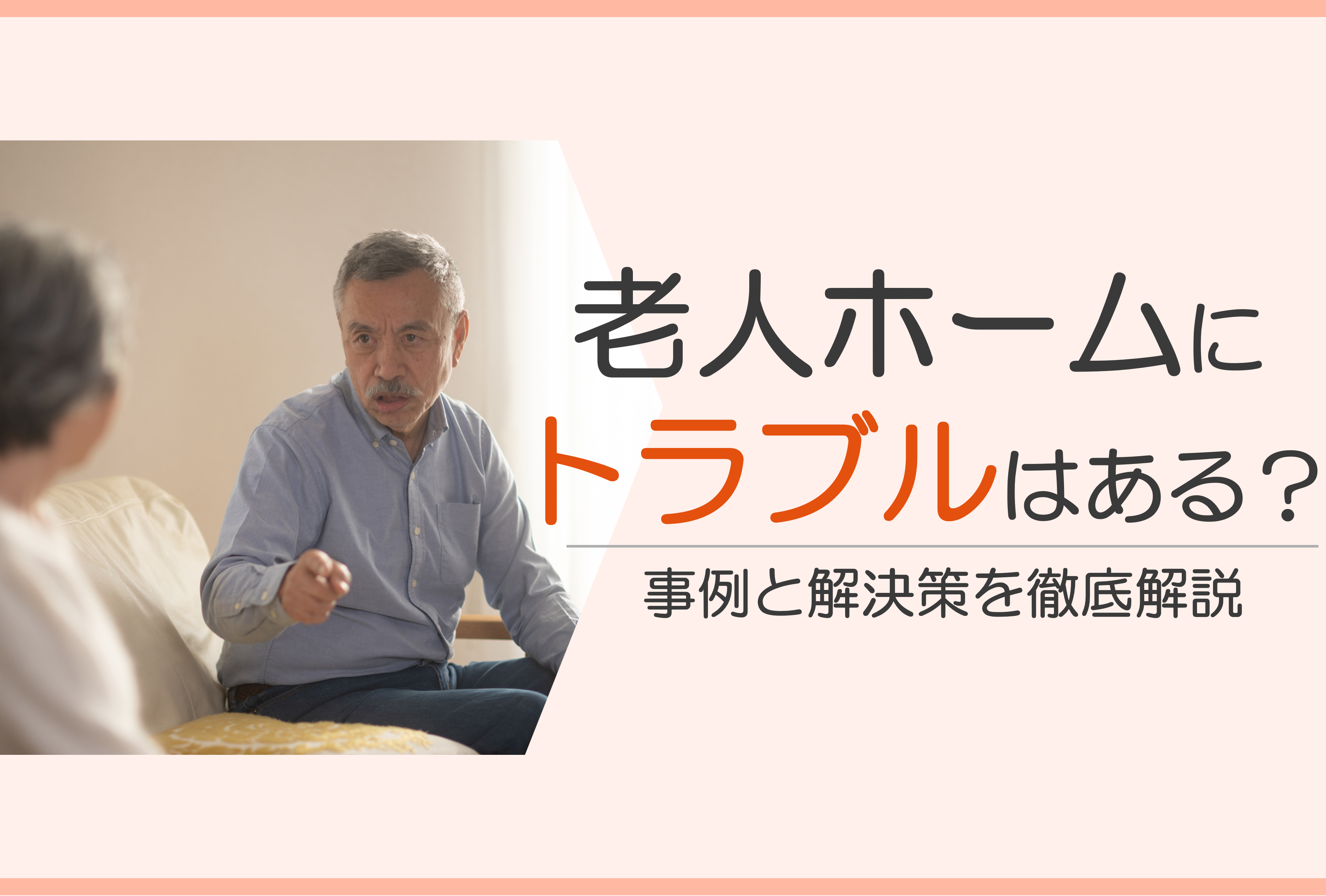



Aさん(80代女性)は、隣室のBさん(70代男性)が夜中に物を整理したり、ごそごそと音を立てることに悩まされていました。
Bさんは活発な性格で、夜間であっても、部屋を整理したり物を探したりすることが多かったのです。Aさんは眠れずにイライラし、直接「夜はもう少し静かにしてもらえませんか」と声をかけました。
Bさんは「分かりました」と応じましたが、Bさんには軽度の認知症があり、悪気なく夜間の活動は続いてしまいます。結局、Aさんは眠れない日々が続き、ご家族やスタッフに相談することになりました。
夜間の物音や活動音は、睡眠を妨げ、心身の健康に影響を与えます。特に認知症の症状が見られる場合、当事者に悪気がないことも多く、周囲の理解と配慮が必要です。ご家族ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
夜間にスタッフからの声掛けは難しいため、施設側としてはBさんに対して日中に声掛けやケアの工夫を行い、夜間の活動を落ち着かせるための環境調整を検討します。
Bさんには悪気がないことを踏まえ、Bさんのご家族から、夜間の行動について「夜はなるべく静かに」と繰り返し声を掛けてもらうことで、夜間の落ち着きにつながるかもしれません。
また、Aさんが安心して過ごせるよう、家族やスタッフと情報を共有し、必要に応じて部屋移動の希望を叶えるなど、状況に応じた対応を進めていきます。
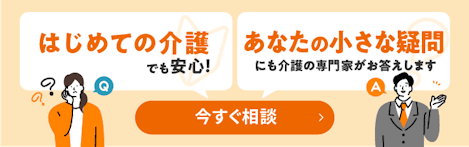
Cさん(78歳女性)は、ある入居者様から「昔の自慢話ばかりする」「いつも偉そうにしている」と陰口を言われているのを耳にしました。
その後、Cさんは共有スペースに出るのを避けるようになり、好きだったレクリエーションやサークル活動に参加することも少なくなってしまいます。気分が沈みがちになり、ひとりで過ごす時間が多くなっていったのです。
陰口や仲間外れは、ご本人様の自尊心を傷つけ、生活意欲の低下や孤立感につながる深刻な問題です。活動意欲の低下が続くと、食欲不振やADL(日常生活動作)の低下、さらには認知症の進行リスクを高める可能性もあるため、早めの対応が重要です。
ご家族ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
施設としては、まず現場リーダーやケアマネージャーがCさんの心情に寄り添い、どのような状況で陰口を耳にしたのか詳しく伺います。その情報を関係スタッフと共有し、チームとして対応を検討します。
陰口を言った入居者様への直接的な指導が難しい場合でも、生活相談員や介護スタッフがさりげなくグループ間の交流を促したり、レクリエーションの際に別の活動に誘導したりするなど、Cさんが心地よく過ごせるような配慮を施設全体で行うことが大切です。
また、Cさんが困ったときに、すぐ相談できるような環境を整えることが求められます。施設内に複数のグループがある場合には、別のグループとCさんが自然な形で交流できるようサポートすることも有効です。

Dさん(85歳男性)のご家族が面会に訪れた際、ある特定の職員がDさんに対して、あまり笑顔が見られず、淡々とした口調で話しかけている様子を目にしました。
他の入居者様への対応も同様の様子でしたが、老人ホームにふさわしい対応なのか少し疑問に感じたようです。ご家族がDさんに「普段はどんな感じ?」と聞いたところ、「あまり話をしたことがないけど、なんとなく冷たく感じる」と答えたため、心配になり、施設のスタッフやケアマネージャーに相談しました。
職員に悪気はなくても、経験が浅かったり余裕が無かったりして、十分な対応ができていない場合もあります。職員の対応に疑問や不安を感じた場合、まずは「どんな部分が気になったのか」を整理し、具体的な行動に移すことが大切です。
ご家族ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
施設としてこのようなご相談を受けた場合、まずはケアマネージャーや現場リーダーが、ご本人様やご家族のお話を丁寧に伺い、具体的な状況を正確に把握することから始めます。
現場スタッフには、事実の確認と共に、職員の接し方やコミュニケーションの背景を聞き取り、改善を求めます。場合によっては、スタッフ教育や研修の実施、スタッフ間での情報共有の徹底を図ることも考えられるでしょう。
重要なのは、特定の職員だけを責めるのではなく、施設全体でケアの質を向上させる意識を持つことです。ご本人様には「何か気になることがあれば、いつでも相談してください」と声を掛け、不安を少しでも和らげるように努めます。
Eさん(82歳男性)は、「この施設は、看取りまで対応可能です」との説明を受け、安心して入居しました。ところが、病状が進行し、慢性呼吸不全による在宅酸素療法が必要な状態となった際、施設から「これ以上は施設では対応できません。入院を検討していただきたいです」と告げられます。
ご家族は「話が違う」と困惑し、施設スタッフやケアマネージャーに相談しました。
「看取り可能」とされている施設でも、医療体制には限界があります。特に、慢性呼吸不全による在宅酸素療法が必要となると、24時間の酸素管理や見守りが求められるため、施設での対応は難しくなる場合があるのです。
ご家族ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
施設ケアマネージャーや施設長、現場リーダーなどが中心となり、主治医と連携してEさんが安心して次の療養先へ移行できるよう調整を行います。
施設に求められるのは、ご本人様・ご家族が急な入院や退去に不安や混乱を感じないよう、分かりやすい説明とサポートを行うことです。
Fさん(79歳女性)は、グループホームで食事介助を受けていました。ある日、食事中にむせ込み、急に苦しそうな様子を見せ、顔色が紫色に変わっていきました(チアノーゼ)。
看護師がすぐに対応し、救急搬送されたため、一命を取り留めます。その後、ご家族は「食事の見守り体制や介助方法に問題があったのでは」と心配になり、施設長に相談しました。
誤嚥事故は、高齢者にとって生命に関わるリスクであり、特に嚥下(えんげ)機能が低下している方は注意が必要です。食事介助や見守りの体制、嚥下機能に合わせた食事内容の調整が重要です。
ご家族ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
施設長や現場リーダーなどが中心となり、事故の経緯を確認し、再発防止策を検討します。また、このような事故が発生した場合は、行政への届け出義務があるため、書面にて報告を行います。
ご家族への説明も行い、不安や疑問に丁寧に対応することも欠かせません。必要に応じて、食事形態の見直しや職員への嚥下対応の研修を実施し、再発防止に努めます。

Gさん(78歳女性)は、東京都内の有料老人ホームに入居する際、前払金として約1,000万円を支払いました。しかし入居後、施設の雰囲気や環境が合わず、3ヶ月以内に退去を希望します。
退去時、施設から「短期解約特例により前払金の一部は返金されます」と説明されましたが、実際の返金額は予想より少なく、「話が違う」と困惑します。ご家族は「契約時にもっと詳しい説明をしてほしかった」と施設長に不満を伝えました。
※短期解約特例とは、入居後3ヶ月以内に退去した場合、前払金のうち入居期間分の日割家賃などを除いた金額が返還される仕組みです。
有料老人ホームの入居一時金(前払金)の返金額は、契約内容によって異なります。特に「初期償却の有無」や「償却期間」、「短期解約特例」の適用条件によって、返金される金額が左右されます。
2021年4月以降、施設側には前払金の返還債務を保全する義務があります。これは、介護施設倒産時のリスク軽減策であり、返金額は、未償却金(前払金の残額)または500万円のいずれか低い方と定められています。
一般的には、前払金の償却期間は5年〜20年程度であり、初期償却の有無や契約からの経過期間にもよりますが、未償却金の目安としては数百万円〜500万円未満となるケースが多いです。
ご家族ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
ケアマネージャーとしては、ご家族様に「契約前に必ず重要事項説明書を丁寧に確認し、不明点はしっかり質問する」ことの重要性をお伝えしています。
特に金銭面はトラブルにつながりやすいため、契約時に初期償却や償却期間、返金ルールを把握しておきましょう。
【参考】東京都消費生活総合センター「有料老人ホームに入居する際に支払った前払金は返してもらえるの?」
Hさん(83歳男性)は、認知症の進行に伴い、施設内で他の入居者様の居室に無断で入る行動や、廊下で歩いている他の入居者様を「泥棒だ」と誤解して、つかみかかる行動が見られるようになりました。
施設側は「他の入居者様への影響が大きく、このままでは安心・安全な生活環境を維持できない」として、ご家族に相談します。ご家族も「他の施設に移るのは難しいのではないか」と感じ、施設側と共に、主治医に相談を行い、Hさんが安心して医療的ケアを受けられるよう、病院入院を勧めることになりました。
認知症の症状による問題行動は、ご家族や他の入居者様にとっても大きな問題です。特に、他の入居者様の安心・安全が脅かされると施設側が判断した場合、契約内容に基づき「契約解除」となることもあります。
しかし、施設もご本人様を「追い出す」のではなく、ご家族と共に、可能な限り対応策を検討するのが一般的です。
ご家族と施設ができることとしては、以下のような対応が考えられます。
|
施設のケアマネージャーや相談員、現場リーダーらが中心となり、主治医と連携を取りながら、Hさんの状態を正確に把握し、安心して次の生活を迎えられるよう調整します。

老人ホームでのトラブルを回避するためには、事前の情報収集が大切です。ここでは、見学や説明の際に確認すべきポイントを紹介いたします。
入居後のトラブルを避けるためにも、見学や説明を受ける際には、次のような点を確認しておきましょう。
清潔さ、明るさ、入居者様やスタッフの表情、共用スペースの使いやすさなどをチェックしましょう。
挨拶や説明の丁寧さ、入居者様との接し方を観察し、信頼できるかどうかを確認します。
看護師の配置状況、協力医療機関、緊急時の対応、医療対応の限界(例:在宅酸素や経管栄養が必要な場合)について事前に確認しておきましょう。
食事形態(刻み食、ミキサー食、アレルギー対応など)、レクリエーションの種類や頻度、個別対応の有無などを質問しておくと安心です。
前払金(入居一時金)の初期償却や償却期間、月額利用料、追加費用(おむつ代、理美容代など)の有無と内訳を確認します。
過去に起きたトラブル事例や解決策を聞き、誠実な対応をしている施設かどうかを見極めましょう。
認知症が進行した場合の対応方針や、看取りまでの流れについて具体的に質問しましょう。
見学時には、ご本人様の性格や生活習慣を施設側に伝え、「どのようなケアを受けられるのか」「トラブルを防ぐためにどんな配慮が必要か」を話し合いましょう。
契約・費用関連 |
|---|
|
生活環境・設備関連 |
|---|
|
介護・医療サービス関連 |
|---|
|
スタッフの質・体制関連 |
|---|
|
その他 |
|---|
|
このチェックリストを使用し、ご本人様やご家族が安心できる入居先かどうかを確認しましょう。

この記事では、老人ホームに入居後のトラブルを避けるために、事前の準備と入居後の対応について詳しく解説しました。以下に、この記事のポイントをまとめます。
特に、金銭面や対人関係で起こりやすいトラブルについては、あらかじめ、どのような事例があるのかを確認しておくことが大切です。急に退去を迫られ「これからどうしたらいいの?」とパニックにならないよう、事前の備えをしておきましょう。
「施設入所を検討しているけれど、どのように情報収集したらいいか分からない」「親にぴったりの施設を見つけたい」と感じている方は、ぜひ「マイナビあなたの介護」を活用してみてください。
「マイナビあなたの介護」では、施設選びのポイントや入居前後の手続き、費用やサービス内容、トラブル事例まで、幅広い情報を分かりやすくご紹介しています。
希望する施設の資料請求や見学のお申し込みもでき、何度でも無料でお問い合わせ可能です。さらに、LINEを通じて専門家に相談できる窓口もあり、忙しい方でも自宅にいながら情報収集や悩み相談ができます。
この記事を参考に、施設入所に関する不安を解消していただけたら幸いです。

介護支援専門員(ケアマネージャー)
朝水 裕一
介護支援専門員(ケアマネージャー)
朝水 裕一
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。