高齢になったり、病気や障害を抱えたりすると、少しの距離を移動することも大変で、サポートが必要になりがちです。
そこで活用したいのが、介護タクシー。
安全で快適に目的地まで送迎してもらうことができ、介護者が時間を有効活用することにもつながるので、サービスの種類や料金などをチェックしておきましょう。
記事をシェアする
高齢になったり、病気や障害を抱えたりすると、少しの距離を移動することも大変で、サポートが必要になりがちです。
そこで活用したいのが、介護タクシー。
安全で快適に目的地まで送迎してもらうことができ、介護者が時間を有効活用することにもつながるので、サービスの種類や料金などをチェックしておきましょう。

介護タクシーとは、自力での外出が困難な人に向けて提供される移動・送迎サービスの呼称です。
高齢者、要介護状態の人、身体が不自由な人などの安全な移動をサポートするもので、車いす使用者でも乗り降りしやすいなど、車両設備や構造が工夫されていることが特徴の一つ。
介護タクシーを上手に活用し、時間がかかりがちな移動介助をプロに頼めれば、介護における時間の使い方を見直すことも可能になります。
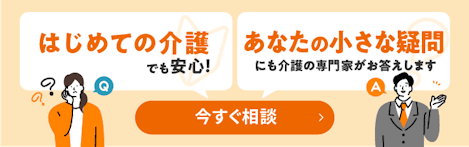

介護タクシーは、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、介護保険が適用されるパターンです。訪問介護サービスのうち「通院等乗降介助」に該当し、車への乗降介助や、車いすへの移乗介助、目的地までの移動介助なども含まれています。
運転手は二種免許に加えて、介護福祉士などの資格あるいは介護職員初任者研修の受講などが求められます。
介護保険が適用されることで費用を抑えられる反面、利用目的が「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」に限られるなど制限があります。
2つ目は介護保険が適用されないパターンで、「福祉タクシー」などと呼ばれることもあります。
通院など生活に欠かせない目的以外にも、娯楽や趣味などのために自由度高く使うことができますが、費用は全額自己負担となります。
また、乗降時の介助などで、家族の付き添いが求められるケースも少なくありません。
介護保険が適用される介護タクシーの場合は、要介護認定で「要介護1〜5」と認定された人が対象です。
自力で公共交通機関を利用することが難しく、車いすやストレッチャーでの移動となる場合などが想定されます。
一方、介護保険が適用されないタクシーでは、介護度などの条件は基本的にありません。
移動に不安が出てきた、体に障害がある、けがで一時的に歩行が困難……など、幅広い人の悩みに対応しています。

どちらのタイプも、予約の日時になると介護タクシーが自宅などを訪れ、運転手が目的地まで送り届けてくれます。移動距離や時間、必要な介助などについて家族間で話し合い、ニーズに合った介護タクシー事業者を選びましょう。
介護保険適用で介護タクシーを使う場合、当該サービスをケアプランに組み込んでもらうことによって、利用時に介護保険の自己負担割合に応じた料金の支払いのみで利用可能となります。
ケアプランを居宅介護支援事業所のケアマネージャーが作成している場合は、担当のケアマネージャーに移動が困難である旨や、「通院で使いたい」「日用品の買い物のためスーパーまで行きたい」など利用目的を具体的に伝えましょう。
ただしケアプランが作成されずに介護タクシーを利用した場合も、一旦全額利用料金を負担し、領収書を市町村に提出することで、後日利用者負担分を除いた金額が払い戻されるという償還払いが適用されます。
介護タクシー事業者を選び、契約を結びます。ケアプランに基づいてサービス利用する場合は、ケアマネジャーに要望を伝えて、候補を挙げてもらうとスムーズでしょう。予約の方法、料金形態、利用目的ごとにかかる費用、支払い方法などを確認しておくと、「こんなはずじゃなかった!」というギャップを感じにくくなります。
契約した介護タクシー事業者に、利用日時を伝え予約を取ります。この時、使用する車いすの種類や必要な福祉用具などを合わせて伝えたり、移動時の注意事項を共有したりします。
予約の日時に、介護タクシーが自宅などへ迎えに来ます。集合住宅や狭い路地に面している場合などには、安全に乗降ができる場所で待ち合わせをすることもあるようです。
不安なことがあれば、前日までに事業者に確認しておきましょう。
介護保険適用のサービスにこだわらない場合、事業者に電話で問い合わせたりすることはもちろん、アプリなどを利用して気軽に介護タクシーを手配することも可能になってきました。
スマートフォン一つで、料金の見積りや予約状況の確認、配車の手配などが可能で、手間なく介護タクシーを利用できる点が魅力です。
ただし、事業者によって「できることの範囲」には差があるので、事前にしっかりと調べておきましょう。

介護タクシーにかかる料金の内訳は、主に「運賃」「介護サービス費用介助料」「器具福祉用具のレンタル費用」の3つです。介護保険サービスを利用すれば「介護サービス費用介助料」が1~3割負担となり、出費を抑えることができます。
一般的なタクシーと同じく、時間制運賃、距離制運賃、時間距離併用制運賃のいずれかが適用されます。
また、予約料が必要な事業者も。具体的な金額は地域や事業者によってさまざまで、介護保険適用の場合は割引料金を設定する場合もあるようです。
車両への乗り降りや移乗介助、着替えなど身支度の介助、室内・室外での付き添いなど、移動に関わるさまざまな介助に対してかかる料金です。
これらには介護保険サービスが適用され、原則1割※の自己負担(片道100円程度)で利用することができます。
※所得に応じて負担割合と金額額は変動
車いすやストレッチャーなど、福祉用具等のレンタルが必要な場合に、数千円程度の費用が加算されます(自分で福祉用具等を用意する場合には料金はかかりません)。
事業者によってレンタルできる福祉用具等の種類が異なるため、希望する用具が借りられるか調べておきましょう。
介護保険が適用されない介護タクシーの運賃も、一般的なタクシーと変わりはありません。
また、介助料は、事業者によって料金設定がさまざまで、受けたいサービスによっても大きく変動するので、利用する前に確認しておくと安心です。
介護サービス費用、器具レンタル費用ともに、全額自己負担となります。

それでは、実際に介護タクシーを利用している人の事例を見てみましょう。自分や家族ならどんな活用の仕方ができそうか、想像してみてください。
要介護1のAさんは、近所の診療所の他に、隣町の専門医にもかかっています。持病の関係で、家からは遠くてもそこで診察・処方してもらう必要があり、家族と一緒に電車やバスを乗り継いで通っていました。
しかし、家族の仕事が忙しくなり、同行してもらうことが難しくなったので、ケアマネージャーに相談。すぐに対応してもらい、介護タクシーの利用を開始しました。
格段に移動が楽になった上に、毎月会う運転手とのコミュニケーションが楽しく、おしゃべりしながらの通院が生活の張りになっています。
Bさんはクレジットカードを所有しておらず、銀行のATMを訪れて現金を下ろしたり、各種料金の振り込みをしたりして、通帳に記帳をするという習慣がありました。
以前はスクーターで移動していましたが、大腿骨を骨折後、自力での移動が困難な状態に。
そこで、要介護認定を受けた後、介護タクシーの利用をケアプランに組み込んでもらいました。
必要に応じて車いすなどの福祉用具もレンタルできるため、安全に用事を済ませることができ助かっています。
Cさんは、とある演歌歌手の大ファン。コンサートにも足繁く通っていましたが、最近では耳が遠くなり、電車のアナウンスが聞こえづらくなってきました。
また、視力も落ち、電光掲示板の文字が読めないこともしばしば。公共交通機関を利用することに不安を感じて足が遠のいていたところ、友人に勧められて介護タクシーを利用してみることにしました。
趣味活動には介護保険サービスは適用されず保険外の介護タクシーを利用することになるため全額自己負担ではありますが、安全にコンサート会場まで送迎してもらえることには大きな安心感があり、大幅にストレスが軽減されました。

移動に不便さを感じている人にとって、とても心強い存在となる介護タクシーですが、注意点もあります。利用する前に知っておきたい、3つのポイントを紹介します。
介護保険適用での利用には、介護度や利用目的(通院、入退院、役所での手続き、金銭の出し入れなど)に条件が設けられます。
必ずケアマネージャーに相談の上、該当するかを確認しておきましょう。
該当しない場合には、介護保険適用外のサービスを利用するという手段があります(趣味や娯楽のために利用することも可能)。
介護保険適用の介護タクシーの場合、基本的に家族は同乗することができません。
ただし、認知症や精神疾患があったり、痰の吸引が必要だったりする場合などには、家族も一緒に乗ることが認められるケースもあります。
同乗を希望する場合は、ケアマネージャー等に相談してみましょう。
通院で利用する際には、「病院に着いてからどうするか?」をイメージしておくことが大切です。
原則的には、病院内では看護師などの院内スタッフが介助・同行することになります。
慣れ親しんでいる運転手だからといって、ずっと一緒に行動してもらえるとは限らないことを覚えておきましょう。

介護タクシーを利用することで、通院や買い物など生活に関わる移動をサポートしてもらうことができます。
安全かつ快適に目的地まで送迎してもらえることは、本人はもちろん家族にとっても安心で、時間を有効活用することにもつながります。
要介護認定を受けることで費用を抑えられる可能性があるので、移動に不安を感じている人は、介護保険サービスの利用を検討するきっかけにしてもよいでしょう。
介護サービスの使い方や選択に迷ったときは、「マイナビあなたの介護」を活用することもお勧めです。LINEや電話などから、いつでも相談OK。施設探し、介護準備のサポート、資料請求・見学申込の代行など、さまざまな支援を行っているので、お気軽にお声がけください。

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
記事をシェアする