「最近、親がささいなことで怒るようになった…」「これまで穏やかだったのに、イライラして、強い口調になることが増えた…」そんなご家族様の変化に戸惑いや不安を感じていませんか?実はこのような「怒りっぽくなる」性格の変化は、認知症の初期症状として見られることがあります。
この記事では、怒りっぽさの原因や加齢による性格変化との違い、接し方のポイント、実際の事例までを分かりやすく解説いたします。大切なご家族様と穏やかな時間を過ごすために、ぜひ最後までご覧ください。
記事をシェアする
「最近、親がささいなことで怒るようになった…」「これまで穏やかだったのに、イライラして、強い口調になることが増えた…」そんなご家族様の変化に戸惑いや不安を感じていませんか?実はこのような「怒りっぽくなる」性格の変化は、認知症の初期症状として見られることがあります。
この記事では、怒りっぽさの原因や加齢による性格変化との違い、接し方のポイント、実際の事例までを分かりやすく解説いたします。大切なご家族様と穏やかな時間を過ごすために、ぜひ最後までご覧ください。


これまで穏やかだったご家族様が、ささいなことでイライラしたり、急に怒り出すようになり、驚きや不安を感じておられるかもしれません。
もしかするとそれは、認知症の初期症状の一つである「性格の変化」が関係している可能性があります。

認知症の初期段階では、記憶力の低下だけでなく「怒りっぽい」「イライラしやすい」といった感情や性格の変化が見られることがあります。
これは、認知症によって脳の機能が変化し、感情のコントロールが難しくなったり、不安や混乱を感じやすくなったりするために起こるとされています。まずは「認知症が引き起こす症状の一つかもしれない」と知っておくことが大切です。
怒りっぽさ以外にも、認知症の初期には以下のような症状が見られることがあります。
認知症の初期には、新しい出来事を記憶するのが難しくなります。体験したこと自体を忘れてしまうため、ヒントを聞いても思い出せないことが多いです。具体的には、以下のような様子が見られます。
日常会話や物の管理が難しくなり、周囲とのやり取りにすれ違いが起こりやすくなります。
物事を順序立てて考えたり、適切に判断したりする力が低下していきます。具体的には、以下のような変化です。
今までスムーズにできていたことに支障が出るため、自信を失いやすくなります。
時間や場所、人などに関する認識があいまいになり、混乱することがあります。具体的には、以下のような様子が見られます。
不安感が強まる原因になり、外出を避けたり、人と会うのをためらったりすることもあります。
感情面にも変化が表れ、活動意欲が低下したり、抑うつ的になることがあります。以下のような変化が見られます。
周囲から見ると「疲れているだけでは?」と感じられやすく、早期の変化として見逃されることもあります。
「年齢を重ねて涙もろくなる」「少し頑固になる」などの性格変化は、誰にでも起こりうるものです。しかし、認知症による怒りっぽさには、以下のような特徴があります。
これらの特徴は、他の認知症の症状と並行して進行することもあります。
当てはまる点が多い場合には、家族や身近な人と状況を共有しながら、対応していく必要があるかもしれません。

認知症の方が怒りっぽくなる背景には、脳機能の低下だけでなく、心理的および環境的な要因が関係しています。
なぜ認知症になると怒りっぽくなるのか |
|---|
|
認知症が進行すると、「何をしようとしていたか忘れてしまう」「周囲の状況が分からない」といった記憶や理解力の低下が目立つようになります。
ご家族様にとっては、日常の出来事のつながりが分からなくなり、強い不安や混乱を感じやすくなるのです。そうした気持ちがうまく処理できず、「怒り」として表れることがあります。
「これまで簡単にできたことができない」「言葉がうまく出てこない」「思うように体が動かない」といった変化が、認知症の方にとって大きなストレスになります。
ご家族様は「できない自分」に戸惑いや焦りを感じ、強いもどかしさを抱えているのです。そうした状態が続くと、いら立ちが積み重なり、怒りとして表れることがあります。
認知症が進行すると、言葉の選び方や理解力に支障が出て、相手に気持ちを伝えるのが難しくなります。また、相手の話を十分に理解できなかったり、会話のテンポについていけなかったりすることも増えます。
うまく通じ合えないことが続くと、ご家族様にとって強い「いら立ち」となり、怒りの感情として表れることがあるのです。
感情をコントロールする脳の機能は、認知症によって徐々に低下していきます。そのため、ささいなことでも感情が高ぶり、ご自分で怒りを抑えることが難しくなるのです。
ご家族様の性格が変わったのではなく、脳の変化によって起こる「症状」と理解することが大切です。
体調不良や、環境の変化によるストレスも、怒りっぽくなる一因になります。具体的には、以下のような要因が影響します。
以上のことについて、うまく言葉で伝えられず、不快感や混乱が怒りとなって表れることがあります。

介護現場やご家庭で実際に起こった、怒りっぽくなった方に関する事例を4つご紹介します。
認知症の初期症状によくある事例 |
|---|
|
80代の女性で、長男夫婦と同居している方のお話です。
物忘れや怒りっぽさが見られるようになり、2ヶ月ほど前からお風呂を強く拒否されるようになりました。ご家族様に「お風呂に入りましょう」と声を掛けても、「昨日入ったばかりでしょ!」と怒り、話が進まない状況が続きます。
どのように声掛けしても取り合ってもらえず、地域包括支援センターに相談することになりました。そして、要介護1の認定を受け、近所の通所介護に通うことになります。
地域の知り合いが同じ通所介護に通っていたこともあり、すんなりと入浴を受け入れてくれました。時々軽い拒否はあるものの、現在も通所介護で入浴できています。
80代の男性で、ひとり暮らしをしている方のお話です。
もともと隣人との関係があまり良くなく、日常的に言い争いがある状況でした。そんな中で、次第に「物を盗られた」と思い込むようになってしまいます。
ある日、「家のスコップがなくなったのは隣人のせいだ」と思い込み、毎日のように抗議しに行くようになったのです。根拠のない訴えを繰り返すことで、隣人からも「なんとかしてほしい」と要望があり、地域でも問題視されるようになります。
ご家族様は遠方に住んでおられ、日常的な対応が難しく、金銭管理などにも不安がある状態でした。そのため、今後の生活や安全面も考慮し、近隣の老人ホームへの入居を検討・決定されました。
80代の女性で、家族と暮らしている方のお話です。
日中は落ち着いていることが多いのですが、深夜になると急に興奮し、「誰かが部屋にいる」「誰かが何かを取った」と強く訴えるようになりました。
ある晩、急に怒り出し、手近にあったティッシュ箱を投げてしまう出来事が起きます。家族は「日中とのあまりの違いに戸惑った」と話しておられ、どう対応すればいいか分からず困っておられました。
医師に相談し、薬の調整と生活リズムの見直しを行った結果、状態は徐々に安定しました。現在は、日中の通所介護とご家族様の見守りを併用しながら、在宅生活を継続されています。
80代の男性で、妻と二人暮らしをしていた方のお話です。
もともとは穏やかな方でしたが、年齢と共に「子どもが家に入ってきて遊んでいる」「妻が他の男と会っている」といった発言をするようになりました。
最初は軽い疑い程度でしたが、次第に思い込みが強まり、ある日ついに金づちを手に持って強く訴える場面があり、ご家族様も驚かれたそうです。
遠方に住む長女様は、地域包括支援センターに相談します。専門的な判断が必要とのことで、地元の精神科を受診し、医師からは「緊急性が高い」と判断されて即日入院となりました。
現在は、病院で薬物治療を受けながら、症状の安定を目指したケアが行われています。

怒りっぽくなっているご家族様にどう接すればよいのか、戸惑うことも多いでしょう。適切に対応することで、ご家族様の興奮を軽減できる可能性があります。
怒りっぽくなったご家族様に接する際に心がけたいこと |
|---|
|
怒っているご家族様に対して、「そんなことないよ」と否定したり説得したりすると、さらに強い興奮を招いてしまうことがあります。
まずは、ご家族様の言葉にしっかり耳を傾け、「そうなんだね」「嫌な気持ちになったんですね」などの共感の言葉を掛けましょう。話を最後まで聞き、介護者自身も落ち着いた表情や声で対応することで、相手の気持ちが少しずつ和らぐことがあります。共感の姿勢は、信頼関係を築く上で重要です。
認知症の方が話す内容が事実と異なるとき、介護者としては「それは違うよ」と訂正したくなるかもしれません。しかし、よかれと思って指摘したことが、ご家族様の自尊心を傷つけたり、怒りや混乱を招いたりするケースもあります。
特に、何度も同じことを尋ねられたり、事実と異なることを主張されたときほど、あえて正さずに受け流すのが有効です。気をそらしたり、別の話題に切り替えたりして、ご家族様の気持ちが落ち着くように工夫しましょう。
怒りの感情には、何らかの「きっかけ」が原因になっていることがよくあります。特に以下のような環境が影響していることも少なくありません。
日々の様子を観察し「どのような状況で怒りっぽくなるか」を把握することが大切です。
ご家族様が感情的になっているときは、無理に会話を続けず、そっとその場を離れましょう。興奮が激しい場合には、どれだけ丁寧に対応しても聞き入れられず、逆に状況を悪化させてしまうことがあります。
物理的に距離を取って、お互いがクールダウンする時間を確保しましょう。介護者自身の安全を守ることは最優先であり、冷静さを保つことにもなります。相手が興奮しているときに「いったん離れる」という選択肢は、決して間違いではないのです。
認知症の方との会話では、「難しい言葉」や「長い説明」はかえって混乱を招きます。話し掛けるときは、一文を短く区切り、優しい言葉でゆっくりと話すようにしましょう。
例えば「そろそろご飯にしましょう」「お風呂の時間ですよ」といった、短く具体的な表現が効果的です。また、表情やジェスチャーも交えて伝えることで、より伝わりやすくなります。ご家族様に合わせた声掛けによって、スムーズにコミュニケーションができるのです。
怒りや不安の感情を和らげる方法として、ご家族様の「好きなもの」の力を借りるのも効果的です。例えば、昔から好きな音楽を流したり、好物のお菓子や飲み物をそっと差し出したりすることで、気分が落ち着くケースがあります。
慣れ親しんだ音楽や味には、気持ちを落ち着かせる効果が期待できます。実際に、介護の現場でも取り入れていることも多いです。こうした「気分転換」は、ご家族様の気持ちを落ち着かせるだけでなく、介護者にもホッとできる時間をもたらしてくれます。
認知症の介護は長期化することが多く、気づかないうちに、心身に大きな負担が積み重なっていきます。特に、介護と仕事を両立している場合、時間や体力、気力の限界を感じることも少なくないでしょう。
真面目で責任感の強い方ほど「自分が頑張らなくては」と思い詰めてしまいがちですが、無理は禁物です。「誰かに話す」だけでも気持ちは軽くなります。ケアマネージャーや地域包括支援センター、親しい友人、「マイナビあなたの介護」など、相談できる環境をつくっておくと、少しずつ気持ちに余裕が生まれてきます。
「最近、怒りっぽくなった気がする」「物忘れが急に増えた」など、ご家族様の異変を感じたら、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。認知症は、早期発見・早期対応が重要とされています。早期に病院受診を行うことで、症状の進行を緩やかにしたり、ご家族様や介護者の負担を軽減できる可能性があります。
まずは、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談してみましょう。「大げさかもしれない」と遠慮せず、不安に思った段階で、すぐに行動することが認知症予防につながります。
介護の負担が大きくなってきたと感じたときは、無理をせず介護サービスの活用を検討しましょう。例えば、通所介護を利用することで、ご家族様にとっては外出や他者との交流が良い刺激になり、介護者もひと息つける時間を持てます。
また、状況に応じてショートステイや施設入所を選ぶことも有効な選択肢です。24時間365日体制で支援を受けられる環境の中で、「ここにいると安心できる」と感じる方もいらっしゃいます。
こうした介護サービスを取り入れることで、心に少しずつゆとりが生まれ、ご家族様も介護者も、より穏やかな毎日を過ごせるようになるでしょう。


怒りっぽくなったご家族様の言動に、不安や戸惑いを感じるのは自然なことです。
それは認知症の初期に見られる症状の一つであり、ご家族様の中で起きている混乱や不安が表に出ている状態かもしれません。
この記事のポイントは、以下のとおりです。
介護は、ひとりで抱え込むものではありません。怒りっぽくなったご家族様への対応に悩んだり、つい自分を責めそうになるときこそ、誰かに相談することが大切です。
「マイナビあなたの介護」では、介護に詳しい専門家が、電話やLINEで無料相談を受け付けています。「ちょっと話を聞いてほしい」「対応方法のアドバイスがほしい」など、介護に関することなら、どんな内容でも構いません。
ひとりで悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家が、あなたの「どうしよう」に寄り添い、解決のお手伝いをいたします。
参考URL
政府広報オンライン|「知っておきたい認知症の基本」
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所|認知症とは
相模原市 認知症疾患医療センター|「怒りたくなるのには理由がある」

介護支援専門員(ケアマネージャー)
朝水 裕一
介護支援専門員(ケアマネージャー)
朝水 裕一
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
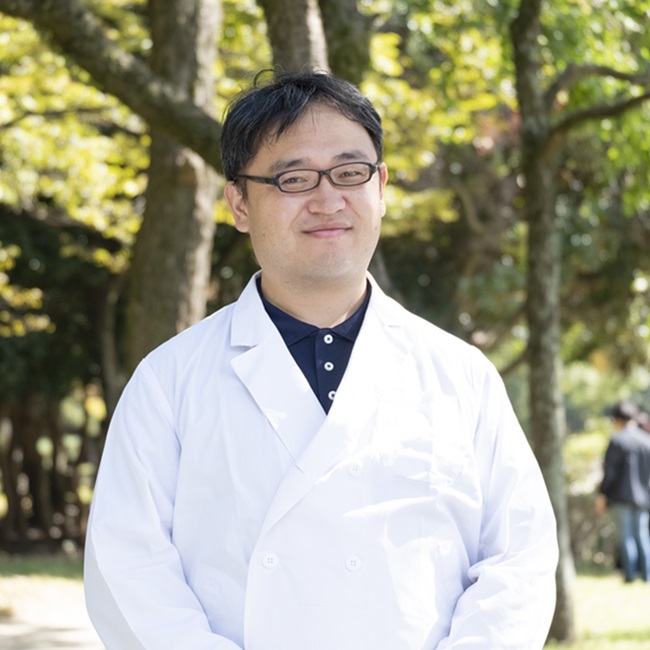
たがしゅうオンラインクリニック 院長
田頭 秀悟
たがしゅうオンラインクリニック 院長
田頭 秀悟
患者に医療の主導権を持ってもらう「主体的医療」を推進するオンライン診療医。
患者に医療の主導権を持ってもらう「主体的医療」を推進するオンライン診療医。

第5回 「親の介護が限界」と感じたときは?介護疲れへの対処法を紹介
ビジネスパーソンと介護

第4回 これで安心!介護生活で「見守りカメラ」を活用するための視点
ビジネスパーソンと介護

第3回 介護のストレスを感じたら。リフレッシュの方法や時間確保のポイントを紹介
ビジネスパーソンと介護
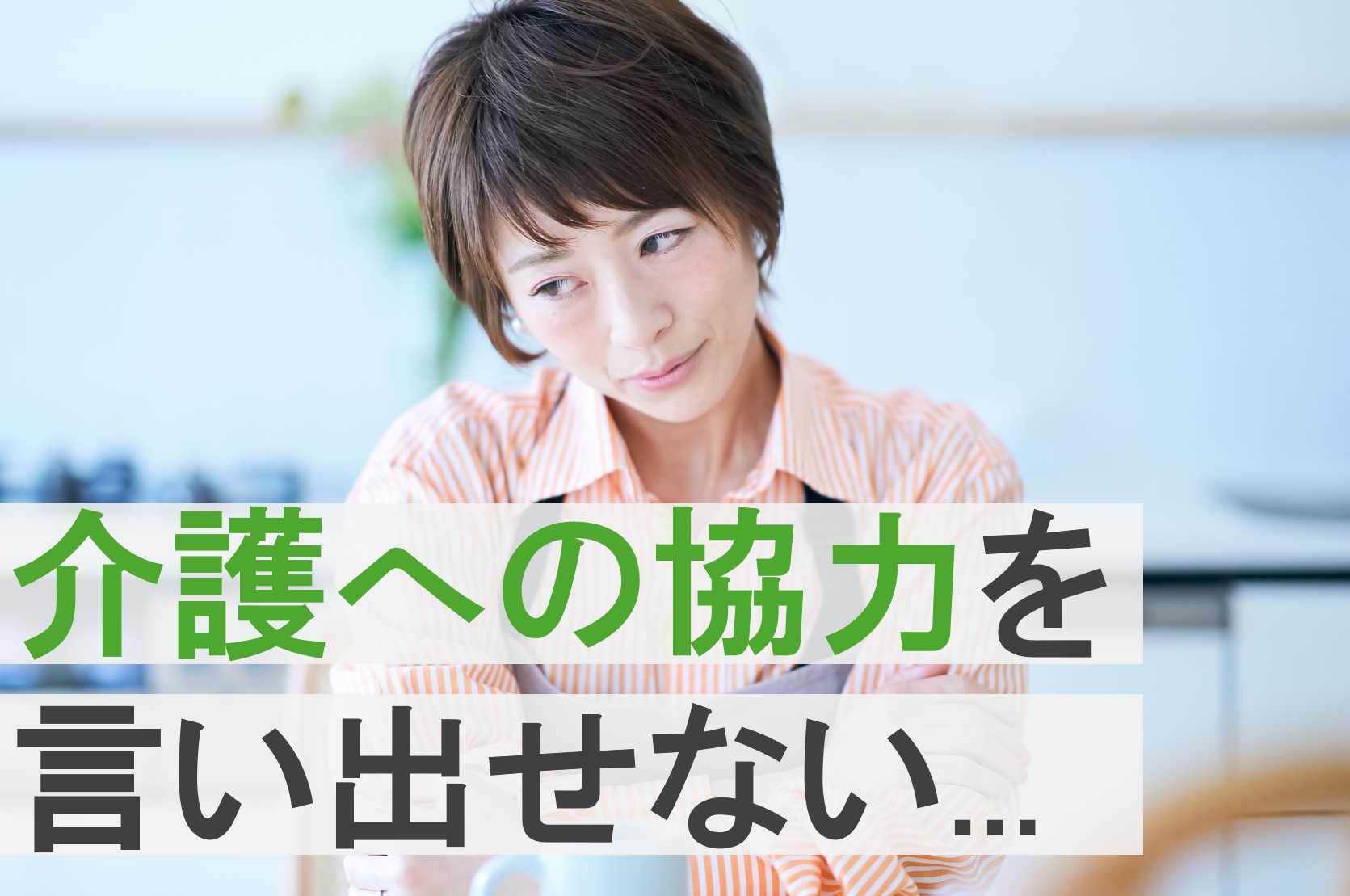
第2回 親の介護を「私ばかり」と悩む方へ…家族と上手に分担するコツ
ビジネスパーソンと介護

第1回 ビジネスケアラーが仕事と介護の両立で知っておくべきマインドセット
ビジネスパーソンと介護
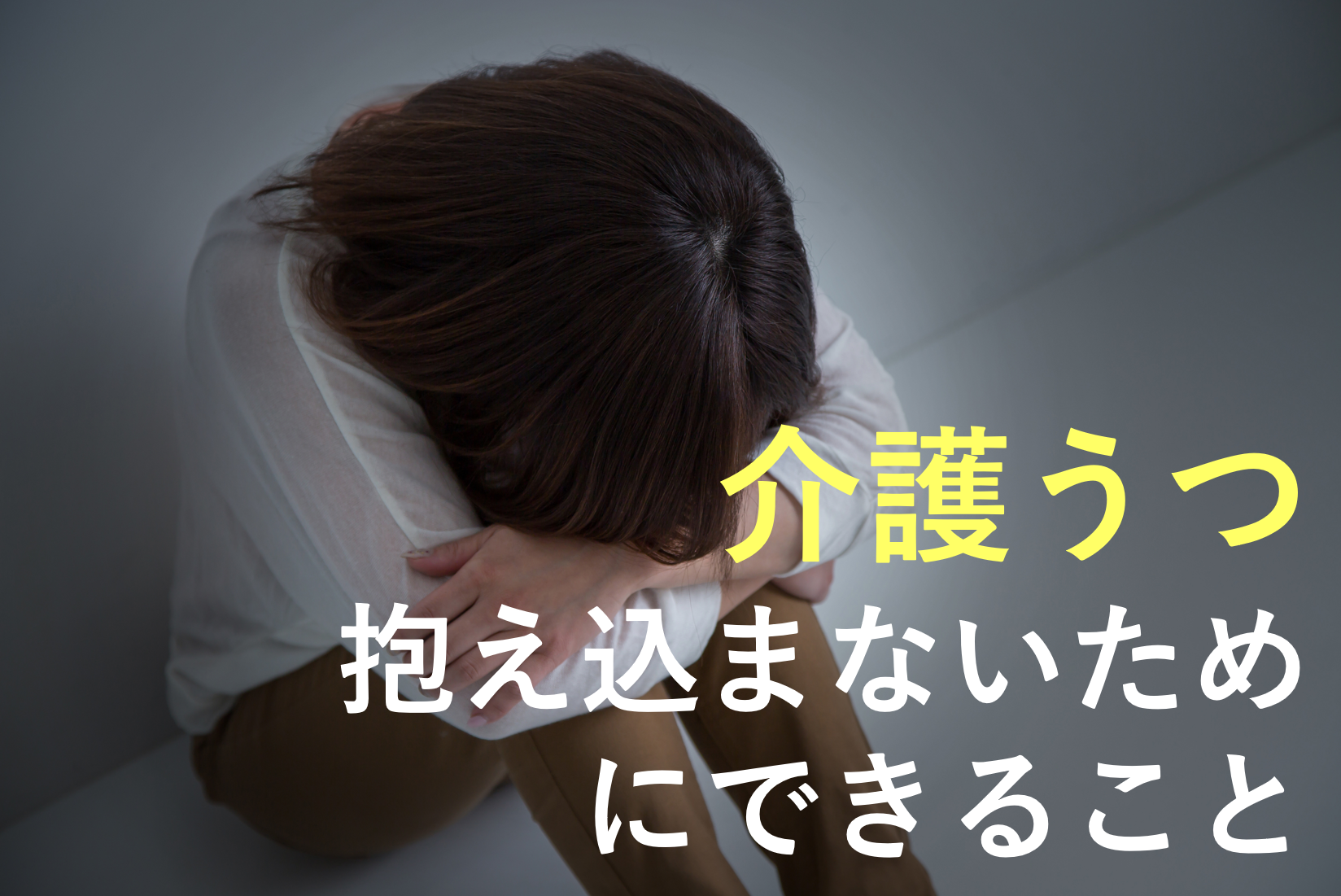
第7回 「介護うつかも?」と感じたら…あなたの心が軽くするための対処法や相談先
ビジネスパーソンと介護