介護において、生活の質(QOL)を維持・向上させることは非常に重要だと言われています。
そのために重要な概念である日常生活動作(ADL)と手段的日常生活動作(IADL)について、ポイントを分かりやすく解説します。自分や家族の生活状況を振り返り、幸福で健康的な人生について考えるきっかけにしてみませんか。
健康と生活を維持する
記事をシェアする
介護において、生活の質(QOL)を維持・向上させることは非常に重要だと言われています。
そのために重要な概念である日常生活動作(ADL)と手段的日常生活動作(IADL)について、ポイントを分かりやすく解説します。自分や家族の生活状況を振り返り、幸福で健康的な人生について考えるきっかけにしてみませんか。

「人生100年時代」という言葉を耳にしたことがあると思います。一昔前は「100歳=驚くほどの長寿」というイメージがありましたが、医療技術の進歩などによって、多くの人が100歳まで生きられる時代が現実のものになりつつあります。
そうした中で注目されるのが、生活の質(以下、QOL)という言葉です。QOLは「Quality Of Life」の略称で、人生や生活の充実感を意味します。
医療や介護の現場では「一人ひとりが無理なくその人らしい生活を送ること」などと解釈されます。ただ長く生きればいいと考えるのではなく、より充実した自分らしい人生を送るという考え方が、今の時代には重要です。
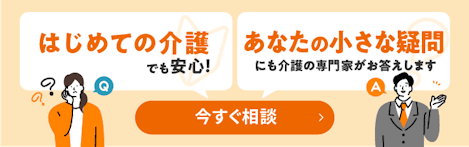

QOLを低下させないためにはどうしたらいいのでしょうか。QOLはさまざまな要素に影響を受けて上下しますが、その一つが日常生活動作(以下、ADL)です。ADLは「Activities of Daily Living」の略称で、食事、排泄、入浴、移動など日常生活を送るために必要な基本の動作のことです。医療や介護の専門家は、このADLを評価することで適切なケアにつなげています。
ADLが低下すると活動性が低下し、社会とのつながりも希薄になる傾向があります。役割や生きがいを失うことで精神的に落ち込みやすくなったり、家に閉じこもったりすることで、さらに体の機能が低下していくことも……。
このように、ADLはQOLに大きな影響を与えるのです。家族など身近な人について、「歩く速度が前より遅い」「体の一部をかばっているような気がする」などの違和感に早めに気付くことがとても大切です。

もう一つ、QOLのために知っておきたいのが、手段的日常生活動作(以下、IADL)です。IADLは「Instrumental Activities of Daily Living」の略称で、掃除、料理、洗濯、買い物、交通機関の利用、電話対応、服薬管理、金銭管理、趣味の活動など、応用的な日常生活動作を指します。ADLと比べると、IADLは記憶力や判断力も必要とされるより複雑な動作だと言えるでしょう。
IADLの中で「できない動作」が出てくると、これまで通りの日常生活が送れなくなり、QOLの低下に直結してしまう可能性があります。また、IADL の低下は、ADLの低下が起こる「前兆」であるケースも少なくありません。自分や家族のQOLを保つためには、IADLの変化にも目を向けておくことが大切なのです。
それでは、どのようにIADLをチェックすればいいのでしょうか。評価方法はいくつもありますが、専門家でない人にも分かりやすいものの一つとして、「Lawton(ロートン)の尺度」を紹介しましょう。8つの項目について当てはまるレベルを1つずつ選び、それぞれ横に記載された点数を集計していきます。合計点が高いほど、自立度も高いことを意味します。
項目ごとの点数にも注目してみましょう。例えば、「(7)服薬の管理」で点数が低ければ、薬を間違えないようにケースを分ける、誰かにチェックしてもらうなどの対策を取ることができます。また、この点数は体調や気分などによって日々変わるものです。定期的にチェックして、「できること」「できなくなっていること」の変化を捉えることも大事です。
項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
(1)電話を使用する能力 | 自分で番号を調べて電話をかけることができる | 1 |
よく知っている番号であればかけることができる | 1 | |
電話には出られるが自分からかけることはできない | 1 | |
まったく電話を使用できない | 0 | |
(2)買い物 | すべての買い物を自分で行うことができる | 1 |
少額の買い物は自分で行うことができる | 0 | |
誰かが一緒でないと買い物ができない | 0 | |
まったく買い物はできない | 0 | |
(3)食事の支度 | 自分で考えてきちんと食事の支度をすることができる | 1 |
材料が用意されれば適切な食事の支度をすることができる | 0 | |
支度された食事を温めることはできる、またはきちんとした食事は作れない | 0 | |
食事の支度をしてもらう必要がある | 0 | |
(4)家事 | 力仕事以外の家事をひとりでこなすことができる | 1 |
皿洗いやベッドの支度などの簡単な家事はできる | 1 | |
簡単な家事はできるが、清潔さを保てない | 1 | |
すべての家事に手助けが必要 | 1 | |
まったく家事はできない | 0 | |
(5)洗濯 | 自分の洗濯をすべて自分で行うことができる | 1 |
靴下などの小物の洗濯を行うことができる | 1 | |
洗濯は他の人にしてもらう必要がある | 0 | |
(6)交通手段 | ひとりで公共交通機関、自家用車で外出可能 | 1 |
ひとりでタクシーは利用できるが他は不可 | 1 | |
付き添いがあれば公共交通機関で外出可能 | 1 | |
付き添いがあればタクシーや自家用車で外出可能 | 0 | |
まったく外出できない | 0 | |
(7)服薬の管理 | 正しい時に正しい量の薬を自分で飲める | 1 |
仕分けされていれば自分で飲める | 0 | |
自分で薬を管理できない | 0 | |
(8)金銭管理能力 | 家計の管理(支払い・銀行利用等)を自分でできる | 1 |
日々の支払いはできるが大きな取引は手助けが必要 | 1 | |
金銭の取扱いを行うことができない | 0 |
出典:公益財団法人長寿科学振興財団「手段的日常生活活動(IADL)尺度」

ADLやIADLをできるだけ低下させないために、日常的にできるのはどのようなことでしょうか。具体的なポイントを3つ、解説します。
玄関、廊下、トイレ、キッチン、浴室、寝室などの「場所」と「動作」をセットで確認して、サポートが必要な部分を見つけてみましょう。
例えば、「一人で歩けるが段差にはつまずきやすい」という課題を発見したら、昇降を補助する手すりやスロープを導入することで自立を助けることができます。また、外出時に使う杖や、買い物に便利なシルバーカーなどをそろえることで、出かける意欲が回復することもあります。
介護保険制度を活用すれば、こうした福祉用具を1~3割の自己負担で借りたり、買ったりすることができます(所得や介護度などによって条件は異なります)。
福祉用具にはさまざまな種類があるので、展示会をチェックしたり、福祉用具専門相談員やケアマネージャーに相談したりして、生活に合ったものを見つけていきましょう。
身なりを整えて外出したり他者と交流したりすることで生活にハリが生まれ、活動量が増えることなどにより、心身ともに健康な状態を保つことにつながります。必ずしも特別な場所に出かける必要はなく、スーパーマーケットで買い物をするといった、身近な「社会とのつながり」を保つことが重要です。
できるだけ家に閉じこもらずに、外の世界から刺激を受けられるようにしましょう。趣味の仲間をつくったり、家族や友人と定期的に会って会話を楽しんだりすることも大切です。人とのコミュニケーションは、認知機能の低下を予防すると言われています。また、地域のボランティア活動などに参加することもおすすめ。「人の役に立つ」という経験から得られる充実感は、とても大きなものです。
家族が高齢になり、できないことが増えていくと「つい何でもやってあげてしまう」という人が多いのではないでしょうか。しかし、よかれと思って手を貸し過ぎてしまうと、本人の自尊心を深く傷つけることもあります。身体機能を維持するためにも、手伝いが過剰にならないよう注意しましょう。
例えば、移動に時間がかかるからといった理由でまだ歩けるのに車いすを使えば、どんどん筋力が衰えてしまいます。移動しやすい環境を整えるなど工夫し、「自分でできる」という達成感を積み重ねることがADLやIADLの維持、ひいてはQOLの向上につながります。どうしても難しいことを手伝う時にも、「一緒にやってみよう」「この部分は頼んでも大丈夫?」などと声をかけながら、本人の自主性や意思を尊重する姿勢が大切です。

QOLを維持・向上させるためには、日頃からADLやIADLに目を向けることが重要だと説明してきました。一方で、できない部分が出てきても、適切なサポートを受けることでQOLを改善することは可能です。
「自宅で生活できているけれど、引きこもりがちで運動不足」「ひとり暮らしで不安なので、誰かに見守ってほしい」など、日常生活に少しでも不安を感じる場合には、介護サービスの利用を検討してみるのはいかがでしょうか。
介護サービスの選択に迷ったときは、「マイナビあなたの介護」を活用して、LINEや電話で気軽に相談することができます。施設探し、介護準備のサポート、資料請求・見学申込の代行など、さまざまな支援を行っています。
お困りごとがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。