認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の症状がある方の自立度を5つのランクに位置づけて表したものです。
本記事では認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準や面談時のポイントなどを紹介します。施設入居までの流れも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
健康と生活を維持する
記事をシェアする
認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の症状がある方の自立度を5つのランクに位置づけて表したものです。
本記事では認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準や面談時のポイントなどを紹介します。施設入居までの流れも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
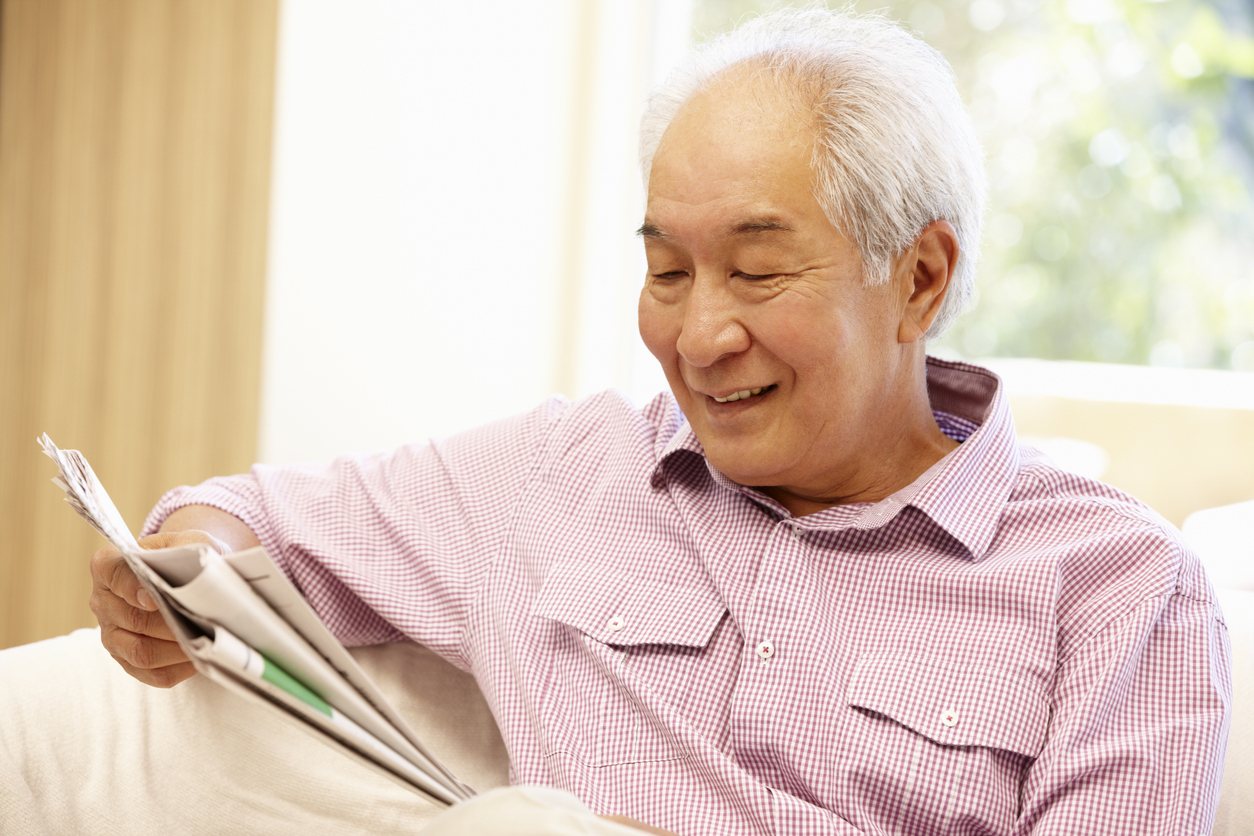

認知症高齢者の日常生活自立度とは、認知症の症状の程度を考慮し、日々の暮らしを送るうえでの自立度を5つのランクに分けて評価したものです。
この評価は、要介護認定を受ける際の判断基準の1つとしても活用されます。
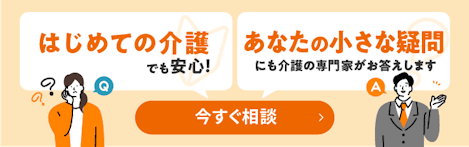

認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準は、「生活に影響が出る行為・症状、コミュニケーションが難しいことがあるかどうか」といった観点から、以下のⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Mの5つのランクに分けられます。
ランク | 判定基準 |
|---|---|
Ⅰ | ほとんどない |
Ⅱ | 少しある |
Ⅲ | ときどきある |
Ⅳ | 頻繁にある |
M | (妄想やせん妄、興奮などの精神症状や、自傷行為や他傷行為など精神症状を起因とする認知症の問題行動が)継続してある |
それぞれのランクについて、詳しく説明します。
「ランクⅠ」は、認知症の症状は見受けられるものの、そうした状態が「ほとんどない」と判断され、家の中での暮らしや社会生活において概ね自立している状態です。日々の暮らしでほとんど困ることはなく、1人暮らしもできる状態にあります。
このランクでは、認知症の症状の進行を予防したり、症状を改善したりするようなサポートを行うことが求められます。
「ランクⅡ」は、日々の暮らしを送るなかで、生活に影響がある行為や症状が見受けられる、コミュニケーションが難しいなどが「少しある」状態を指します。そのため、1人暮らしをするには少々不安があるものの、家族や同居人などが注意していれば在宅で自立した生活を継続することが可能な状態です。
また、ランクⅡには、「ランクⅡa」と「ランクⅡb」があります。 aが「家の外」でランクⅡの症状が見られる場合、bが「家の中」でランクⅡの症状が見られる場合に判定されます。
例えば、スーパーで適切な買い物ができなくなる、屋外で道に迷うことが多くなるなどといった症状がある場合は、「ランクⅡa」となります。
対して、家の中でも金銭管理や服薬管理ができなくなる、電話対応・訪問者の対応が難しくなるなど、1人で家にいることが困難になった場合には「ランクⅡb」と判定されることが一般的です。
「ランクⅢ」は、日々の暮らしを送るなかで、生活に影響が出る行為や症状が見受けられたり、コミュニケーションが難しかったりすることが「ときどきある」状態です。
以下は、ランクⅢの症状の一例です。
また、昼間と夜中でランクが分けられており、特に、昼間に多く症状がある場合は「ランクⅢa」、夜に多く症状がある場合は「ランクⅢb」になります。
夜間帯の方が対応する介護者の負担が大きいため、どちらの状態にあるのか把握しやすいようにランクが沸けられています。
「ランクⅣ」は、日々の暮らしを送るなかで、生活に影響が出る行為や症状が見受けられる、コミュニケーションが難しいなど、ランクⅢで見られる症状が「頻繁にある」状態です。そのため、常に見守りやサポートが必要です。
家族や同居人、周囲の協力やサポートがあれば、在宅サービスを利用しながら在宅での暮らしを継続できる状態です。しかし、本人をサポートする環境を整えるのが難しい場合は、特別養護老人ホームやグループホームなどの施設入居を検討する必要があります。
「ランクM」は、妄想やせん妄、興奮などの精神症状や、自傷行為や他傷行為など精神症状を起因とする認知症の問題行動とされる行為や症状が「継続してある」状態です。在宅での介護を継続することが難しく、医師の診断のもと、薬物療法や非薬物療法により、認知症の症状や認知症起因の行動を治療する専門医療が必要な状態です。

「認知症高齢者の日常生活自立度」の判定を受ける際は、市区町村から派遣される認定調査員が、自宅や入居している施設に来て、本人や家族への面談を行います。
面談の際には普段の状態をできるだけ正確に調査員に伝え、実態に近い判定を受けることが重要です。面談時には、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
面談の際は、ただ聞かれたことだけを答えるようにしないようにしましょう。「聞かれなかったから」といって、伝え忘れがあると正確な日常生活自立度や介護度が認定できなくなる可能性があります。調査項目に含まれていない症状もあるため、次のような認知症の症状がみられる場合は、調査員にしっかりと伝えましょう。
上記以外にも、気になる症状があれば、伝えることが大切です。
認定調査員による聞き取り調査の際には、家族も同席するのが基本です。面談時には、家族に対しても普段の様子や困っていること、認知症の症状の様子などが質問されます。
ただし、調査員が本人に質問している際は、本人の言葉で本人の想いや困っていることを知りたいため、家族は割って入らず、静かに見守ることが大切です。
認知症の症状で、奇声を発する、被害妄想が強いなど対応に困っている症状がみられる場合は、漏れなく調査員に伝えましょう。認知症高齢者の日常生活自立度判定をする際には、家族や周囲の方がどれくらい大変な思いをしているかも重要な聞き取り事項となります。そのため、具体的な話を伝えることが大切です。
家族だけの視点の情報だけでは、偏った情報となることもあるため、第三者の視点からも情報を得ておくことも重要です。デイサービス(通所介護)や訪問介護など利用している介護サービスがある場合、面談前に普段の様子や状態などの話を職員から聞いておくと良いでしょう。
例えば、自宅では強い入浴拒否があり入浴をしたがらないが、デイサービスでは進んで入浴するなど、自宅ではやれないことが、家族の目がないところでは行えることもあります。このように、家族と一緒にいるときとそうでないときで自立度が異なる場合、判定の内容に相違が出てくる可能性があります。
そのため、正確な自立度判定を受けるために、第三者からの情報も調査員に伝えることが必要です。
調査員に情報を正しく伝えるために、面談の1ヶ月ほど前からの様子を記録しておくことが望ましいでしょう。普段、妄想やせん妄がみられたり、異食があったりするケースでも、面談時にはスラスラと受け答えできることもあります。
そのため、普段の認知症の症状や本人の状態を正確に伝えられるよう、日付や行動をノートやメモに漏れなくまとめておきましょう。ボイスレコーダーや動画などを使用して記録しておくのもおすすめです。

認知症高齢者の日常生活自立度判定を受け、要介護認定を受けた高齢者は以下のような介護施設に入居可能です。
しかし、なかには認知症の症状や精神状態などにより本人が施設入居を嫌がる場合もあります。
そのような場合の対処法を「介護施設に入りたがらない親を説得するには?ポイントと事例を紹介」 の記事内で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉移設)では、日常生活を送るうえで必要な介護や機能訓練、療養上の世話などが受けられます。
日常的に介護を必要とする要介護3以上の方が入居可能で、認知症高齢者の日常生活自立度でみるとランクⅢの方を占める割合が多いです。
入居対象の目安は、更衣が1人で行えず時間がかかる、食事や排泄の行為をどうやったらいいかわからないなど、日常生活を送るうえで介護が必要な状態にあることです。在宅生活において火の不始末があることも、入居を検討する目安の1つです。
認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、家庭的な環境と地域との交流が図れる環境のもと、認知症の高齢者が共同生活を送れる施設です。日常生活を送るうえで必要な介護や機能訓練を受けられ、自立した生活を目指せるよう支援されます。
要支援2または要介護1以上の方が利用可能です。日常生活自立度でみると、日常生活を送るなかで、生活に若干支障をきたす症状があるランクⅡ以上の方が目安になります。しかし、奇声や大声をあげる、他傷行為があるなど他者に迷惑となる認知症の症状が著しく見られる場合は、共同生活に支障をきたすため入居できないケースもあります。
また、施設の職員体制や、すでに入居している方の状況などによっても異なるため、入居を希望する際は相談が必要です。
有料老人ホームは、安定した生活が行えるよう日常生活を送るうえで必要な介護やサポートが受けられる施設です。
有料老人ホームでは、ランクⅡ程度の方が目安で、外部の介護サービスを利用しながら生活を継続することが可能でしょう。
有料老人ホームには次の3種類があります。
種類 | 内容 |
|---|---|
介護付有料老人ホーム | 介護等のサービスが付いた高齢者向けの施設。介護が必要になった場合、ホームが提供する「特定施設入居者生活介護」を利用しながら施設での暮らしを継続可能。 |
住宅型有料老人ホーム | 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの施設。介護が必要になった場合、訪問介護やデイサービス(通所介護)などのサービス利用をしながら施設での暮らしを継続可能。 |
健康型有料老人ホーム | 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。 |
健康型有料老人ホームは介護が必要になった場合、退所する必要があるため、認知症のある高齢者には適していないといえます。
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が安全に暮らせるような居住環境が整えられており、医療や福祉の職員による安否確認・生活相談などのサービスが受けられます。職員による見守りがあるため、認知症高齢者の日常生活自立度はランクⅠ~Ⅱ程度の在宅生活が可能な方に向いている施設です。
施設によっては、認知症のある高齢者本人だけでなく、夫婦で入居可能な場合もありますが、詳しい入居の条件は施設ごとに異なるため、確認が必要です。

認知症高齢者の日常生活自立度は認知症の症状の進行度合いによって、5段階のランクに分けられます。認知症高齢者の日常生活自立度がランク付けされることで、要介護認定を受ける際の重要な指標ともなります。
そのため、面談時は普段の状態をできるだけ正確に調査員に伝え、実態に近い判定を受けることが肝心です。
そして、認知症高齢者の日常生活自立度や介護度などを考慮し、本人の心身状態に合わせて在宅介護サービスの利用や施設入居を検討しましょう。本人や家族が安心して暮らしを継続していけるよう、環境を整えることが大切です。
マイナビあなたの介護では介護に関するお悩みをLINEや電話で相談することができます。最適な施設探しから介護準備のお手続きのサポートなど幅広く対応します。
どんな些細なお悩みでも、まずはご相談してみるのはいかがでしょうか。
参考URL
認知症高齢者の日常生活自立度|厚生労働省
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)|厚生労働省
認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)|厚生労働省
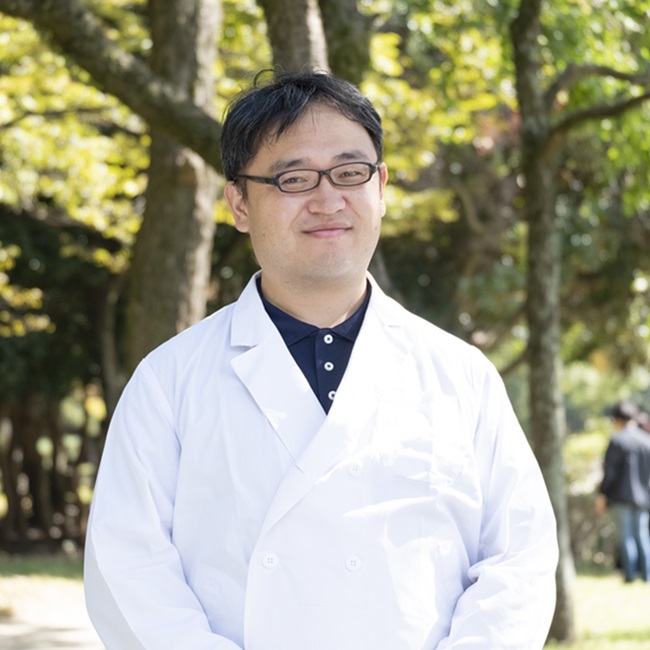
たがしゅうオンラインクリニック 院長
田頭 秀悟
たがしゅうオンラインクリニック 院長
田頭 秀悟
患者に医療の主導権を持ってもらう「主体的医療」を推進するオンライン診療医。
患者に医療の主導権を持ってもらう「主体的医療」を推進するオンライン診療医。