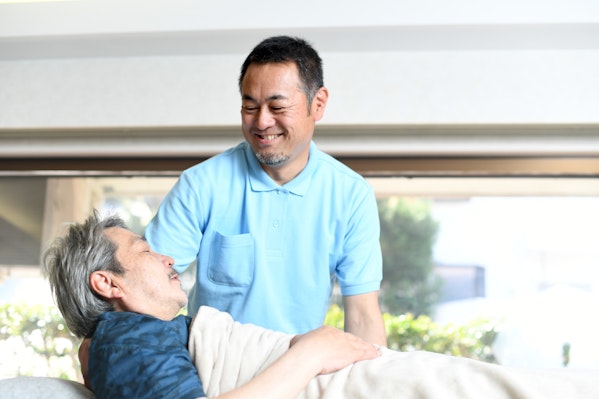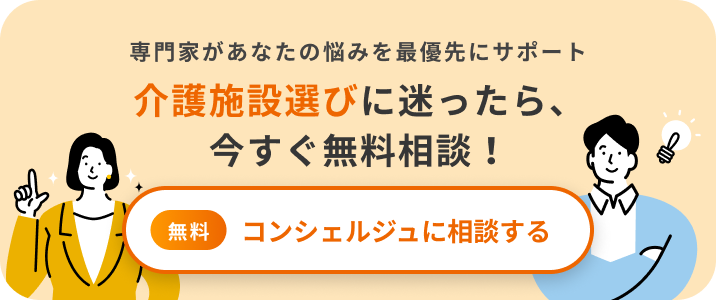在宅介護での基本的な介助と時短テクニック
在宅介護では、日常生活のさまざまな場面で、ご家族様へのサポートが必要です。
ここでは、介護者の方が少しでも負担を減らし、効率的に介護を行えるよう、各場面における基本的な介助方法と、時短テクニックについてご紹介します。
① 移乗の介助
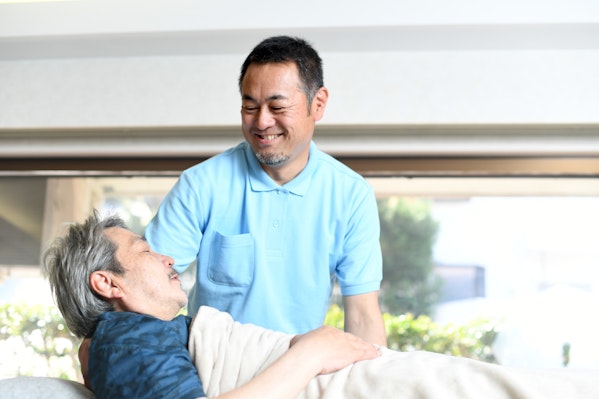
移乗の介助とは、ベッドから車いすへ、または車いすからトイレへなど、移動をサポートする際に必要となる介護技術です。
安全かつスムーズな移乗は、ご家族様の負担を軽減するだけでなく、介護をする方の腰痛予防にもつながります。
スムーズに移乗するためのボディメカニクス
移乗介助をスムーズに行うためには、ボディメカニクスの知識が欠かせません。
ボディメカニクスとは、人間の身体の構造や動きを理解し、効率的かつ安全に動作を行うための原則です。
まずは、以下の5つを意識して介助を行いましょう。
- 重心を低く保つ
身体の重心を低くすることで、安定性が増し、少ない力で身体を支えられます。
- 足を肩幅程度に開き、安定した姿勢をとる
足を肩幅程度に開き、しっかりと床を踏みしめることで、身体のバランスを保ちやすくなります。
- 身体を近づける
ご家族様の身体をできるだけ介護者の身体に近づけることで、少ない力で持ち上げることが可能になります。
- 大きな筋肉を使う
持っている力を十分に発揮するためには、手先や腕の力に頼らず、腹筋や背筋などの体幹部をはじめ、お尻の筋肉である大臀筋(だいでんきん)などの大きな筋肉を活用しましょう。
- 重心移動を活用する
動かす方向に足先を向けて重心移動を行い、ご家族様の身体を動かします。大きな筋肉を活用して、持ち上げずに水平に引くようにしましょう。
移乗介助を行う際には、「高い場所から低い場所へ移動させること」を意識しましょう。
例えば、ベッドから車いすへ移乗する際は、ベッドの高さを車いすよりも少し高く調整すると、介護者の負担が軽減できます。
移乗ボードやリフトの活用方法
移乗介助の負担を軽減するためには、移乗ボードとリフトの活用も有効です。ここでは、それぞれの活用方法を説明します。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
移乗ボード | 移乗ボードは、ベッドと車いすの間など、段差のある場所での移動をサポートする板状の福祉用具です。
使用する際は、ボードをしっかりと固定しましょう。
ご家族様の臀部を支え、ゆっくりと移動させることがポイントです。 |
リフト | リフトは、身体を持ち上げるための福祉用具です。主に浴槽をまたげない方や、体重が重く介護者が抱え上げることが困難な場合に利用します。 |
移乗介助で時短に役立つ福祉用具の紹介
移乗介助は、介護者の身体的な負担が大きくなりがちです。そこで、移乗介助の時短に役立ち、より安全に行うための福祉用具をご紹介します。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
スライディングシート | スライディングシートは、摩擦を軽減し、少ない力で身体を移動できるシートです。
ベッド上での体位変換などに使用します。 |
回転盤(ターンテーブル) | 回転盤は、立ったまま、もしくは座ったままの状態で身体の向きを変えられる用具です。 |
昇降座椅子 | 昇降座椅子は、座面が電動で上下する機能を持つ椅子です。
座ったり立ち上がったりする際の動作を補助するために設計されています。 |
② 食事の介助

食事の介助は、ご家族様の状態に合わせた工夫が必要です。
ここでは、食べやすい食器や調理法の工夫、時短テクニックについて解説します。
食べやすい食器や調理法の工夫
食事の介助において、食べやすい食器や調理法の工夫は、食欲不振の改善や誤嚥(ごえん)予防につながります。
具体的には、以下の点に注意すると良いでしょう。
- 食器の工夫
持ちやすい取っ手がついた食器や、滑り止め加工がされた食器を使用すると、安定性が増し、食べやすくなります。
- 調理法の工夫
食材をやわらかく煮込んだり、細かく刻んだりすることで、噛む力や飲み込む力が弱くなった方でも食べやすくなります。また、とろみをつけることで、誤嚥を防ぐ効果も期待できます。
食事は毎日の生活の楽しみの一つです。ご家族様の状況に合わせて、食べやすい食事に工夫しましょう。
ご家族様の自立を促すサポートの仕方
食事介助は、できる限りご家族様の自立を促すことが大切です。介助しすぎると、ご本人が持っている能力を奪うことになってしまいます。
具体的には、以下の点に注意しましょう。
- 見守り
ご家族様がご自身で食べられる部分については見守りながら、ゆっくりと食事をしてもらうように促しましょう。
- 部分介助
食事の途中で疲れてしまった場合や、うまく食べられない場合に、必要な部分だけを介助するようにしましょう。
- 声かけ
食事のペースや、食べる量に合わせて、適切な声かけを行い、食事への意欲を引き出しましょう。
また、訪問介護を利用し、ヘルパーと一緒に調理をすることも、食事への意欲向上につながります。
食事介助で時短に役立つ福祉用具の紹介
以下のような用具を使うことで、食事介助の時間短縮や、介護者の負担軽減につながります。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
握りやすいスプーンやフォーク | グリップ部分が太く、握りやすい形状のスプーンやフォークは、握力が弱い方でも握りやすく、食事をサポートします。 |
食事用エプロン | 食事用エプロンは、食べこぼしによる衣類の汚れを防ぎます。
防水加工のものや、首元で簡単に装着できるものなど、さまざまな種類があります。 |
滑り止めマット | 食事中に食器が滑るのを防ぎます。
食器を安定させ、こぼしにくくなります。 |
③ 排泄の介助

排泄の介助は、介護の中でも特にデリケートな部分です。ここでは、トイレへの誘導をスムーズに行うコツや福祉用具、時短テクニックについて解説します。
トイレへの誘導をスムーズに行うコツ
トイレへのスムーズな誘導は、自尊心を尊重し、気持ちよく排泄してもらうために必要です。
以下の点に注意して、トイレへの誘導を行いましょう。
- 声かけ
起床後、食事の前後、就寝前など、排泄を行いそうなタイミングを見計らって、「トイレに行きましょうか?」と優しく声をかけます。
- 導線
トイレまでの道のりを安全に誘導します。障害物は取り除き、必要に応じて、手すりの設置や床の滑り止め対策なども検討しましょう。
- プライバシーへの配慮
例え家族であっても、排泄の介助は非常にデリケートなものです。ドアを閉めるなど、落ち着いて排泄できる環境を整えましょう。
- 時間
時間に余裕をもってトイレへ誘導しましょう。焦らせてしまうと、転倒につながる可能性があります。
これらの点に注意することで、ご家族様の負担を減らし、気持ちよく排泄してもらえます。
ポータブルトイレの活用
ポータブルトイレは、寝室などに設置できる簡易トイレです。歩行が困難な方や、夜間の移動が不安な方などの排泄をサポートします。
ポータブルトイレには、さまざまな種類があります。例えば、一見、普通の椅子のように見える家具調のものや、ボタンを押すと排泄物を自動で個包装してくれるラップ式のもの、排泄後に洗浄・乾燥してくれる自動洗浄機能付きのものなどです。ご家族様の状態や住環境、好みに合わせて選ぶことが可能です。
設置場所については、プライバシーに配慮しつつ、転倒リスクの少ない場所を選びましょう。ベッドの横や、部屋の一角に設置するのが一般的です。ポータブルトイレを上手に活用することで、転倒などの心配がなく、安心して排泄してもらえます。
排泄介助で時短に役立つ福祉用具の紹介
排泄介助は、介護の中でも特に時間と労力がかかる作業です。ここでは、排泄介助の時間短縮や、介護者の負担を軽減するのに役立つ福祉用具をご紹介します。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
尿器 | ベッド上や座位のまま排尿できる用具です。
移動が困難な方や、夜間の排泄時に便利です。
尿器には、男性用と女性用があります。 |
自動排泄処理装置 | 排泄物を自動的に吸引・処理する装置です。
ただし、身体の傾きが大きい方や、横向きで寝る方の場合、装置が対応できないことがありますので、事前に確認が必要です。 |
排泄予測デバイス | 排泄のタイミングを予測し、知らせてくれる装置です。
適切なタイミングでトイレ誘導ができます。 |
④ 入浴の介助

入浴の介助は、清潔を保つだけでなく、心身のリフレッシュにもつながる大切なケアです。ここでは、安全で効率的な入浴手順や有効な福祉用具について解説します。
安全で効率的な入浴手順
浴室内は滑りやすいため、入浴の介助には転倒などのリスクが伴います。ここでは、安全な入浴手順について解説します。
- 入浴前の準備
脱衣所や浴室の温度を調整し、タオルや着替えを用意しておきます。また、入浴中に体調が悪くなった場合に備えて、携帯電話などを近くに置いておきましょう。
- 声かけ
入浴前に「いい湯が沸いていますので、お風呂に入りましょうか?」と優しく声をかけ、入浴への意欲を高めましょう。
- 脱衣
プライバシーに配慮しながら行いましょう。ボタンが少ない衣服は、楽に着替えられます。
- 入浴
浴室では、滑りやすい場所や、段差に注意しながら、安全に移動します。シャワーの温度はぬるめに設定し、熱すぎないように注意しましょう。
- 洗身
高齢者の皮膚は弱く、乾燥しやすい特徴があります。ゴシゴシと強くこすらないように注意しましょう。
- 入浴後のケア
入浴後、タオルで優しく水分を拭き取り、保湿クリームなどで皮膚を保湿します。また、体調の変化に注意し、ゆっくりと休めるようにサポートしましょう。
これらの手順を守ることで、安全で入浴介助を行うことが可能です。
シャワーチェアや機械浴の活用
入浴介助の負担を軽減するために、シャワーチェアや機械浴といった福祉用具の活用も有効です。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
シャワーチェア | 座面が広く、高さの調節も可能で、安心して入浴できるように設計されています。 |
機械浴 | 機械浴は、ベッドで過ごすことが多い方や、身体を支えることが難しい方が、安全に入浴できる装置です。リフトで身体を吊り上げて入浴するものや、ストレッチャーに寝たままの状態で入浴できるタイプがあります。 |
これらの福祉用具を適切に活用することで、入浴介助の負担を軽減し、安全で快適に入浴できます。
入浴介助で時短に役立つ介護サービス・福祉用具の紹介
入浴介助をよりスムーズに行うために、時短に役立つ介護サービスや福祉用具の活用も検討しましょう。
福祉用具や介護サービス | 活用方法 |
|---|
訪問入浴介護 | 自宅に看護師や介護職の人が訪問し、入浴の介助を行ってくれるサービスです。
スタッフが体調確認や皮膚状態をチェックしてくれます。 |
手すりのレンタル・設置 | 脱衣場や浴室内に手すりを設置することで、転倒のリスクを減らせます。
手すりには、浴槽の縁に取り付けるタイプなどもあり、レンタルが可能です。 |
滑り止めマット | 浴室や浴槽内に滑り止めマットを敷くことで、転倒のリスクを減らせます。 |
これらのサービスや福祉用具を組み合わせることで、安全に入浴できる環境を整え、介護者の負担も軽減できます。
⑤ 更衣の介助

更衣の介助は、ご家族様の自尊心を尊重しながら、スムーズに行う必要があります。ここでは、着替えやすい服装の選び方と、効率的な着替えの仕方について解説します。
着替えやすい服装の選び方
着替えやすい服装は、ご家族様の負担を軽減するだけでなく、介護をする方の負担軽減にもつながります。以下の点に注意して、服装を選びましょう。
- ゆったりとしたデザイン
身体を締め付けない、ゆったりとしたデザインの服を選びましょう。
- 前開きタイプ
前開きタイプの服は、着脱がスムーズで、介助がしやすいです。
- 伸縮性のある素材
伸縮性のある素材の服は、身体を動かしやすく、着心地も良いです。
- 乾きやすい素材
洗濯後に乾燥しやすい素材を選ぶと、清潔に保てます。
着替えやすい服装を選ぶことで、ご家族様の自立を促し、介護をする方の負担も軽減できます。
効率的な着替えの仕方
着替えの仕方を工夫することで、介助時間を短縮し、ご家族様の負担を減らせます。
着替えを行う際は、以下の点に注意しましょう。
- 着脱しやすい順番
上着から着る、または脱ぐなど、着脱しやすい順番を意識しましょう。
- 無理のない姿勢
無理な姿勢での着替えは、身体に負担がかかります。介護を受ける方の体勢に合わせ、無理のない姿勢で着替えを行いましょう。
- 声かけ
着替えの際は、必ず声かけを行い、安心感を与えましょう。「腕を上げますね」など、これから行う動作を事前に伝えることで、スムーズな介助ができます。
- 確認
着替えが終わったら、衣服がしわになっていないか、体にフィットしているかを確認します。特に、しわになったまま横になると、床ずれになる可能性があるため、注意が必要です。
これらの点に注意することで、ご家族様の負担を軽減し、効率的に着替え介助を行えます。
⑥ 歩行介助

歩行介助は、ご家族様の状態に合わせて、安全に行う必要があります。ここでは、歩行器や杖の適切な使用方法、転倒防止のための注意点、歩行介助で時短に役立つ福祉用具について解説します。
歩行器や杖の適切な使用方法
歩行器や杖は、歩くのが大変な時に助けてくれる便利な道具です。ただし、ご家族様に合わないものを選んでしまったり、使い方を間違えたりすると、転倒などの事故につながる可能性があります。専門家と相談し、安全に使えるようにしましょう。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
歩行器 | 歩行器には、四脚型(ピックアップ型)や歩行車、シルバーカーなどさまざまな種類があります。 |
杖 | 杖には、T字杖、多点杖などがあり、ご家族様の状態に合わせて選びましょう。
杖先ゴムの摩耗には注意し、定期的に交換しましょう。 |
※福祉用具を選ぶ際には、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。また、理学療法士などの専門職による判断が必要なケースもあります。
転倒防止のための注意点
転倒は、骨折につながる危険性があります。転倒防止のために、以下の点に注意しましょう。
- 足元環境の整備
障害物や段差をなくします。滑りやすい床にはマットを敷くなど、転倒しにくい環境を整えましょう。
- 履物や服装の工夫
滑りにくい靴を履き、靴ひもがほどけていないか確認しましょう。ズボンの丈が長すぎると、転倒の原因となります。
- 無理のないペース
体調に合わせて、ゆっくりと歩きましょう。
- 声かけ
高齢の方は、焦って行動しがちです。歩行介助の際には、必ず声かけを行い、安心感を与えましょう。
歩行介助で時短に役立つ福祉用具の紹介
歩行介助をより効率的かつ安全に行うために、便利な福祉用具を活用しましょう。
福祉用具 | 活用方法 |
|---|
電動アシスト機能付き歩行器 | 歩行が不安定な方でも、上り坂ではアシスト、下り坂では自動減速してくれます。片流れも防止できる歩行器です。
手を離すと、自動的に止まってくれるものもあります。 |
転倒予防シューズ | 転倒予防シューズは、靴底に滑り止め加工がされており、転倒のリスクを軽減します。 |
※福祉用具を選ぶ際には、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。また、理学療法士などの専門職による判断が必要なケースもあります。
時短につながる!介護スキル向上のための心構え

介護は、どうしても長期にわたり、心身ともに大きな負担がかかってしまいがちです。ここでは、介護を少しでも楽にするための心構えや時短のコツについて解説していきます。
介護者自身の心身のケアを大事にする
介護を続けるためには、まず介護者自身が心身ともに健康であることが重要です。介護は、身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。自分のケアを後回しにせず、休息やリフレッシュの時間を意識的に作るようにしましょう。
例えば、短時間でも自分の趣味の時間を作る、十分な睡眠時間を確保する、バランスの良い食事を心がけるなどが大切です。また、ストレスを溜め込まないように、友人や家族に話を聞いてもらうのも良いでしょう。
介護スキルを向上させるために継続的に情報収集する
介護に関する知識やスキルを向上させることは、安全で効率的な介護を行う上で重要です。情報収集を行うためには、以下のような方法があります。
- 書籍やインターネット
介護に関する書籍や、信頼できる情報をインターネットで収集しましょう。例えば、「マイナビあなたの介護」などの情報サイトでは、在宅介護に役立つさまざまな情報を得られます。
- セミナーや研修
介護に関するセミナーや研修に参加することで、専門的な知識や技術を学べます。社会福祉協議会などが開催するものには、無料セミナーも多いです。
- 専門家への相談
主治医やケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。
継続的に情報収集を行い、介護スキルを向上させましょう。そうすることで、より質の高い介護を提供できるようになり、結果的にご自身の負担軽減にもつながります。
ひとりで抱え込み過ぎず、周りに協力してもらう
介護はひとりで抱え込むと、身体的にも精神的にも大きな負担となり、長続きしません。介護を継続するためには、家族や親族、介護サービスなど、周囲の協力を得ることが重要です。
まとめ
この記事では、在宅介護におけるさまざまな場面での介助方法や、介護を効率化するためのポイントについて解説しました。要点を以下にまとめます。
- 移乗介助:ボディメカニクスを活用し、福祉用具を使って安全かつスムーズに移乗をサポートしましょう。
- 食事介助:食べやすい食器や調理を工夫し、自立を促すサポートを心がけましょう。
- 排泄介助:プライバシーに配慮し、ポータブルトイレなども活用しましょう。
- 入浴介助:事前準備を行い、福祉用具や訪問入浴で安全な入浴をサポートしましょう。
- 更衣介助:着替えやすい服装を選び、スムーズな着替えを心がけましょう。
- 歩行介助:歩行器や杖を正しく使えるようにサポートし、転倒防止に注意しましょう。
- 介護スキル向上:ご自身のケア、情報収集、周囲の協力が大切です。
在宅介護で大切なのは「ひとりで悩みを抱え込みすぎないこと」です。身体的・精神的な負担が大きい場合は無理をせず、ケアマネージャーや地域包括支援センター、「マイナビあなたの介護」などの専門家に相談し、介護サービスや福祉用具の利用を検討しましょう。
「マイナビあなたの介護」なら電話やLINEでも相談ができるのでちょっとした相談でも気軽に相談しやすいでしょう。
どんな些細なお悩みでもまずはご相談してみてください。
介護の専門家へ相談する ▶ 会員登録はこちら ▶
著者・監修現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。