年齢を重ねると、「お口の環境」はどうしても悪化しがち。
しかし、口内に汚れがたまると、虫歯や歯周病が心配なことはもちろん、肺炎や感染症など全身の病気につながる可能性もあります。
毎日の口腔ケアでお口の中をきれいに保つ方法を知り、充実した生活を送りましょう。
健康と生活を維持する
記事をシェアする
年齢を重ねると、「お口の環境」はどうしても悪化しがち。
しかし、口内に汚れがたまると、虫歯や歯周病が心配なことはもちろん、肺炎や感染症など全身の病気につながる可能性もあります。
毎日の口腔ケアでお口の中をきれいに保つ方法を知り、充実した生活を送りましょう。

口腔ケアとは、虫歯や歯周病などの口腔疾患やトラブルを防ぐことで、体を健やかに保ったり、生活の質を高めたりすることを目的としたケアです。
歯や歯茎の汚れを落として口腔を清潔に保つだけでなく、唾液の分泌を促したり嚥下機能の低下を予防したりするリハビリなども含まれます。
効果を得るためには、毎日の積み重ねが大切。健康的な生活を送るために、できることから始めてみましょう。
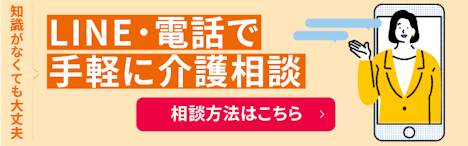

歯磨きやうがいなどが不十分だと、細菌の塊である歯垢がたまってしまいます。この状態を放置すると、歯や歯茎にトラブルが発生。
特に歯周病が進行すると、歯を支える骨が破壊され、大切な歯を失うこともあります。
高齢になると、唾液の分泌量が減ったり嚥下機能が低下したりして、口腔内の環境が悪化する傾向があるため、丁寧な口腔ケアが、より重要になります。
具体的に、どのようなメリットがあるか確認していきましょう。
大人の口腔内には数百種類の細菌が存在し、あまり歯を磨かない人では4,000~6,000億個もの細菌が棲み着いていると言われています。
しかし、よく歯を磨く人ではその数が大幅に減少し、深刻な虫歯や歯周病などのトラブルを回避することができます。
例えば、食事をした後には食べかすが口腔内に残りがち。特に、甘いものや炭水化物などに含まれる糖分は、虫歯菌の栄養源になります。食後はもちろん、甘いものを飲んだ後などにも歯磨きやうがいをする習慣があれば、細菌の繁殖を減らすことができます。
口腔内で増えた細菌は血管を通じて全身に広がり、他の臓器にも悪影響を及ぼす可能性があります。
特に、虫歯や歯周病によって口の中の血管が炎症を起こすと、細菌が血液中に入り込みやすくなります。細菌の広がりを妨げるためには、適切なタイミングでのケアが欠かせません。
就寝中は唾液の分泌量が減少し、細菌が増殖しやすくなるため、就寝前と起床後すぐに口腔ケアを行うことが効果的です。
誤嚥性肺炎※を防ぐ他、心疾患、脳梗塞、糖尿病、感染症など、さまざまな病気のリスクを減らすことができます。
※飲食物や唾液などが気管に入ることによって発症する肺炎
近年の研究で、認知機能と咀嚼力に深い関係があることや、歯周病菌が体内で炎症を引き起こし、それが脳の機能にも影響を与える可能性があることが分かってきました。
つまり、口腔内の健康を維持することは、認知機能の低下を防ぎ、生活の質を向上させることにもつながるのです。
また、誰かと一緒に食事や会話を楽しむことで、さらに生活の質は高まるもの。
口腔ケアをしっかり行えば、健康な歯で食事をおいしく味わえるだけでなく、口臭の不安を解消し、積極的に人と会話できるようになるでしょう。

それでは、毎日の口腔ケアは、どのように行えばよいのでしょうか。用意しておくと便利なケア用品、気になるケアの手順、口腔体操について紹介します。
お口の状態や好みに合ったものを選びましょう。毛先の軟らかいタイプなら、口腔内を傷つけづらい上に、歯の表面を優しく磨くことができます。口を大きく開けることができない場合には、ヘッドの部分が小さいタイプがお勧めです。
取っ手が付いているものが持ちやすくておすすめです。
口腔ケア用のスポンジ、コットン、口腔内を潤す保湿剤、歯間ブラシなどを必要に応じて用意しましょう。
入れ歯を使っている場合には、専用のブラシを活用するときれいに磨けます。
また、素手で口の中を触ることは衛生的に望ましくないため、介護者にとっては使い捨て手袋も必需品です。
(1)入れ歯を外す
入れ歯を使用している場合、そのまま口腔ケアをすると、口腔内を隅々まできれいにすることが難しく、介護者が手をけがする恐れもあります。
ケアに入る前に、必ず取り外しましょう。
(2)歯を磨く/入れ歯を洗う
うがいなどで口腔内を湿らせてから、歯ブラシを口の中に入れて、歯の表面や裏側を磨いていきます。この時に「右の奥歯から始める」「上の歯が終わったら下の歯へ」などと順番を決めておくと、磨き残しを防ぐことができます。
小さく細かく歯ブラシを動かし、過剰な力が入らないよう気を付けましょう。
また、歯と歯の間、歯と歯茎の間、奥歯の溝の部分などは、汚れが残りやすいため要注意。歯間ブラシやデンタルフロスを活用すると、歯垢をしっかりと除去できます。
入れ歯は、流水で汚れを洗い流した後に、専用のブラシで磨きます。一般的な歯磨き粉は、入れ歯を傷つける可能性があるため使用しないようにしましょう。
就寝前など、長時間入れ歯を外すタイミングで専用の洗浄液に浸けると、頑固な汚れも落とすことができます。
(3)口腔内の粘膜や舌の掃除
細菌の原因となる汚れは、口蓋や舌の表面などにも隠れています。
お口の状態によっては、口腔ケア用のスポンジやコットンを使って、頬の内側、歯茎、舌の表面などを優しくこすって拭き取りましょう。
スポンジやコットンは水で湿らせ、水気を絞ってから使います。急に奥まで入れると嘔吐や誤嚥※のリスクがあるため、手前の方からゆっくりと進めましょう。
舌の表面に付着する舌苔と呼ばれる汚れは、白や黄色っぽい色をしています。一度で完全に除去するのは難しいので、毎日少しずつ取り除くことが大切です。
※食べ物や飲み物などが気管に入ってしまうこと
(4)うがいをする
十分に汚れを取ることができたら、水で口をすすぎます。
一度に含む水の量が多過ぎると、誤って飲み込んでしまう恐れがあるため、少量の水で複数に分けるとよいでしょう。
(5)保湿剤を塗る
最後に口腔内を保湿します。指やスポンジブラシなどに保湿剤を取り、口腔内の粘膜や舌などに塗布します。
乾燥予防や唾液分泌などの効果が期待できるので、口呼吸になりがちな人や口の中が乾燥しやすい人には、特におすすめです。
保湿剤には、ジェル状、スプレー状、マウスリンスなど多様な種類があるので、使いやすいものを選びましょう。
唾液は、食べ物と混ざり合って飲み込みを助けたり、口腔内の細菌を洗い流して環境を維持したりするために重要な役割を持ちます。
口腔体操を行うことで唾液の分泌を促すことができるため、歯磨きと合わせて実践してみましょう。
やり方は簡単で、口の中で舌を上下左右に動かしたり、左右の頬を交互に膨らませたりするだけでOK。耳の下から上顎の奥歯の辺りを、円を描くように指でマッサージすることも効果的です。

介護における口腔ケアは、効率よく安全に、そして毎日継続することが肝心です。とは言え、最初から完璧なケアをすることは難しいもの。まずは、次の4つのポイントを押さえてトライしてみましょう。
口腔内を刺激し、水を使う口腔ケアは、一歩間違えると誤嚥を招く恐れがあります。介護する人とされる人、双方が注意を払って行うことが大事です。
「歯ブラシを入れるね」「少し水を口に含んで」などと、声をかけながら進めましょう。
また、なるべく椅子に座り、顎を引いた姿勢を取ってもらいましょう。
歯磨きやうがいなどの工程の中で、自力でできることがあれば、本人に任せることもポイント。自分の手を動かして歯ブラシを使うだけでも、機能訓練(リハビリ)につながるからです。
難しそうな部分があれば「大丈夫?」などと声をかけ、最低限のことを手伝うようにしましょう。
毎日のルーティンの中に、タイミングを決めて口腔ケアを組み込むことで、規則正しい生活リズムがつくられます。
「起床後」「食前と食後」「就寝前」といったように、ケアを行う時間帯を大まかに決めておけば、日常生活にメリハリが生まれるでしょう。
体調の変化などにより、どうしても気分が乗らない日もあるでしょう。そんな時には、無理強いしないことも大切です。
本人が口腔ケアにマイナスイメージを持つと、その後の継続が難しくなってしまいます。
本人にとって心身の負担が少ないことを優先し、マッサージや口腔体操などの時間を増やすことも一案です。

口腔ケアでは、いくつか注意点があります。
まずは、先に紹介したように、水や唾液などを誤嚥しないように気を配ること。
もしも、ケアをした後に声が枯れていたり、大きくむせたりする場合には、誤嚥の可能性があります。体調の変化がないかを、しばらく注意して観察しましょう。
口腔ケアには、口の中を清潔にすること以外にも、口腔内の状態をチェックする目的があります。
口内炎や発赤などがないかを見て、必要があれば医療機関を受診しましょう。ブラッシングの際には、異常がある部分に触らないように気を付けてください。
こうした口腔内のトラブルを避けるためにも、ケアに使用する道具の管理は欠かせません。
スポンジやコットンは一度使ったら捨てるなど、常に清潔なものを使用しましょう。

お口の中だけでなく、心身の健康にまで影響する口腔ケア。ポイントを押さえれば、誰でも自宅で取り組むことができます。
「もっと詳しいやり方を知りたい」「プロから習ってみたい」という人に向けて、歯科医師や歯科衛生士による研修会を開催している自治体もあるので、興味があれば調べてみましょう。
口腔ケア以外にも、在宅での介護には悩みや疑問が付きもの。もし、不安を感じることがあれば、「マイナビあなたの介護」を活用してみませんか。迷いが生じがちな介護サービスの選択、施設探し、介護準備のサポート、資料請求&見学申込の代行など、幅広い支援を行っています。
LINEや電話を使って、どうぞお気軽にご相談ください。