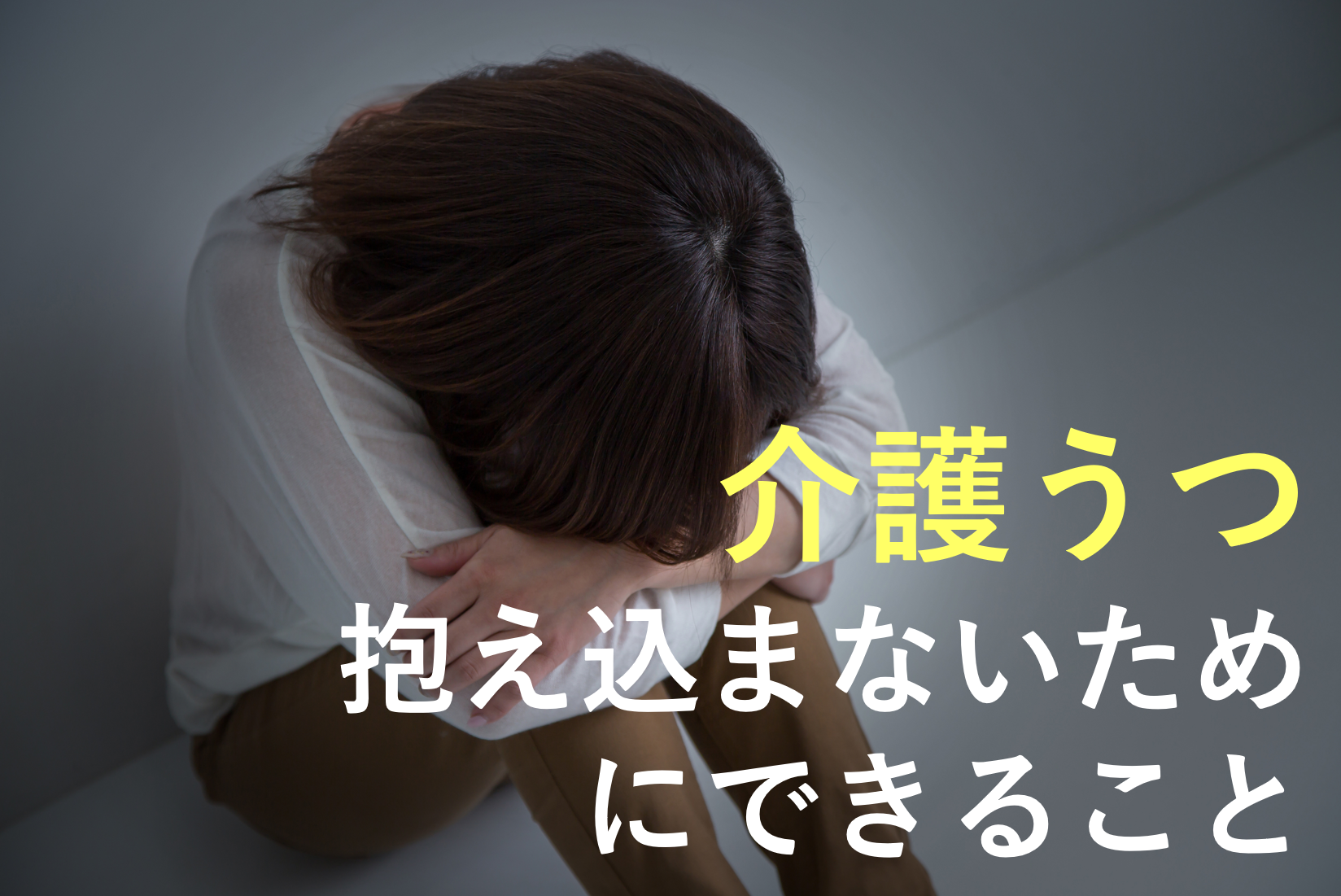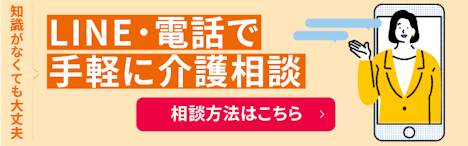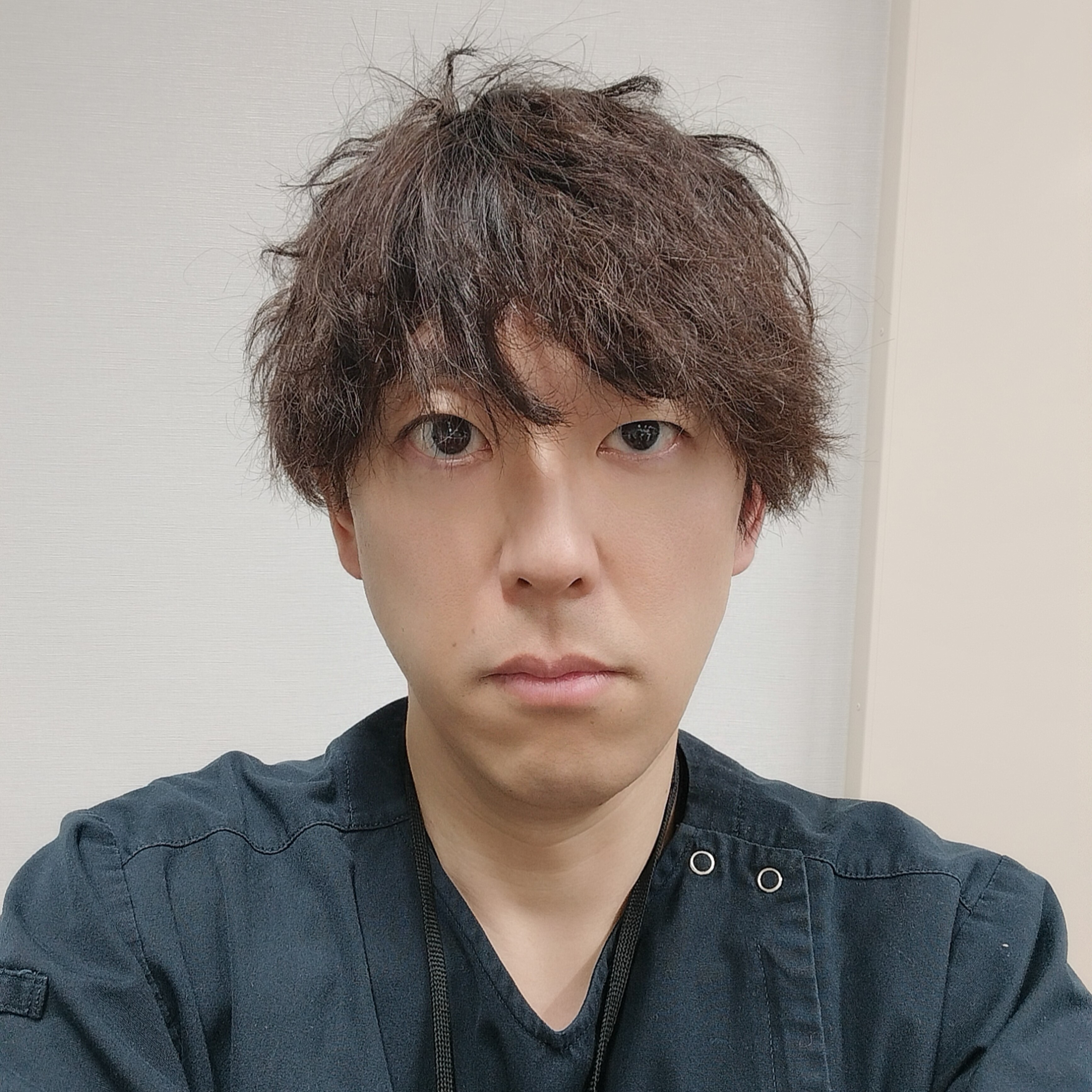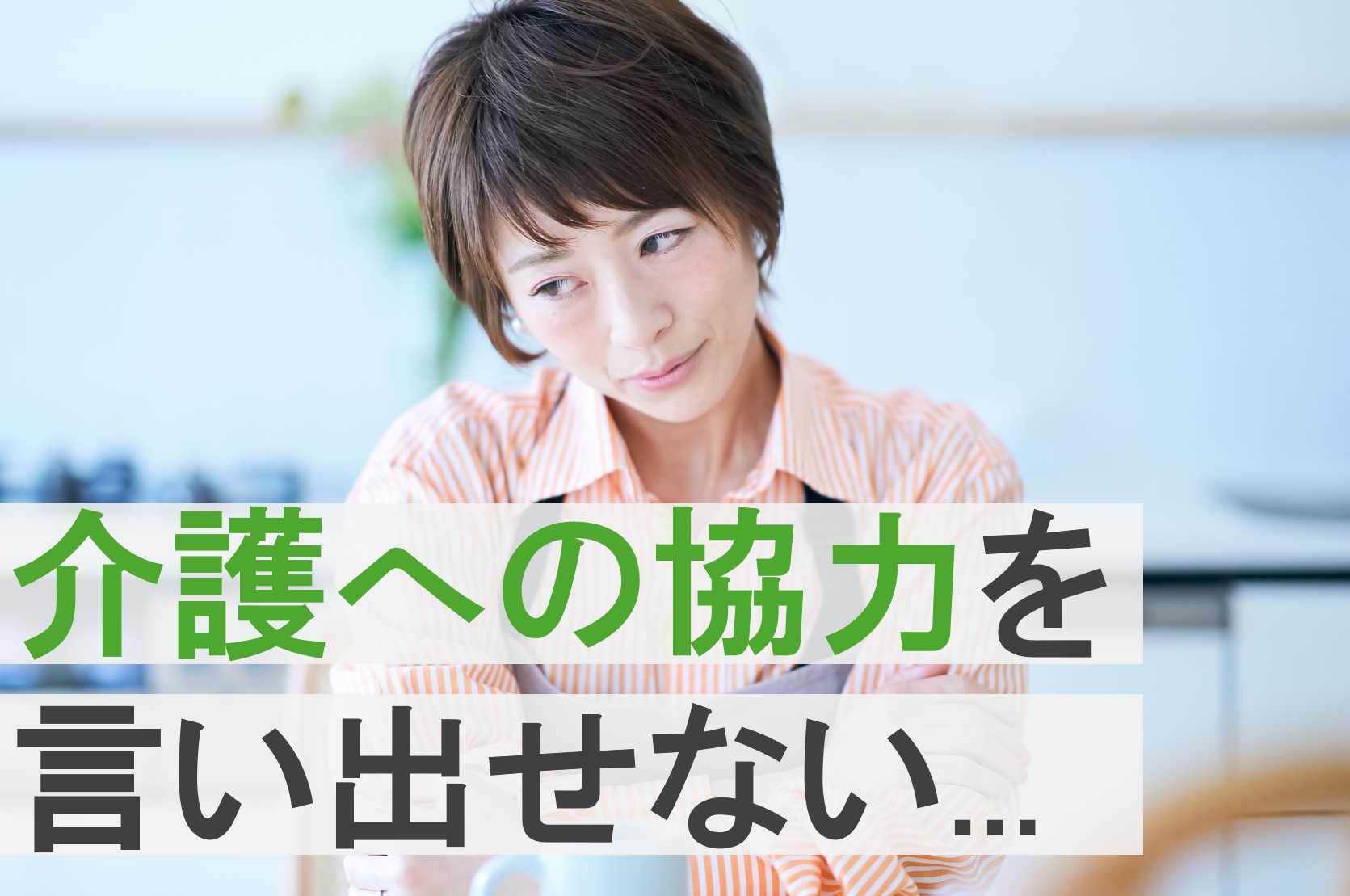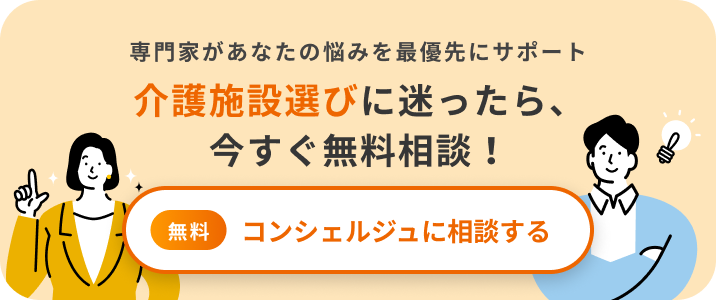介護うつとは

「介護うつ」とは、身内などの介護をする人が、介護を原因としてうつ病の症状を発症した状態のことです。介護は身体的な負担だけでなく、精神的なストレスも大きいため、うつ状態に陥ることがあります。
単なる疲労感とは異なり、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失、睡眠や食欲の異常、集中困難、自己評価の低下などが2週間以上続く場合には、うつ病が疑われます。
この記事では上記を「介護うつ」とし、介護うつの原因やセルフチェックの方法について解説いたします。
介護うつとは具体的にどんな状態?
介護うつとは、ご家族様の介護をしている人が、介護を主な原因として発症するうつ病のことです。
単なる疲れとは異なり、気分の落ち込みや意欲低下、不眠、食欲不振など、さまざまな症状が現れます。
介護うつは、介護という状況が背景にあるため、より深刻化しやすい傾向があります。
どんな原因で介護うつになる?
介護うつになってしまう主な原因は、精神的、身体的、経済的ストレスの3つが考えられます。
精神的ストレスは、ひとりで介護を抱え込んでしまうことによる孤独感、大切なご家族様が以前と変わってしまったことへのショックなど、さまざまな感情が積み重なることが原因です。
身体的ストレスは、食事や排泄の介助で体に負担がかかったり、自身の体調が悪くても休めなかったりすることが挙げられます。
経済的ストレスは、介護用品の購入費、介護保険サービスの利用料負担に加え、介護のために仕事を退職したり、勤務時間を減らしたりすることによる収入減などが挙げられます。
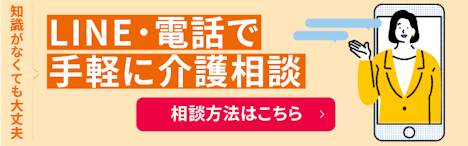
介護うつの度合いをセルフチェック
以下は、介護うつの度合いをセルフチェックするための表です。どのくらい当てはまるかチェックしてみましょう。
項目 | 回答 |
|---|
なかなか寝つけない、夜中に何度も目が覚める、または寝すぎてしまう | はい , いいえ |
食欲がない、または食べ過ぎてしまう | はい , いいえ |
朝から疲れやすく、身体がだるい | はい , いいえ |
頭や肩、首が重い | はい , いいえ |
気分が落ち込み、何事にも悲観的になる | はい , いいえ |
何事にも興味がもてず、集中力が続かない | はい , いいえ |
イライラして不安を感じる | はい , いいえ |
会社に遅刻したり欠勤したりすることが増えた | はい , いいえ |
「自分は駄目な人間だ」など否定的な発言が増えた | はい , いいえ |
趣味に興味を示さなくなった | はい , いいえ |
上記の「うつ病のサイン」は、あくまでも目安であり、誰にでも起こりうることです。
しかし、当てはまるものがいくつかあり、10日から2週間以上続く場合は、さらに悪化するのを防ぐため、メンタルクリニックなどに相談することをおすすめします。
参考:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ご存知ですか?うつ病」
介護うつを和らげるセルフケアを紹介

介護うつを予防するためには、日頃から自分自身の心と身体をケアすることが大切です。
ここでは、すぐに実践できるセルフケアの方法を紹介いたします。
【介護うつの防止に役立つセルフケア】 |
|---|
- まずはストレスを自覚する
- 深呼吸やストレッチをする
- 短時間の運動や散歩をする
- 睡眠環境など規則正しい生活リズムを整える
- 自分の時間を大事にする
- 周りの誰かに話して心を軽くする
|
まずはストレスを自覚する
まずは、自分のストレスを客観的に把握することから始めましょう。「自分は大丈夫」と思っていても、ストレスは知らないうちに蓄積されているからです。
毎日の出来事や感じたことを日記に書き出すことで、自分の感情を整理しやすくなります。また、定期的にストレスチェックリストを活用し、自分のストレスレベルを確認するのも有効です。
深呼吸やストレッチをする
ストレスを感じると無意識に呼吸が浅くなりがちです。そんなときは深呼吸すると、リラックス効果が期待できます。
深呼吸は、ゆっくり鼻から息を吸い込み、お腹を膨らませるイメージで、時間をかけて口から息を吐き切ります。また、ストレッチで首や肩をゆっくり回したり、背中を伸ばしたりすると、こわばった筋肉をほぐすことが可能です。
無理のない範囲で、空き時間に試してみてはいかがでしょうか。
短時間の運動や散歩をする
適度な運動は、ストレス解消に効果があるといわれています。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど、短時間でも身体を動かすことが大切です。
例えば、
- いつもより少し遠回りして買い物に行く
- エレベーターではなく階段を使う
- 近所を散歩する
など、外の空気を吸い、景色を眺めるだけでも気分転換になります。
睡眠環境など規則正しい生活リズムを整える
質の良い睡眠は、心身の疲労を回復させるために欠かせません。ぐっすり眠れた朝は、前向きな気持ちで一日をスタートできるものです。
質の良い睡眠をとるためには、睡眠環境を整えましょう。
- 寝室はできるだけ暗く静かな状態にする
- 寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は控える
- 自分に合った寝具を選ぶ
そして、規則正しい生活リズムを保つことも重要です。毎日できるだけ同じ時間に寝起きし、特に朝食はしっかりと食べるように心がけましょう。
日中に適度な運動を取り入れることも、眠りを促す効果があります。
自分の時間を大事にする
介護に追われていると、自分のことは後回しになりがちです。
しかし、介護うつを防ぐためには、自分のための時間をつくることを意識しましょう。1日に15分でも構いません。
好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、ゆっくり入浴するなど、心身共にリラックスできる時間をつくることをおすすめします。
また、疲れているときは、無理をせず休息を取ることも忘れないでください。
周りの誰かに話して心を軽くする
自分の悩みを誰かに聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。信頼できる家族や友人に、今の気持ちを正直に話してみましょう。
また、介護者の集まりに参加するのも、同じ悩みを持つ人と話せるのでおすすめです。
もし、身近に話せる人がいない場合や、専門的なアドバイスを聞きたい場合には、介護の専門家やカウンセラーなどに相談することも検討しましょう。
介護の専門家に相談してみる ▶
介護の悩みについての相談先を紹介

介護の悩みは、ひとりで抱え込まずに専門機関や窓口に相談することが大切です。ここでは、悩みの内容別に相談先を紹介いたします。
適切な相談先を選ぶポイント
介護の悩みは多岐にわたるため、内容によって適切な相談先が異なります。ここでは、相談先を選ぶ際のポイントを紹介いたします。
- 相談したい内容を明確にしておく
「介護と仕事の両立が難しい」「介護疲れで精神的につらい」など、まずは自分が悩んでいる内容を明確にしておくことが大切です。
- 相談方法を決定する
直接会って相談したいのか、電話やオンラインで相談したいのか、希望する相談方法に対応している窓口を選ぶと良いでしょう
最近では、電話やLINEなどを通じて、気軽に専門家へ相談できる環境も整ってきました。
- 専門性を確認する
介護の方法やサービス利用など具体的な相談は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課が適しています。心の悩みについては、心療内科やカウンセリングに相談しましょう。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域で支えるための「総合相談窓口」です。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が配置されており、介護に関する幅広い相談に対応しています。
例えば、要介護認定の申請や介護に関するアドバイスに加え、介護者の健康に関する悩みについてもサポートを受けることが可能です。
お住まいの地域のセンターに電話または訪問すれば、無料で相談できます。
自治体の介護相談窓口
市区町村の役所にも、介護に関する相談窓口が設置されています。
地域包括支援センターと同様に、介護保険制度の説明や申請手続き、地域の介護サービス事業者に関する情報を得られます。
心療内科やカウンセリングで相談する
「気分が落ち込む」「眠れない」などの不調が続く場合は、心身に大きな負担がかかっているサインかもしれません。
そのような場合は、心療内科や精神科などの専門機関への受診を検討しましょう。専門医による診断や治療を受けることで、症状の改善が期待できます。
また、カウンセリングを利用するのも有効です。臨床心理士や公認心理師などの専門家が、悩みを丁寧に聞き、サポートしてくれます。
厚生労働省のホームページで、ひとりで悩まないための相談機関や窓口が紹介されています。全国の医療機関も検索できるので、ぜひ参考にしてください。
参考:厚生労働省「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」
マイナビあなたの介護
最近では、都合の良い時間に電話やオンラインで専門家へ相談できるサービスも増えています。
「マイナビあなたの介護」は、在宅介護や施設探しなど、介護に関するさまざまなお悩みに無料で応えてくれる心強い味方です。
例えば以下のような、介護の悩みを気軽に相談できます。
- 家族が認知症になったかもしれない
- 在宅介護に何が必要なのか分からない
- 将来的に施設への入居も考えたいけれど、探し方が分からない
電話はもちろん、LINEでの無料相談も可能です。介護の専門家が、あなたのお悩みに寄り添い、解決に向けてサポートします。
介護の専門家への相談する ▶
介護をひとりで抱え込まないためにできること

介護は、長期間必要なことも多く、全てをひとりで抱え込んでしまうと、心身共に疲弊してしまいます。
ここでは、介護の負担を軽減するための制度や方法について紹介いたします。
介護休業制度を利用する
介護休業制度は、仕事と介護を両立するための制度です。
要介護状態にあるご家族様おひとりにつき、通算93日間を3回まで分割して取得できます。もちろん、1回で93日間休むことも可能です。
利用するためには、原則として2週間前までに勤務先に申請する必要があります。勤務先の規定を確認し、早めに相談・申請の手続きをしましょう。
参考:厚生労働省「介護休業とは」
介護休業給付金や介護慰労金を申請する
「介護休業給付金」とは、介護のために休業した場合、雇用保険から休業開始前の賃金の67%相当額を受け取れる制度のことです。申請の手続きは、勤務先を通じてハローワークで行います。
また、自治体によっては「介護慰労金」など独自の制度を設けている場合もあります。
ただし、自治体ごとに内容や対象となる要件が異なるため、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。
これらの制度を活用し、経済的な不安を少しでも和らげることが大切です。
参考:厚生労働省「第11章 介護休業給付について」、西東京市「家族介護慰労金を支給します」
デイサービス、ショートステイなどレスパイトケアを活用する
レスパイトケアとは、介護者が一時的に介護から離れ、休息するために利用するサービスのことです。
日帰りで利用できるデイサービスや、短期間の宿泊が可能なショートステイ、医療機関によっては、介護者の休息を目的としたレスパイト入院も提供されています。
これらのサービスを利用し、介護者は友人との交流や趣味に没頭する時間を持ち、精神的なゆとりを得ることが可能です。
▶ 介護負担を軽減できる「レスパイトケア」のメリットと注意点
家族や親族に協力してもらうように相談する
介護は、決してひとりで抱え込むものではありません。家族や親族に、現在の状況や困っていることを正直に伝え、協力を求めましょう。
家族会議を開き、介護の現状や課題を共有し、役割分担について話し合うことをおすすめします。遠方の場合には、電話やビデオ通話で連絡を取るのも良いでしょう。
会議の際には「大変だ」と感情的に訴えるだけでなく、どのような状況で、何に困っていて、どのような協力をしてほしいのかを明確に伝えることが大切です。
週末に見守りや話し相手になってもらったり、月数回の通院介助をしてもらったりするだけでも、かなり負担を軽減できます。
また、どうしても直接的な介助が難しければ、経済的なサポートをしてもらうのも良いでしょう。家族や親族と協力し、精神的な負担を軽減することが重要です。
まとめ

介護うつは、特別なことではなく、介護をしている方なら誰でも経験しうる「心の不調」です。ひとりで抱え込まず、早めにSOSを発信しましょう。
そのためには、自身の心と身体の状態に意識を向けることが大切です。
この記事でお伝えしたポイントを、以下にまとめます。
- 自分自身の状態を知る:気分の落ち込みや不眠は、SOSのサインかもしれません。セルフチェックで早めに気づきましょう。
- セルフケアを忘れずに:休息や自分の時間をつくることを意識的に行い、心と身体を守りましょう。
- ひとりで悩まない:「つらい気持ち」は誰かに話すだけでも楽になります。電話やオンラインで専門家に相談することも可能です。
- サポートを上手に活用:介護休業制度や給付金、レスパイトケア、家族の協力など、積極的に活用しましょう。
介護は「完璧」を目指す必要はありません。利用できるサービスや家族や制度を頼りながら、ご自身の健康を第一に優先してください。
介護の悩みは、人それぞれです。「介護のやり方が分からない…」「そろそろ施設も考えたいけど、たくさんありすぎて選べない…」
以上のように、答えが見つからず悩んでしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、「マイナビあなたの介護」をご活用ください。
介護をよく知る経験豊富な専門家が、あなたの抱えるお悩みや困りごとに、電話やLINEで無料相談に乗ってくれます。
「話を聞いてみたい」「情報収集だけでもしたい」という方も、専門家への相談で、介護のお悩みを一緒に解決するのはいかがでしょうか。
介護の専門家へ相談する ▶ 会員登録はこちら ▶
著者・監修現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
監修数年間の社会人経験を経て医師になる。現在は、精神科医として様々な疾患の治療に携わっている。
数年間の社会人経験を経て医師になる。現在は、精神科医として様々な疾患の治療に携わっている。