親が高齢になると、家族として介護を視野に入れた準備が必要になります。介護費用は突然発生することが多く、想像以上に高額になることもあります。
しかし、いざ長期的な計画を立てようとしても、費用の目安が分からず、不安を感じる人もいるでしょう。だからこそ、介護にかかる費用を正しく知り、早めに備えておくことが大切です。費用の見通しが立てば、介護への不安も和らぐでしょう。費用の目安や、長期的な介護計画を立てる際の考え方のポイントをご紹介します。
介護の費用と経済的支援を知る
介護の基礎知識
介護費用の長期的な計画は早めの準備が鍵!考え方のポイントをご紹介記事をシェアする
親が高齢になると、家族として介護を視野に入れた準備が必要になります。介護費用は突然発生することが多く、想像以上に高額になることもあります。
しかし、いざ長期的な計画を立てようとしても、費用の目安が分からず、不安を感じる人もいるでしょう。だからこそ、介護にかかる費用を正しく知り、早めに備えておくことが大切です。費用の見通しが立てば、介護への不安も和らぐでしょう。費用の目安や、長期的な介護計画を立てる際の考え方のポイントをご紹介します。


介護の長期的な計画を立てるためには、介護費用の平均額や目安を把握しておくことが重要です。
生命保険文化センターの調査から平均的な費用、介護期間をご紹介します。

出典:生命保険文化センター|生命保険に関する全国実態調査2024(令和6)年度
平均47万円
一時的な費用とは、住宅改造や介護用ベッドの購入費などが該当します。平均は47万 ですが、内実は「0円(掛かった費用はない)」から「200万円以上」まで幅広いです。
平均9.0万円
上記のとおり、月々の費用の平均は9.0万円ですが、介護を行う場所によって差があります。場所ごとの平均は次の通りです。
・在宅:平均5.2万円
・施設:平均13.8万円

出典:生命保険文化センター|生命保険に関する全国実態調査2024(令和6)年度
介護期間は平均55.0カ月
介護期間の平均は55.0カ月(4年7カ月)ですが、介護期間が「10年以上」と答えた割合も14.8%に上ります。また、回答者のなかには介護中の方も含まれており、その場合は、「これまでの介護期間」で回答しているため、実際の介護期間は上記よりも長くなるといえるでしょう。
介護にかかる費用は、利用する施設によっても差が大きいです。入居一時金は施設ごとに幅がありますが、入居一時金が少ない場合には月額費用が高めである傾向が多いです。参考として、以下に施設ごとの特徴と、大まかな費用の目安をご紹介します。
.png?w=700&h=494)
施設の費用の目安だけでなく特徴を確認し、介護の基本方針や入居を検討する施設の種類・場所の目星をつけておくことをおすすめします。
また、以下でどの施設がどういった人に向いているかの考え方を解説します。
可能な限り自宅で過ごしたいと考えていても、在宅介護が難しくなるケースもあります。その際の選択肢として、「介護付き有料老人ホーム」「特別養護老人ホーム」などが挙げられます。これらの施設には個室が用意されていることも多く、自宅のようにプライバシーを保ちながら、必要な介護サービスを受けることが可能です。施設については費用、場所、雰囲気などから、何を優先させるか決めて、候補施設のイメージを固めるとよいでしょう。
同世代の仲間と過ごしたい場合は、「サービス付き高齢者向け住宅(一般型)」「住宅型有料老人ホーム」「ケアハウス(自立型)」などから、施設内のイベントや交流が活発な施設を選ぶといいでしょう。ただし、これらの施設のなかには、介護状態が進むと退去を求められる場合があるので、退去後の住まいについても考えておく必要があります。
費用がかかってでも手厚い介護サービスを受けたい場合であれば、「介護付き有料老人ホーム」がおすすめです。種類も多く、満足できる施設が見つけやすいでしょう。
なお、介護費用を考える際は、介護期間についても留意しましょう。例えば、先述の介護期間の平均は「平均55.0カ月」ですが、これはあくまで平均であり、実際の介護期間はその人によって異なります。
例えば、75歳から要介護認定を受け、その後も長生きした場合、介護が必要な期間が10年、20年と続く可能性もあります。このように、平均より介護が長引いた場合を想定し、余裕を持った介護費用の計画を立てることが大切です。
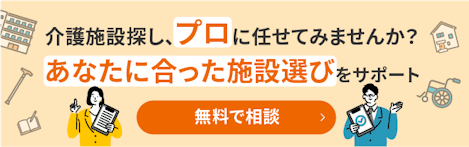

介護費用の長期計画を立てるための、3つのステップをご紹介します。
要介護者本人(以下、本人)の資産を把握し、身の丈にあった費用計画を立てることが重要です。
資産に見合わない生活は、将来的に資産が不足する懸念があります。しかし、必要以上に支出を抑えると介護のサポートが不足し、状況が悪化したり、生活環境が悪くなる恐れがあります。そのため、バランスが重要になります。
以下で資産の把握の仕方を説明します。
本人の毎月の収支を把握します。「収入」と「支出」を確認することで、資産残高の推移を確認できるようにすることが目的です。次のような項目の金額を確認しましょう。
収入 |
|
|---|---|
支出 |
|
収支がマイナスになった際の備えとして、手元の預貯金や、必要に応じて取り崩せる資産を把握しましょう。
現預金以外の資産は、市場価格の変動があるため、売却時の金額が予測しづらいことがあります。そのため、時価はやや控えめに見積もっておくのが堅実です。また、車や貴金属、不動産などはすぐに現金化できない可能性も考慮するとよいでしょう。
また、自宅を保有している場合は、将来的に施設入居を想定して、自宅を売却できるかどうかも検討しておくとよいでしょう。
要介護者の家族の役割には、大きく経済的な負担と介護を担う役割に分かれます。
本人の収入・資産で介護費用をすべて賄いたくても、場合によっては家族が費用を負担することもあるでしょう。
介護の担い手としての負担とは、食事介助や買い物、通院の付き添いなどを指します。
これらの役割を、家族でどう担っていくのか考えることは重要です。
はじめに、家族それぞれの近況を確認しましょう。「子どもが小さい」「遠方に住んでいる」「経済的余裕がない」など、それぞれの事情を理解したうえで、「できること」「やりたいと思っていること」を共有することが大切です。コミュニケーションを取りながら、具体的にどうしていくかを話し合いましょう。
介護費用を把握するために、大まかなシミュレーションをしましょう。シミュレーションの段取りは次の通りです。
【シミュレーションの段取り】 |
|---|
①親の年齢と介護期間を想定 ②在宅介護・施設入居の年数を見積もる(※) ③「①」と「②」から費用を計算 |
(※)②は「在宅介護10年の後、施設入居10年」のように、比率を決めて見積もる
シミュレーション時に注意したいのが、「在宅介護」と「施設入居」で大きく金額が異なる点です。先述した生命保険文化センターとの「在宅介護」の平均値から、「在宅介護10年の後、施設入居10年」とする場合の費用例を紹介します。
<例:75歳の親(ひとり親)を84歳まで在宅で介護する場合> |
|---|
(1)一時的な費用:47万円 (2)毎月:5.2万円×120カ月=624万円 |
<例:85歳の親(ひとり親)が94歳まで施設に入居する場合> |
|---|
(1)入居一時金:0~数千万円 (2)毎月:13.8万円×120カ月=1,656万円 |
シミュレーションで資産がマイナスになることもあるでしょう。しかし、預貯金を含めたケースを考え、預貯金や必要に応じて取り崩せる資産が「ゼロ」になるまで何年くらいかかるのかを知ることも目的のひとつです。
シミュレーションの結果、介護費用の計画が厳しい場合、次のような選択肢があります。

介護費用の長期的な計画を立てる際は、次のポイントに留意しましょう。
本人の意思を尊重することは、介護計画を立てるうえで大前提です。費用を考えつつ、本人の希望に沿った介護計画を検討しましょう。ただし、本人にとって自ら介護について話すことは心理的に負担が大きい場合もあります。いきなり介護の話題を切り出すのではなく、「老後にどんな暮らしをしたいか」といった将来設計の話題から入り、徐々に希望を聞き出すのがよいでしょう。
在宅介護では、介護する側の身体的・精神的負担も十分に考える必要があります。時間の制約、慢性的な疲労、体の不調といった負担が積み重なると、介護そのものを継続するのが難しくなる可能性もあります。
また、介護のため交通費がかさんだり、働く時間を減らさざるを得ないなど、家計への影響が生じることもあります。介護費用の計画には、介護者自身の生活も視野に入れておきましょう。
介護費用とは別に医療費が発生する可能性も考慮しておきましょう。高齢者は、転倒による骨折や誤嚥性肺炎などのリスクが高く、入院や手術が必要になることもあります。こうした事態に備えて、民間医療保険の加入状況や保障内容、高額医療養費制度の適用範囲についても事前に確認しておくと安心です。
なお、医療費がかからない場合も、75歳以上であれば後期高齢者医療制度の保険料は原則として支払いが続きます。
地域包括支援センターは、自治体が設置する公的な相談窓口で、介護・福祉・医療・生活支援などに関する総合的なサポートを提供しています。介護が始まる前から利用でき、将来的な介護の必要性や、今受けられる支援についての相談ができます。
また、センターによっては、認知症予防の教室や健康相談といった地域活動も行っており、健康維持に役立つ情報を得られます。迷ったときの相談先として活用するとよいでしょう。

介護は選択肢によって費用が大きく変わります。資産や負担を把握し、家計にとって無理の少ない介護を目指したいものです。ただし、家計面とともに本人の意向や、介護する側の役割分担・負担についても配慮することが重要です。
家計や周囲、総合的に無理のない介護計画を立てるためには、親子や兄弟姉妹で気軽に介護について話せるようにしておくことが大切です。早い段階で介護に意識を向け、介護費用の計画を立てていきましょう。
予算に合った介護施設を探す際には、マイナビあなたの介護で相談することができます。LINEや電話で介護で、介護の専門家に手軽に聞くことができます。最適な施設探しから介護準備のお手続きのサポートなど幅広く対応しています。
どんな些細なお悩みでも、まずはご相談してみるのはいかがでしょうか。
参考URL
生命保険文化センター|生命保険に関する全国実態調査2021(令和3)年度
介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?|生命保険文化センター
リスクに備えるための生活設計|生命保険文化センター

FPサテライト所属 ファイナンシャルプランナー
堀田 絵里奈(ほりた えりな)
FPサテライト所属 ファイナンシャルプランナー
堀田 絵里奈(ほりた えりな)
現在は独立系FPとして執筆業務をはじめ幅広く活動中。
現在は独立系FPとして執筆業務をはじめ幅広く活動中。