家族や自分自身に介護が必要になったときのために、介護サービスについて気になっている人も多いはずです。また、介護サービスと一口にいっても非常に種類が多いため、どのような介護サービスを利用できるのか、整理しておきたいという人もいるでしょう。
この記事では、介護サービスの種類や内容を、一覧でわかりやすく解説します。介護サービスを利用するまでの流れについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
介護サービス探しの第一歩
介護の基礎知識
介護サービスとは?種類の一覧やサービス内容を紹介記事をシェアする
家族や自分自身に介護が必要になったときのために、介護サービスについて気になっている人も多いはずです。また、介護サービスと一口にいっても非常に種類が多いため、どのような介護サービスを利用できるのか、整理しておきたいという人もいるでしょう。
この記事では、介護サービスの種類や内容を、一覧でわかりやすく解説します。介護サービスを利用するまでの流れについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


介護サービス(介護保険サービス)とは、40歳以上の人が加入する介護保険を利用して受けられる各種サービスのことです。65歳以上もしくは特定の条件下で介護が必要な40~64歳の人が、介護サービスを受けられます。
なお、介護サービスを受けるためには、介護サービスの必要度を判断する「要介護認定」で、要支援1~2あるいは要介護1~5の認定を受ける必要があります。介護サービス利用者の所得に応じて、料金の1~3割を負担することで、介護サービスを受けることが可能です。
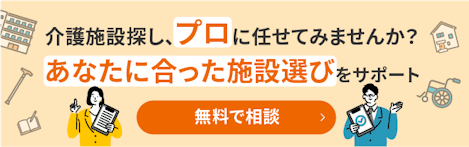

介護サービスには、大きく分けて「介護給付を行うサービス(要介護の認定を受けている人向け)」と「予防給付を行うサービス(要支援の認定を受けている人向け)」の2つがあります。具体的には、下記のような介護サービスがあります。
■介護サービスの種類
要介護度 | 介護サービスの種類(一例) | |||
|---|---|---|---|---|
介護給付を行うサービス | 要介護1~要介護5 | 居宅介護支援 | 利用者が自宅で自立した生活を送れるよう、ケアマネジャーがケアプランを作成し、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービス | |
居宅介護サービス | 訪問サービス |
| ||
通所サービス |
| |||
短期入所サービス |
| |||
施設サービス |
| |||
地域密着型サービス |
| |||
予防給付を行うサービス | 要支援1~要支援2 | 介護予防支援 | 利用者が自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、ケアマネジャーがケアプランを作成し、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービス | |
介護予防サービス | 訪問サービス |
| ||
通所サービス |
| |||
短期入所サービス |
| |||
地域密着型介護予防サービス |
| |||
※上記は一例。このほか、居宅介護(介護予防)福祉用具購入、居宅介護(予防介護)住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。
※厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」
なお、要介護認定を受けていない人(自立した人)向けにも、介護を予防するための訪問介護や、通所介護に相当するサービスのほか、身体のトレーニング、頭の体操といったサービスがあります。
ここからは、介護給付を行うサービスと予防給付を行うサービスについて、詳しくご紹介します。

要介護の認定を受けた人向けに介護給付を行うサービスには、「居宅介護支援」「居宅介護サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の4種類があります。それぞれのサービスの内容を見ていきましょう。
居宅介護支援とは、利用者が自宅で自立した生活を送れるよう、ケアマネジャーがケアプランを作成し、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービスのことを指します。利用者負担は発生せず、無料でサービスを受けられます。
居宅介護サービスとは、自宅で生活する人を対象とした介護サービス全般のことを指します。居宅介護サービスには主に、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」の3種類があります。それぞれのサービス内容は、下記のとおりです。
訪問サービスとは、介護職員や看護職員が自宅を訪問して実施する介護サービスです。訪問介護や訪問入浴、訪問看護などが該当します。
通所サービスとは、介護施設に通って受ける介護サービスです。通所介護や通所リハビリなどが該当します。
短期入所サービスは、30日間までの連続利用に限り、介護施設に宿泊して受けられる介護サービスです。短期入所生活介護(ショートステイ)や、短期入所療養介護が該当します。
なお、上記3種類のサービスのほかにも、福祉用具のレンタルおよび購入費の支給や、自宅で暮らし続けるための住宅改修費の支給といったサービスもあります。
施設サービスとは、介護施設に入所して受けられる介護サービスのことです。具体的には、下記でご紹介する施設で介護サービスを受けることができます。
介護老人福祉施設は、常に介護が必要な人が、可能な限り在宅復帰できるよう、入浴や食事などの支援や機能訓練のほか、療養上の世話などをする施設です。基本的には、要介護3以上の人が利用できます。
介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している人が、可能な限り自立した日常生活を送れるよう、リハビリテーションや必要な医療のほか、介護などのサービスを受けられる施設です。要介護1~5の人が対象となります。
介護医療院は、長期にわたって療養が必要な人が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、療養上の管理や看護・介護のほか、機能訓練、そのほか必要な医療、日常生活に必要なサービスなどを受けられる施設です。要介護1~5の人が対象となります。
地域密着型サービスとは、認知症高齢者や中重度の要介護高齢者などが、住み慣れた地域で生活が継続できるよう、市区町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスのことです。具体的には、下記3つのサービスがあります。
認知症対応型共同生活介護とは、認知症の人を対象に専門的なケアを提供し、可能な限り自立した日常生活を送れるよう支援する施設です。1つの共同生活住居に5~9人の利用者が入所し、介護スタッフと共に共同生活を送ります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、常に介護が必要な人が可能な限り自立した日常生活を送れるよう、入浴・食事などの支援や機能訓練のほか、療養上の世話などをする介護サービスです。利用者は、定員30人未満の施設に入所してサービスを受けられます。基本的には、要介護3以上の人が利用できます。
地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送れるよう、生活上の支援や機能訓練などを受けられるサービスです。利用者は、入所定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームに入所してサービスを受けることができます。

続いては、要支援認定を受けた人向けに、予防給付を行うサービスについて見ていきます。
予防給付を行うサービスとは、まだ本格的な介護は必要ない人(要支援の人)が、できる限り要介護状態になることを防ぐために、生活機能の維持向上や改善を目的としたサービスのことです。具体的には、「介護予防支援」「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」があります。
介護予防支援とは、要支援1~2の認定を受けた人が、自宅で介護予防のためのサービスを利用できるよう、ケアマネジャーや保健師などがケアプランの作成などを行うサービスです。ケアマネジャーは、ケアプランをもとに事業所や施設などとの連絡・調整も行います。
介護予防サービスとは、高齢者ができるかぎり要介護状態に陥るのを防ぐため、生活機能の維持向上や改善を目的としたサービスのことです。介護予防サービスは、主に「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」の3種類があります。それぞれのサービス内容は、下記のとおりです。
訪問サービスは、看護職員や介護職員が訪問し、自宅で入浴の介助やリハビリテーションのほか、療養上のサポート、診療の補助などを受けられるサービスです。訪問サービスには、介護予防訪問入浴介護ほか、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導などがあります。
通所サービスとは、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)のこと。介護老人保健施設や病院などに通い、専門スタッフによる機能の維持回復訓練や日常生活に必要な動作訓練を受けられる、リハビリテーションを中心としたサービスです。
短期入所サービスは、福祉施設や医療施設に短期間入所し、介護や医療、機能訓練を受けられるサービスです。具体的なサービスとしては、介護予防短期入所生活介護(福祉施設等のショートステイ)や介護予防短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)などがあります。
地域密着型介護予防サービスとは、利用者が住み慣れた地域を離れることなく、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供される介護サービスです。具体的には、下記のようなサービスがあります。

介護サービスには、これまでにご紹介した「介護給付を行うサービス」と「予防給付を行うサービス」以外にも、生活環境を整えるためのサービスも存在します。
このサービスは、利用者の日常生活において必要な自立支援を行うとともに、介護者の経済的負担の軽減を図るためのサービスです。具体的なサービスには、「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」「住宅改修」などがあります。
福祉用具貸与とは、日常生活や介護に役立つ福祉用具をレンタルできるサービスです。車椅子や車椅子付属品のほか、特殊寝台、手すりなどが貸与品に含まれます。サービスの対象となるのは、要介護1以上の認定を受けた人です。
特定福祉用具販売とは、日常生活や介護に役立つ福祉用具を販売するサービスです。腰掛便座や入浴補助用具のほか、簡易浴槽などを購入することができます。サービスの対象となるのは、要介護1以上の認定を受けた人です。
住宅改修は、利用者が住み慣れた住宅で生活し続けられるよう、手すりの設置や段差の解消などの改修を行うサービスです。要支援1~2および要介護1以上の認定を受けた人が対象となります。
介護サービスを利用する際には、要介護認定の申請や市区町村の職員による調査など、さまざまな準備が必要です。
まずは、市区町村の窓口で要介護認定を申請します。要介護度は、市区町村の職員による調査や、主治医意見書による審査を経て決定されます。さらに、ケアマネジャーが要介護度に応じたサービス計画書(ケアプラン)を作成し、介護サービスの利用を始めるのが一般的な流れです。
なお、介護サービスの利用においては、ケアマネジャーによるケアプランの作成は必須ではありません。ケアプランは自己作成も可能です。(セルフプラン)サービス費用を全額自己負担した後、保険者から自己負担割合に応じた金額が払い戻される「償還払い」の場合は、ケアプランを作成しなくてもサービスを利用できます。
■介護サービス利用の手続き

なお、要介護度別の心身の状態の目安は、下記のようになります。
■要介護度別の心身の状態の目安
区分 | 目安 |
|---|---|
自立 (非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分一人で行うことが可能であり、かつ、薬の内服や電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある。 |
要支援1 | 排泄や食事はほとんど自分一人でできるが、要介護状態とならないように身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とし、適切にサービスを利用すれば改善の見込みが高い。 |
要支援2 | 排泄や食事はほとんど自分一人でできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とし、適切にサービスを利用すれば改善の見込みが高い。 |
要介護1 | 排泄や食事はほとんど自分一人でできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。 |
要介護2 | 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。また、歩行や移動の動作に何らかの支えを必要とする。 |
要介護3 | 身の回りの世話や排泄が自分一人ではできない。また、移動などの動作や立位保持が自分一人ではできないことがある。さらに、いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。 |
要介護4 | 身の回りの世話や排泄が自分一人ではほとんどできない。移動などの動作や立位保持が自分一人ではできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
要介護5 | 排泄や食事が自分一人ではほとんどできない。身の回りの世話や移動などの動作や立位保持が自分一人ではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 |
※上に示した状態は平均的なものであり、完全に一致しないことがある。
※総務省「要介護認定等の仕組み」
※埼玉県朝霞市「要支援・要介護度の目安」
介護サービスの負担金額は、利用者の所得や介護サービスの種類によって異なります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
▶ 介護サービスの費用はいくら?自己負担額や保険の対象サービスを解説

介護サービスや施設を探す際には、信頼できるウェブサイトを利用することが大切です。下記のようなウェブサイトをご利用ください。
<介護サービスを探す際に利用したいウェブサイト>

介護サービスには数多くの種類があり、利用できるサービスや施設の内容もさまざまです。まずはどのような介護サービスがあるのか把握した上で、信頼できるウェブサイトを参考に介護サービスを選びましょう。
「マイナビあなたの介護」は、AI診断やコンシェルジュ相談といった特徴を備えた検索サービスです。最適な施設探しから介護準備のお手続きのサポートなど幅広く対応しますので、老人ホームを探す際にはぜひ「マイナビあなたの介護」をご活用ください。
参考URL・書籍
WAMNET「サービス一覧/サービス紹介」
厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」
書籍:「介護事業所・施設の選び方が本当にわかる本」(自由国民社)P50~53

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO
菊地 雅洋
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。
社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。