ご家族の物忘れや、怒りっぽくなることなどが増え、「もしかしたら認知症かもしれない」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。そんなとき、認知症について詳しく知っておくことで、不安が軽減されます。
本記事では、認知症とは何か、どのような状態なのか、初期症状で見られる症状についてわかりやすく解説します。また、認知症と判断されたときの対応についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
健康と生活を維持する
介護の基礎知識
認知症とは?主な種類や初期に見られる症状についてわかりやすく解説記事をシェアする
ご家族の物忘れや、怒りっぽくなることなどが増え、「もしかしたら認知症かもしれない」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。そんなとき、認知症について詳しく知っておくことで、不安が軽減されます。
本記事では、認知症とは何か、どのような状態なのか、初期症状で見られる症状についてわかりやすく解説します。また、認知症と判断されたときの対応についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


認知症とは、脳の細胞の動きが少しずつ変化し、記憶力や判断力といった認知機能が低下することによって、生活を送るうえで困難な症状や行為がある状態です。
WHO(世界保健機構)では、認知症を次のように定義しています。
認知症とは、脳の細胞の動きが少しずつ変化し、記憶力や判断力といった認知機能が低下することによって、生活を送るうえで困難な症状や行為がある状態です。 WHO(世界保健機構)では、認知症を次のように定義しています。 |
年齢を重ねるにつれて認知症と診断される方は増える傾向にあります。
2022年のデータでは、65歳以上の高齢者が認知症を発症している割合は12.3%となっています。
認知症の前段階にあたる「軽度認知障害」を含めると27.8%となり、65歳以上の高齢者の3人に1人に認知機能の低下が見られることがわかります。
参考:厚生労働省|認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計
とはいえ、認知症は65歳未満の方も発症する可能性があります。65歳未満の方が発症する認知症は「若年性認知症」と呼ばれます。
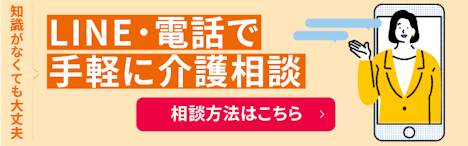
加齢によって記憶力が低下することで起きる「物忘れ」。
物忘れは、体験の一部を忘れるのに対し、認知症による物忘れは、体験そのものを忘れてしまい、生活に支障が出るという点で大きな違いがあります。
物忘れがあるからと言って認知症とは限りません。
軽度認知障害(MCI)は、認知症とまではいかないものの、物忘れ、記憶力・注意力の低下などの軽い認知機能の低下が見られている状態です。
日常生活を送るうえで大きな問題はありませんが、早期に発見することで、認知症への進行を遅らせたり、リハビリを行ったりすることが可能です。

認知症になると、次のような症状が現れます。これらは「中核症状」とも呼ばれ、認知機能の低下が原因で引き起こされます。
また、行動・心理症状(BPSD)として、妄想・幻覚・意欲低下・不安などの心理症状や、徘徊・興奮・暴言などの行動症状が現れることもあります。
これらの症状は認知症の症状にともなって周囲の環境や本人の心身状態によって引き起こされる症状で、「周辺症状」とも呼ばれています。

最も多いのはアルツハイマー型認知症です。
脳内に異常なたんぱく質が蓄積して脳が萎縮することで発症し、初期には言葉が出にくくなったり物の名前を思い出せなくなったりします。
昔の記憶は残っていても最近の出来事を忘れる傾向があり、進行すると過去の記憶も失われ、時間や場所の認識が難しくなります。
根本的な治療法は確立されていませんが、進行を遅らせる薬は存在します。
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血によって脳に酸素や栄養が行き届かなくなることで起こり、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病が原因となることが多いです。
生活習慣を改善することで予防できる可能性がある点が特徴です。
レビー小体型認知症は、脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質が生じることで神経が破壊されて発症します。
見えないものが見える幻視や幻聴が起こるほか、手足の震えや筋肉のこわばりといった症状が見られるのが特徴です。進行を遅らせる薬が開発されており、治療によって生活の質を維持することが可能です。
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉が萎縮・変形することで発症します。
初期には物忘れのほか、言葉の意味が理解できなくなる、意味のない言葉を話す、といった症状が現れることがあります。

認知症の初期には、いくつかの特徴的な症状が見られます。以下で詳しく見ていきましょう。
記憶障害の一種で、新しいことが覚えられなくなり、最近の出来事や会話、体験そのものを忘れてしまうといった症状が現れます。
上記のほか、何度も繰り返し同じことを尋ねたり、話したりするようになるのも特徴です。
また、判断力や理解力の低下も初期に見られる症状です。これは記憶障害や言語障害に伴って現れます。
時間や場所がわからなくなる「見当識障害」も初期症状のひとつです。
認知症の初期には、以下のように意欲の低下も見られることがあります。
認知症の初期には、強い不安感を訴える方も少なくありません。
孤独を感じたり、「頭がおかしくなった」と自ら不安を口にすることもあります。
認知症によって性格や人柄に変化が生じることもあります。
それまで穏やかで温厚だった方が、急に怒りっぽくなったり頑固になったりすると、周囲からも「最近様子がおかしい」と気づかれることが多いでしょう。
▶【医師監修】認知症初期に怒りっぽくなる理由とは?その原因と接し方を解説

認知症を初期段階で発見し、早期に診断・対応することで、進行を遅らせたり、症状を軽減する治療を受けられます。
以下の認知症では、根本的な原因を取り除くことはできなくても、薬によって認知症の症状を和らげる「対症療法」により進行を遅らせることができます。
また、本人がまだ意思表示できる状態であれば、今後の生活やケアの方針、財産管理について話し合うことができるため、段階的に準備していくことが可能です。
また、介護者も知識を身につけることで余裕を持って対応でき、家族の関係も良好に保ちやすくなります。
親や家族が認知症になった場合、何もせずに放置してしまうことは非常に危険です。
症状が進行すると、事故やけが、さらには思わぬトラブルにつながる恐れがあります。そのため、早い段階から適切な対応をとることが大切です。
ここでは具体的な対応方法を紹介します。
認知症の親や家族を支えるには、まず介護する側が正しい知識を持つことが重要です。
身近な人が認知症になると「なぜこんな行動をするのかわからない」と不安や苛立ちを感じる人も少なくありません。
認知症による症状や言動の意味を理解し、どう対応すべきかを知っておくだけで、心に余裕が生まれます。
「認知症かもしれない」と思い当たる症状がある場合は、かかりつけ医やもの忘れ外来を受診しましょう。
医療機関を受診し、診断を受けることで適切な治療や関わりができるようになり、本人に合ったサポートを早めに始められます。
各市区町村に設置されている「地域包括センター」では、介護や生活に関する幅広い相談を受け付けています。相談内容に応じて、支援方法やサービス利用の提案をしてくれるので、まずは気軽に相談してみましょう。
また、電話相談が可能な専門の窓口も活用できることがありますので、調べてみましょう。
介護が必要な状態と判断された場合は、「要介護認定」の申請を行いましょう。認定を受けると介護保険制度を利用でき、さまざまな介護サービスが利用可能になります。
利用できるサービスの一例 |
|---|
|
申請手続きは地域包括センターを通じて行えるため、まずは相談してみましょう。

認知症とは、さまざまな病気によって脳の細胞の働きが変化し、認知機能が低下することで日常生活に支障をきたす病気です。
認知症は、早期発見・早期対応によって、進行を遅らせたり、必要なサービスを適切に利用したりすることが可能になります。
本記事で紹介した初期症状を参考に、少しでも「認知症かもしれない」と感じることがあれば、できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。
本人も家族も安心して暮らしを続けていけるよう、環境を整え、適切なサポートを受けることが大切です。
認知症以外にも、介護には悩みや疑問が付きもの。もし、不安を感じることがあれば、「マイナビあなたの介護」を活用してみませんか。迷いが生じがちな介護サービスの選択、施設探し、介護準備のサポート、資料請求&見学申込の代行など、幅広い支援を行っています。
LINEや電話を使って、どうぞお気軽にご相談ください。
参考
国立長寿医療研究センター|認知症とは
厚生労働省|認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計
公益財団法人生命保険文化センター|リスクに備えるための生活設計
日本神経学会|認知症の定義、概要、経過、疫学
厚生労働省|参考資料「認知症の種類(主なもの)
厚生労働省|認知症に関する相談先
公益社団法人認知症の人と家族の会|電話相談
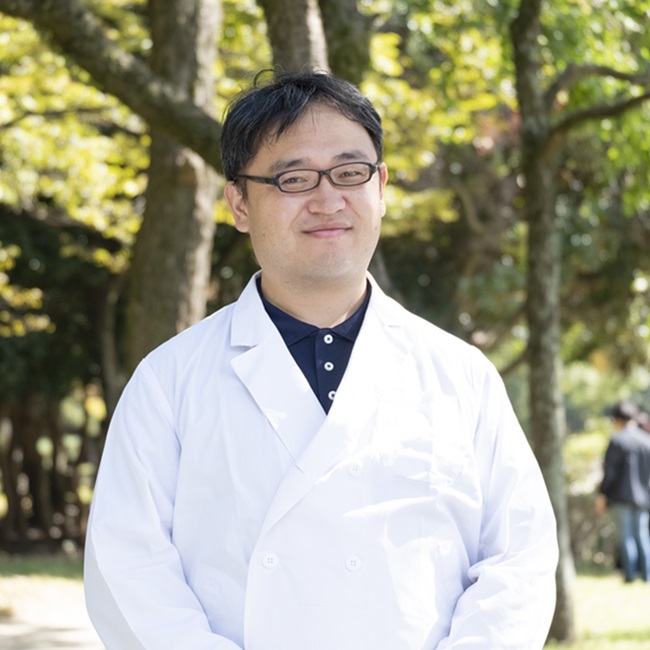
たがしゅうオンラインクリニック 院長
田頭 秀悟
たがしゅうオンラインクリニック 院長
田頭 秀悟
患者に医療の主導権を持ってもらう「主体的医療」を推進するオンライン診療医。
患者に医療の主導権を持ってもらう「主体的医療」を推進するオンライン診療医。