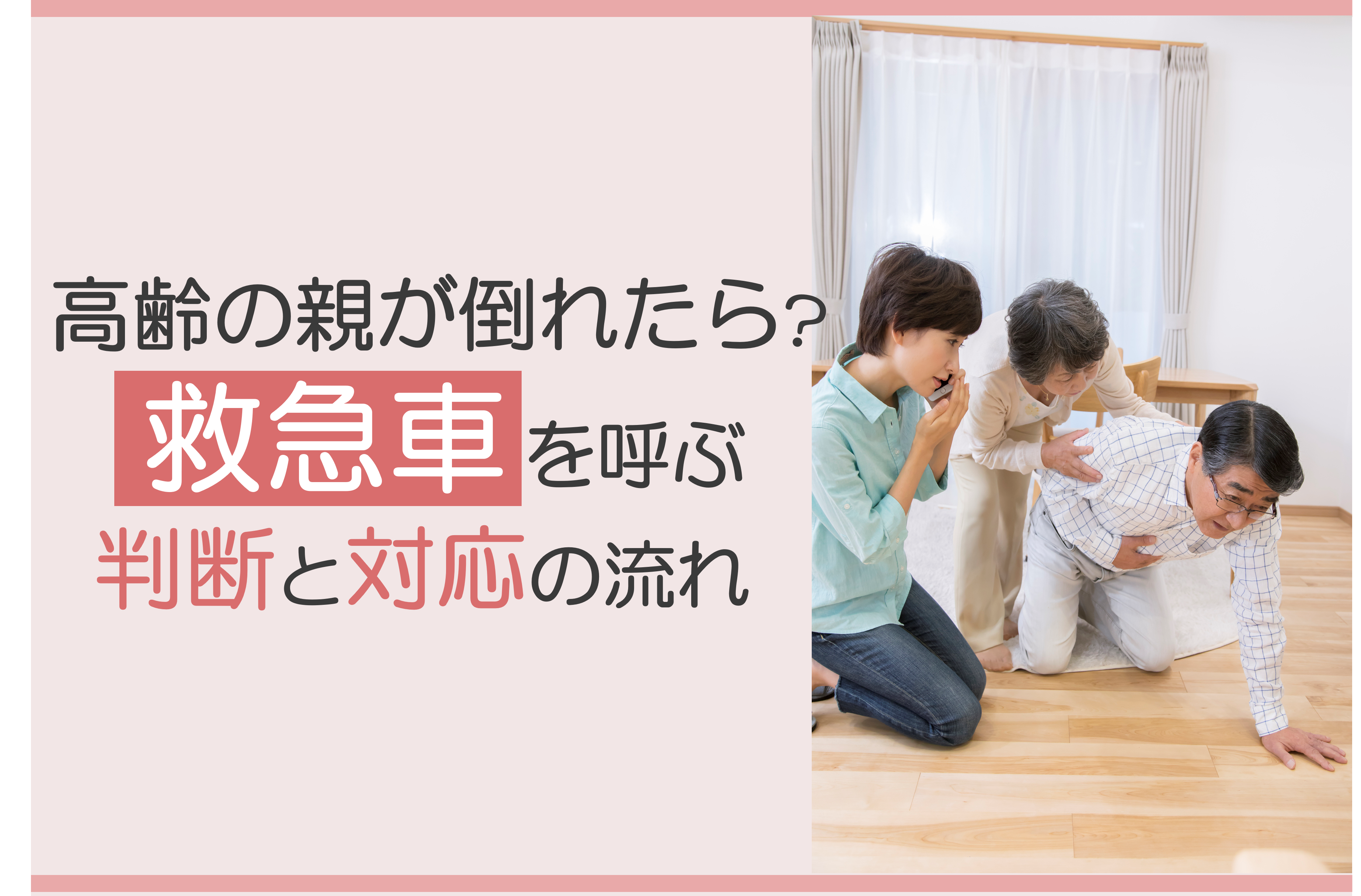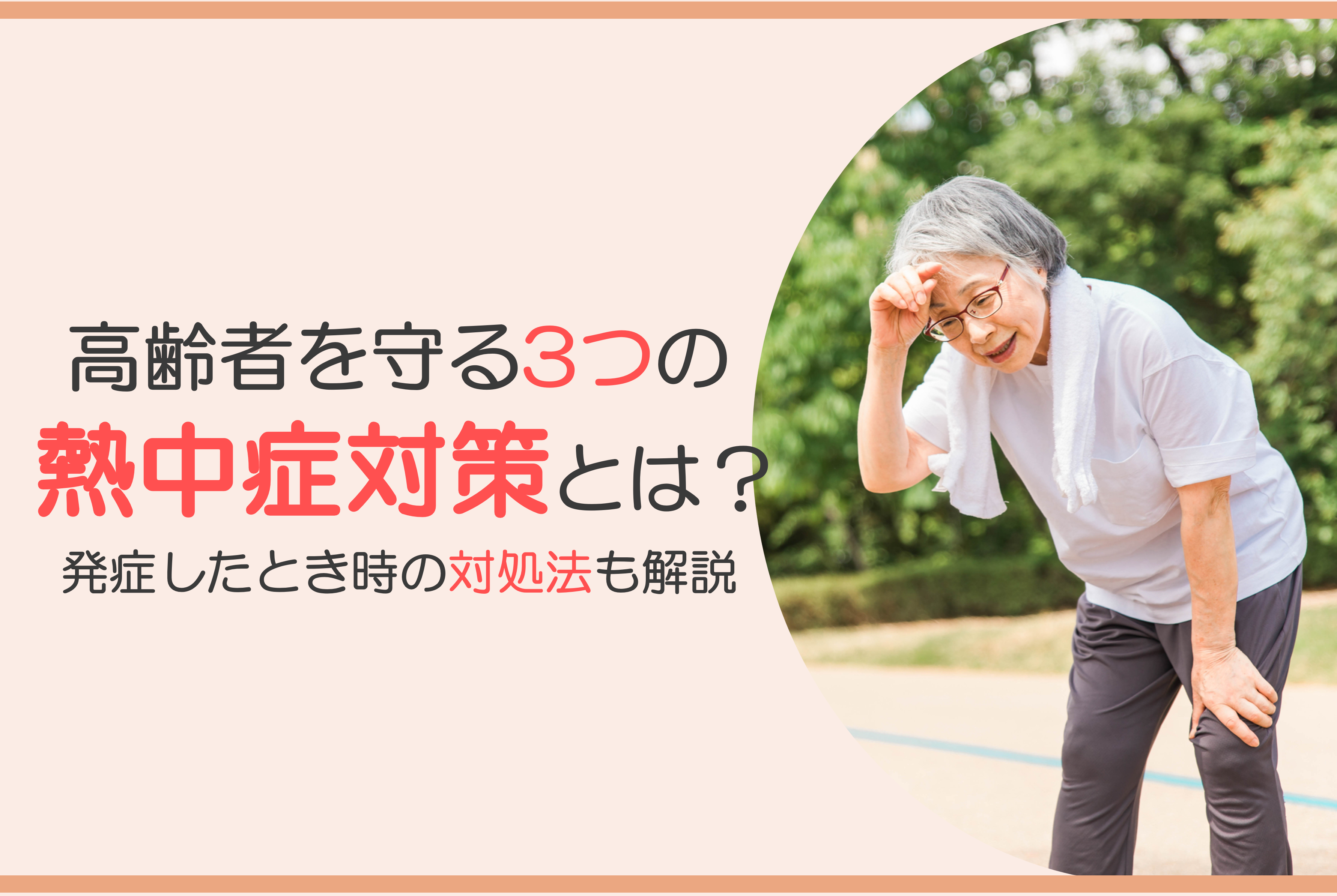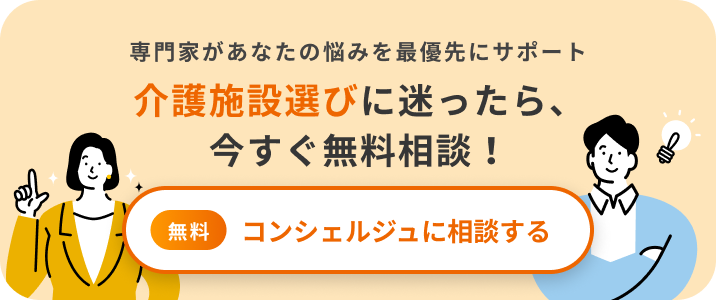Q&A
質問
寝たきりの在宅介護は大変ですか?
施設に入ってもらうことも考えたいのですが、在宅介護と施設入居でかかる費用の違いを教えてください。
回答
ご家族様が寝たきりになり、今後の介護について、不安に感じておられるお気持ち、お察しいたします。
実際、同じような悩みを抱えて相談に来られる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、寝たきりの方の在宅介護は、ご家族の力だけで続けるのは非常に大変です。そして、在宅介護と施設入居では、毎日の過ごし方や費用も大きく異なります。
在宅介護には「住み慣れた自宅で過ごせる」という安心感がありますが、介助の手間や急変時にどう対応するかという難しさを抱えてしまう面もあります。
一方で、施設入居は24時間体制のケアが受けられ、介護者の身体的・精神的な負担を大きく軽減できますが、経済的には在宅介護よりも費用がかかるケースが多いです。
どちらが正解というわけではありません。
大切なのは、ご家族様の体調や気持ち、ご家族のサポート体制、そして経済面などを踏まえて、無理のない形を見つけることだと思います。
介護の専門家への相談はこちら ▶
寝たきりの在宅介護の現実と選択肢
ここでは、寝たきり状態になる原因やリスクを整理したうえで、多くのご家族が直面する「在宅か施設か」という問題について解説いたします。
寝たきり状態とは?主な原因とリスク
「寝たきりの状態」と聞くと、ベッドに横たわったまま動けない状態を思い浮かべる方が多いでしょう。実際には、食事や排泄、入浴・着替えなど、日常生活のほとんどで介助が必要になり、自力で起き上がったり移動したりするのも難しい状態を指します。
寝たきりになる原因は、脳卒中や骨折、認知症、衰弱などです。入院や安静がきっかけで身体を動かさなくなり、そのまま寝たきりになる「生活不活発病(廃用症候群)」もよくみられます。
この状態を放置すると、床ずれ(褥瘡)や誤嚥(ごえん)、筋力の低下、関節のこわばりなどのリスクが高くなっていきます。
また、ご家族様が自分で動けないことでストレスが強くなったり「家族に迷惑をかけている」と感じてしまうことも少なくありません。
多くのご家族様が直面する「在宅か、施設か」の悩み
ご家族様が寝たきりになったとき、多くの方が「在宅か、施設入所か」という選択で悩まれます。
在宅介護は、住み慣れた環境でご家族様が安心して過ごせる大きなメリットがあります。一方で、介護負担や医療的ケアの不安、緊急時の対応など、ご家族様にとってハードルが高いことが一般的です。
施設入居は、24時間体制の介護や医療支援を受けられる安心感はありますが、費用負担が大きくなることに加え「家を離れることへの不安感」を抱える方も多いです。
さらに、施設の種類は多く「どれが合っているのか分からない」という声もよく聞かれます。
大事なのは「在宅だから良い」「施設はかわいそう」と決めつけることではありません。ご家族様やご家族のお気持ちや状況などを踏まえ「今の暮らしを無理なく続けられるかどうか」という視点で考えることが大切です。
あなたに合った介護方法を探す
介護で悩んでいる方にとって必要なのは「自分たちに合った選択肢」を見つけることです。
この記事では、寝たきりの方に必要な在宅ケアの方法や介護サービスの活用法、施設入所を選ぶ際の費用や比較ポイントを解説いたします。
この記事を読めば、あなたとご家族様の状況に最適な選択肢が見つかります。ぜひ、最後までお読みください。
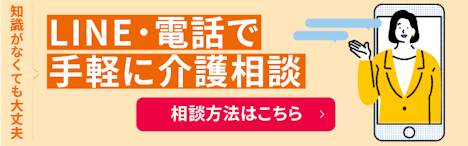
寝たきりの在宅介護でやること
.jpg?w=600&h=346)
ここでは、在宅介護でやるべきことを解説いたします。
①食事の介助
寝たきりの方にとって、食事は大きな楽しみです。ただし、身体を動かしにくい状態では、食べ物や飲み物が気管に入ってしまう誤嚥(ごえん)リスクが高まります。
◯姿勢のポイント
誤嚥を防ぐためには、上体を30〜60度ほど起こし、あごを軽く引いた姿勢をとります。
介護用ベッドのリクライニング機能やクッションを使って、ご家族様本人がリラックスできる姿勢を整えましょう。
※最適なベッドの高さは、ご家族様本人の状態や体調によって異なります。
◯食事形態の工夫
ご家族様本人の飲み込みやすさに応じて、とろみをつける・きざみ食にする・ムース状にするなど、食事の形態も調整しましょう。
最近では、市販の介護食やとろみ剤も充実しており、栄養バランスを保ちながら、誤嚥リスクを抑えることができます。
また、一口の量は少なめに、飲み込んだのを確認してから次のひとさじを口へ運ぶなど、ゆっくりとしたペースを心がけましょう。
ご家族様の状態によっては、栄養士や言語聴覚士(ST)のアドバイスを受けると、より安心して介助できます。
【参考】国立病院機構 兵庫中央病院 リハビリテーション科「誤嚥を防ぐために」
②排泄の介助
排泄介助は、ご家族様にとって、とてもデリケートなケアのひとつです。
皮膚トラブルや感染症を防ぐためにも、こまめに対応しましょう。
◯おむつ交換の基本手順
- まずは、必要な物品を準備します。(新しいおむつ・使い捨て手袋・陰部洗浄用のぬるま湯または専用シート・ゴミ袋など)
- 横向きにして、背中側のおむつを外します。身体の負担を軽減するため、左右交互に体位を変えながら行いましょう。
- 汚れた部分を清拭・洗浄します。汚れがひどい場合は、お湯やシャワーボトルで優しく洗い流します。
- しっかり乾かしてから、新しいおむつを当てます。湿ったまま装着すると、皮膚トラブルの原因になるので、注意が必要です。
- シワを伸ばして、圧迫感や漏れがないように調整しましょう。
◯陰部洗浄のポイント
- 前から後ろへ拭き取るのが基本です。(特に女性の場合、感染リスクが高まるため)
- 使い捨ての柔らかい布や洗浄用シートを使うと、肌への刺激を軽減できます。
- 肌が赤くなっている部分には、ワセリンや皮膚保護剤を使うのも有効です。
ご家族様の尊厳を守るために「これから行うケアの説明や動作ごとの声かけ」を忘れずに行いましょう。
声かけを行うことで、協力動作も得られやすく、よりスムーズな介助につながります。
③清潔の保持
寝たきりの方にとって、清潔を保つことは感染症や皮膚トラブルの予防だけでなく、QOL(生活の質)にも関わります。
「口の中が乾いている」「髪のベタつきが気になる」などの状態は、ご家族様にとって強い不快感につながるのです。
◯清拭(せいしき)
入浴が難しい場合は、温かいタオルで全身を優しく拭く「清拭」が効果的です。肌をこすらず、ポンポンと押さえるように拭くのがコツです。
脇の下・首・背中・陰部など、蒸れやすい場所を中心に行うと、清潔を保ちやすくなります。
◯口腔ケア
口の中が乾燥すると、誤嚥性肺炎のリスクや食欲低下につながります。
1日2回(朝・夜)を目安に、専用の口腔ケアスポンジや保湿ジェルを使って優しく清掃しましょう。
※入れ歯の場合は、毎食後の洗浄と就寝時の外し忘れにも注意が必要です。
口腔ケアについてや、詳しいやり方はこちらもご覧ください。
▶ 口腔ケアとは?介護で口腔ケアが重要な理由とやり方を解説
◯入浴介助
体調に問題がなければ、週1〜2回程度の入浴は、皮膚の状態や気分転換にも効果的です。在宅での入浴が難しい場合は、通所介護や訪問入浴サービスの利用も検討しましょう。
訪問入浴は、浴槽を持ち込んで、看護師と介護スタッフが入浴をサポートしてくれるため安心です。
清潔保持は、床ずれの早期発見など、全身を観察できる貴重な機会でもあります。毎日の変化を見守ることも、大切なケアのひとつです。
④床ずれ(褥瘡)の予防
寝たきりの方にとって、特に注意すべきなのが「床ずれ(褥瘡)」です。長時間、同じ姿勢でいることで、皮膚の下の血流が悪くなり、やがて皮膚や筋肉が壊死してしまう状態になってしまいます。悪化すると、感染症のリスクも高まります。
◯床ずれを防ぐには「体位変換」が大切
基本は、2時間おきに身体の向きを変えることです。右・左・仰向けを交互に切り替えることで、体圧がかかる部分を分散し、皮膚へのダメージを防ぎます。
ただし、ご家族様の状態によっては身体を動かすのが難しかったり、介護者にとって負担が大きい場合もあるため、クッションや体圧分散マットレスなどを活用して負担を軽減することも大切です。
◯福祉用具の活用が有効
介護保険の福祉用具レンタルを活用すれば、床ずれ予防や介護負担軽減ができます。
- 体圧分散マットレス:身体にかかる体圧を和らげる特殊なマットレスです。
- 体位変換クッション:姿勢を保ったまま横向きにしたり、支えたりできる補助具です。
- ポジショニングピロー:手足や腰回りなど、微調整したい部位に使える柔らかいクッションです。
また、皮膚の観察も忘れずに行いましょう。
「赤みがある」「皮膚が薄くなっている」などの症状は、床ずれの前触れです。病院受診するなど、早めに対応し重症化を防ぎましょう。
寝たきり介護の負担を軽くするサービス

全てのケアを、ご家族だけで行うのは困難です。ここでは、公的サービスを上手に使い、介護負担を軽減する方法を解説いたします。
最初の相談窓口「地域包括支援センター」
「誰に何を相談していいのか分からない」ときに頼れるのが、地域包括支援センターです。
全国の市区町村に設置されており、介護・医療・福祉の専門職が、無料で相談に応じてくれます。
地域包括支援センターで相談できること |
|---|
- 介護に関する悩みや不安
- 介護保険の申請方法
- 介護サービスの種類や内容
- 介護事業者に関する情報
|
「今すぐではないけど、将来の介護が不安」「ちょっと話を聞いてほしい」という段階でも相談できます。
在宅介護を支える介護サービス一覧
寝たきりの方を在宅で介護するには、介護サービスの利用が欠かせません。ここでは、代表的な介護保険サービスを紹介いたします。
〇訪問介護
ヘルパーがご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物などの生活援助を行います。
ご家族様ができない部分を補い、必要なサポートを柔軟に受けられるのが特長です。
▶ 訪問介護とは?サービスの内容や使い方を解説!
◯訪問入浴介護
看護師と介護職員が専用の浴槽を持ち込み、ご自宅で入浴をサポートしてくれるサービスです。
寝たきりの方でも、看護師による体調管理を受け、安心して入浴できます。
◯訪問看護
医師の指示のもと、看護師がご自宅を訪問して、健康チェックや医療的ケア(褥瘡処置・点滴・服薬管理など)を行います。
緊急時の相談や対応についても相談できるので安心です。
▶ 訪問看護とはどのようなサービス?対象者やメリット・利用料金を解説
◯短期入所生活介護(ショートステイ)
一時的に施設に泊まり、日常生活のサポートや医療的ケアを受けられるサービスです。
ご家族の休養(レスパイト)や、冠婚葬祭・出張などの予定にも活用できます。
▶ 短期入所生活介護(ショートステイ)とは?対象者や費用を解説
以上のような介護保険サービスを組み合わせると、介護負担を軽減できます。
在宅介護と施設入居の費用、メリット・デメリット比較

ここでは、在宅介護と施設介護の違いを比較表で整理し、それぞれの特徴を分かりやすく解説いたします。
【在宅介護・特養・介護付き有料老人ホームの比較一覧】
項目 | 在宅介護 | 介護老人福祉施設(特養) | 介護付き有料老人ホーム |
|---|
対象者※1 | 要介護4〜5 | 要介護3以上 | 要介護1以上 |
|---|
医療対応 | 訪問看護・訪問診療で対応可能 | 看護職員常駐(夜間は不在のことも) | 24時間体制の医療連携あり※施設によって異なる |
|---|
介護体制 | ご家族様中心、訪問系サービスでサポート | 24時間常駐の介護スタッフ | 24時間常駐の介護スタッフ |
|---|
費用目安(月額) | 約6万〜7.5万円+居住費・食費 ※2 | 約10万〜14万円(居住費・食費含む) | 約15万〜30万円以上(居住費・食費含む) |
|---|
入居のしやすさ | 制限なし | 入所待機者多数。数カ月〜年単位でかかることも | 民間施設が多く、比較的入所しやすい |
|---|
特徴 | 住み慣れた家で過ごせるが、ご家族様の負担が大きい | 公的施設で費用は安めだが、すぐには入所できない場合が多い | 充実した設備やサービスが魅力 最近は、特養と同程度の月額費用の有料老人ホームも増えている |
|---|
※1 対象者は、施設によって異なります。
※2 介護保険サービスの自己負担額、医療費、おむつ代等の合計目安。持ち家の場合、居住費はかかりません。
【参考】厚生労働省「サービスにかかる利用料」、公益財団法人 家計経済研究所「在宅介護にかかる費用」
在宅介護と施設入居の費用差
上記の表をもとに、在宅介護に必要な月額費用をみていきましょう。
在宅介護の場合
寝たきりの方は、要介護4〜5であることが一般的です。
公益財団法人家計経済研究所の調査によれば、介護保険サービスの自己負担や食費、医療費などを含めて、月6万〜7.5万円程度が一般的な目安です。
施設入居の場合
たとえば、介護老人福祉施設(特養)では、月額10万〜14万円が相場となっており、在宅介護との費用差は月4万〜8万円程度です。
この差額は、ユニット型(個室)か多床室かによるものです。
一方、介護付き有料老人ホームでは、サービス内容や立地によって月額15万〜30万円と幅があります。
そのため、在宅介護との差は月額9万〜20万円以上になるケースも珍しくありません。
ただし、最近では、特養と同水準の価格帯で入居できる有料老人ホームも増えてきており、選択肢は広がっています。
このように、在宅と施設では金額の開きが大きくなる場合もあります。
しかし、大切なのは、サポート体制やご家族様の負担軽減を考慮し、費用面だけでなく全体のバランスで判断することです。
寝たきりでも入居できる施設
寝たきりの方が長期的に生活する場として、主に検討されるのが特養と介護付き有料老人ホームです。
ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説いたします。
◯介護老人福祉施設(特養)
特養は、公的に運営されている介護施設で、要介護3以上の方が入所対象です。寝たきりの方など、日常生活においてサポートが必要な方にも対応しており、介護職員が24時間体制でケアを提供しています。
最大のメリットは、民間施設に比べて費用が抑えられる点です。多床室を選べば、より安く済むこともあります。一方、個室のユニット型を選ぶと、環境は良いものの、少し費用は上がります。
ただし、特養は全国的に入所希望者が非常に多く、待機期間が長くなることが一般的です。「すぐにでも入所したい」場合には、他の選択肢と併せて検討する必要があるでしょう
▶ 介護老人福祉施設(特養)とは?入所条件や費用相場・サービス内容を解説
◯介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、民間企業が運営する介護施設です。介護スタッフが24時間常駐し、入浴や排泄、食事などの日常生活全般のサポートを受けられます。
寝たきりの方でも安心して暮らせるよう、看護師の配置や医療機関との連携に力を入れている施設も多いです。また、施設によってはリハビリテーションやレクリエーション、ターミナルケアまで対応しているところもあり、「その人らしい暮らし」を大切にした介護を提供しています。
月額費用は15万〜30万円と幅がありますが、特養と同じくらいの価格帯で入居できる施設も増えてきました。
「比較的、短期間で入所したい」「医療対応が充実している」などの条件を重視する方にとって、有力な選択肢といえるでしょう。
▶ 有料老人ホームの種類とは?介護付き・住宅型・健康型の違いを解説
費用負担を抑える公的制度
ここでは、年金収入で施設費用を支払うために確認すべき公的制度を2つご紹介いたします。
◯高額介護サービス費制度
介護保険サービスを利用すると、自己負担額(1〜3割)が毎月発生します。その合計額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
この制度を利用すれば、上限を超えた分が後から戻ってくるため、家計の負担を軽減できます。払い戻しを受けるには、原則として市区町村の窓口への申請が必要です。手続きの詳細については、担当のケアマネージャーや市区町村の介護保険課に相談すると安心です。
◯世帯分離による負担軽減
世帯分離とは、住民票上の世帯を分けることです。ご本人様が「非課税世帯」として扱われるケースがあります。
非課税世帯になると、以下のようなメリットがあります。
- 高額介護サービス費の上限額が引き下げられる
- 施設入所時の食費・居住費の負担軽減制度(特定入所者介護サービス費)の対象になりやすい
- 医療費負担の軽減(高額療養費制度の上限引き下げ)につながることもある
ただし、全てのケースで適用されるわけではなく、実際の課税状況や収入によって異なります。制度利用の前に、市区町村や税理士、ケアマネージャーに相談しましょう。
【参考】栃木市「後期高齢者医療保険料のQ&A」
【介護経験者の声】 施設入居を決断した理由

ここでは、私がケアマネージャーとして、実際に施設入所のご相談を受けた事例2つを紹介いたします。
事例1:在宅介護の限界直前に決断
① 在宅介護時の状況
ご本人(91歳・女性・要介護4)は、在宅酸素を使用しており、訪問看護や訪問入浴を活用しながら在宅生活を送っていました。
もともとは、通所介護も利用していましたが、次第に通所が難しくなり、寝たきり状態になったのです。
食事や排泄なども含め、介護のほとんどを同居の長女様が担っていました。
② 葛藤・悩み
ご本人は認知機能が比較的しっかりしており、長女様も「できるだけ自宅で介護したい」という思いが強くありました。
一方で、兄弟姉妹は他県在住でサポートを受けられず、長女様もフルタイム勤務のため、心身共に疲労が蓄積します。サービスを活用しても限界を感じていました。
③ ケアマネージャーへの相談と提案
ケアマネージャーとして「自宅で介護したいが、もう限界に近い」という相談を受け、施設入所の選択肢を提案しました。
将来的な入所も視野に入れた支援を続けたのです。
④ 入所のきっかけ
長女様が、職場で新しいプロジェクトに配属され、残業や出張が避けられなくなったことで、在宅介護の継続が困難になったのです。
そこで、空きの出た近隣の介護付き有料老人ホームへの入所を決断されました。
⑤ 入所後の変化と家族の気持ち
ご本人は、24時間スタッフの見守りのもとで穏やかな生活を送っています。
長女様は、当初「申し訳なさ」があったものの、今では「いつでも会いに行ける」「母親も満足してくれている」と前向きな気持ちに変わってきています。
事例2:共倒れを防ぐための決断
① 在宅介護時の状況
ご本人(89歳・女性・要介護4)は、高齢のご主人と2人暮らしで、1日の大半をベッド上で過ごしていました。
ポータブルトイレを使用しており、歩行は不安定です。介助は全てご主人が行っていましたが、かなり体力が必要な状態でした。
また、認知症の影響で夜間に何度も起きてしまい、ご主人は十分な睡眠を取れない日が続いていました。
長女様は、車で2時間ほどの距離に住んでおり、フルタイムで勤務しています。
週末のたびに実家へ通い、サポートをしていました。
② 葛藤・悩み
早い段階から長女様は施設入所も視野に入れておられましたが、お父様が「自分がひとりになるのは寂しい」と希望されず、なかなか話が進まない状況が続いていたのです。
③ ケアマネージャーへの相談と提案
私はケアマネージャーとして、長女様からのご相談を受け、まずは特別養護老人ホームでのショートステイを提案しました。
長期入所に対するハードルが高かったため、最初は月に2泊程度から始め、徐々に利用回数を増やしていったのです。
④ 入所を決断したきっかけ
ある日、お父様が体調を崩し、腰痛も重なって動けなくなり、緊急入院となりました。その間、長女様が急きょ帰省されます。
仕事を1週間休み、ショートステイや他の施設を検討されました。
特養には空きがなく、ちょうど空きのあった病院の支援入院を利用することになります。1カ月の入院を経て、有料老人ホームへ入所することになりました。
⑤ 入所後の変化とご家族の気持ち
お父様の介護は、すでに限界を迎えていました。今回の入所はまさに「共倒れを防ぐ」決断だったと思います。
ご本人は今、介護施設で穏やかに過ごしておられます。お父様も体調が回復し、定期的に面会に訪れることで気持ちも安定されている様子です。長女様からは「介護の心配がなくなり、ようやく落ち着いて仕事ができるようになった」との声をいただいています。
施設の選び方とチェックポイント

ここでは、後悔しない施設の選び方とチェックポイントを紹介いたします。
「医療的ケア体制」と「看取り対応」の有無
施設を選ぶ際に、まず確認したいのが「医療的ケア体制」と「看取り対応」です。
ご家族様の病状の悪化などが予想される場合、医療ニーズにどこまで対応してもらえるかは重要なポイントといえるでしょう。
チェックしたい医療体制は、以下のとおりです。
- 在宅酸素・胃ろう・インスリン注射などの医療的処置への対応可否
- 看護師が常駐している時間帯
- 夜間の緊急時に医師と連携が取れる体制があるか
また「看取りケア」の可否についても確認しておきましょう。住み慣れた施設で最期を迎えられるかどうかは、とても重要です。
【チェックリスト】見学時に使える!質問リスト
施設見学では、パンフレットや担当者の説明だけでなく、雰囲気や職員の様子をしっかり観察することが大切です。
チェック項目 | 質問の例 |
|---|
スタッフの対応 | - 入居者にどんな言葉がけをしているか
- 笑顔や目線、声のトーンはどうか
|
生活環境 | - 居室は清潔に保たれているか
- 共有スペースのメンテナンスはされているか
|
食事の内容 | - 提供されている食事はどのような内容か
- 見学中に見られるか
|
入浴や排泄の支援体制 | - どのようなタイミングで、どれくらいの頻度でサポートされているか
|
職員配置 | |
緊急時の対応 | |
看取り対応 | - 看取りを行った実績は
- どのようなケアを実施しているか
|
可能であれば「昼食の時間帯」「レクリエーション時」など、施設がにぎわっている時間に見学されることをおすすめします。
普段の自然な様子が観察できます。
良いケアマネ・相談員の見つけ方
施設選びは、経験のある専門職と一緒に進めるのが安心です。
その中でも、良いケアマネージャーや相談員を見つけておくと、施設選びがスムーズになります。
◯信頼できるケアマネージャー・相談員の特徴
- 話をしっかり聞いてくれる(否定せず、共感してくれる)
- 選択肢を提示してくれる(押しつけず、比較させてくれる)
- 選択肢のメリット・デメリットをきちんと説明してくれる
- ご家族様の生活背景や気持ちに配慮がある
◯ケアマネージャーからのアドバイス
人間同士ですから「合う・合わない」は必ずあります。
もし「合わない」と感じた場合には、ケアマネージャーを交代してもらうことも可能です。
「何でも相談できそう」と感じられるケアマネージャーを選ぶことをおすすめします。
まとめ:あなたと家族に合った最善の選択をするために

寝たきりのご家族様を支える日々は、身体的にも精神的にも大きな負担がかかるものです。
施設入所を検討する際には、費用や入所後の生活について、悩みや迷いを持たれる方も多くおられます。
この記事のポイントは、以下のとおりです。
- 寝たきりの状態でも入居できる施設は複数あり、医療対応や費用の違いを確認することが大切です。
- 在宅介護には限界があり、共倒れを防ぐためにも早めの選択が必要になる場面があります。
- 良い施設選びには「医療的ケア体制」「スタッフの対応」「見学での印象」など複数の視点が必要です。
- 信頼できるケアマネージャーや相談員との連携が、後悔のない施設選びにつながります。
|
介護と仕事を両立しながら「ご家族様にとって納得できる形」をひとりで決めるのは、簡単なことではありません。
そんなときは、「マイナビあなたの介護」をご活用ください。
「マイナビあなたの介護」では、介護コンシェルジュが、施設探しや在宅介護など、さまざまな悩みに無料で対応いたします。電話やLINEで気軽に相談でき、忙しい方でもご自分のペースでやり取りが可能です。
施設の資料請求や見学日の調整も代行してもらえるため「仕事をしながら施設選びを進めたい」という方にもぴったりです。
ご家族で話し合うきっかけとして、ぜひ一度「マイナビあなたの介護」に相談してみてはいかがでしょうか。
著者・監修現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。
現役ケアマネ兼Webライター。介護施設長の経験を活かし、利用者・家族・スタッフに寄り添う記事を執筆。



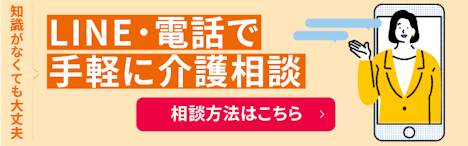
.jpg?w=600&h=346)